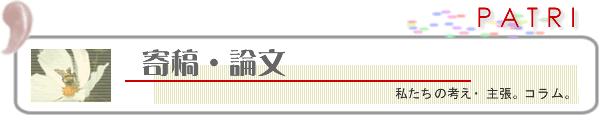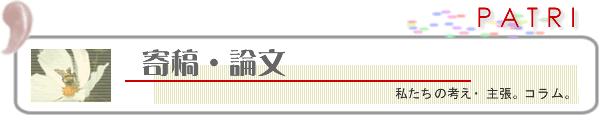30年目の我が「連合赤軍問題」総括
3章 連合赤軍問題から何を教訓とする
1節 たとえ「革命的」「人民的」という言葉がその前に冠されても暴力、軍事を美したり、絶対化したりせず、その自然発生性に拝跪しないようにーー赤軍派の軍事路線の模索とその軌跡の中での問題点の検証。
政治や経済、文化や思想の問題に於いて、暴力や軍事を絶対視してはならないこと、ましてロマン化し、美化したりするのはトンでもない思い違いである。
その事態に酔ってしまい、この世界の自然発生性に拝跪することは最大の危険である。
武器を持つこと、軍隊的集団を形成し、行動する事には、それに伴って宿命的とも言える自然発生性が生ずる。
7/6事件の際の塩見の仏氏への行為もその類である。
塩見達はあの件について、強制的要素も加わっていたが、即座にその自然発生性を自己批判した。
あのような即自的、生理的とも言える感情をすぐに冷静に捉え返し、反省して行く意識性が必要なのである。
そうすれば軍事に伴う未経験からの過ちは、その被害を最小限に止め、逆にプラスに転化させて行くことも出来る。
あの時トンコしていた森君はいざ知らず赤軍派フラックは「軍事に伴う自然発生性と闘う」ことを組織的に確認して行っていた。
暴力の発動、軍事、戦争は煎じ詰めれば『人と人の殺し合いの世界』である。
そこには「魔」が潜み、「狂」が氾濫する。
人はそこで、平時では考えられないような、トンでもない馬鹿なことをやらかすのである。
何故ならこの理想、理念を少しでも忘れたり、希薄化すれば軍事、戦争という条件下では
その思想的弱点が幾千倍にも拡大し、取り返しのつかない過ちを爆発させるからである。
ドフトエフスキーや高橋和己の「悪霊」の世界が日常茶飯に取り憑いてくるであろう。
人民の戦士、革命家も不断にこの世界に迷い込む危険が大いにある。
一寸先は闇であり、先のことは分からないし、どうせ死ぬのであるから、投機的になってしたい放題をやってみようという考えも1つの悪霊に取り憑かれた事態であろう。
それでは、軍事、戦争の世界は仁義なき闘いなのか?違う。
その世界にも仁義はある。
否!その世界でこそ、仁義は一層貫徹されるし、貫徹されなければならない。
あくまで人間解放、人民解放の大目的、大義が軍事、戦争の基礎に据えられなければならず、軍事を遂行する者にとって、この原則は一瞬たりとも忘れてはならないことである。
あくまで人間主義、労働者主義、愛郷としての民族主義(パトリオティズム)を基本とした人民主義、とりわけ人民大衆を中心とした知的、道徳的ヘゲモニーを確立する方向で「魔」や「狂」を追い払うよう努力すべきである。
そうすれば、つまり、正しい理念、理想、路線に沿って進めば別に悪霊の取り憑くしまは無くなってしまうことも歴史が示すところである。
悪霊は個人主義、個人利己主義、実存主義の彼方からやってくる。
であれば、人民の一人として、人民の隊列の中に参画し、人民大衆の闘いと結合する事、その要求、利益を実現することが人民の戦士として生き,闘い、創造する原動力となるように生きること、人民大衆の意見や人民大衆間の論争に耳を傾けることが比較的に正しい判断を得ることになる、と言った認識に確信を持つことである。
同志を大切にし、同志愛を育み、革命家集団内の信頼関係、団結の日々の具体的確証が生き、闘い、前進する意欲、志気の源泉であることを確信し、その為の努力をすることも最重要時の1つである。
「悪霊」や「狂」と悪戦苦闘しつつも、正しい世界観と路線に従ってアポリアを通りすぎて、後を振り返れば、そこには人類が進んできた歴史の大道が敷かれていたことがハッキリするように進んで行きたいモノである。
そしてこれと同時に次のことが併せて確認されるべきであろう。
とは言っても、軍事、戦争、武勇は歴史を構成する枢要の分野であり、その舞台に於いて幾多の英雄、豪傑、戦略家、戦士が登場し、勇壮にして絢爛、豪華なる叙事詩が如何に多く展開されてきたであろうか。
非暴力を唱えるにしても、この歴史的事実を無視するとすればそれは全くの愚かである。
非暴力思想はこの冷厳な歴史的実を踏まえて、なおかつ追求されるべきものであろう。
この意味では軍事、戦争は人間生活の日常であり、そこにはそこでの法則があるのであり、それに従えば人間は別に「悪霊」や「狂」に悩まされることもないのである。
「連合赤軍」や赤軍派等「革命戦争派」は、人民運動の面からその世界に入り込もうとし、そのとば口まで進み出て、敗れた。
この教訓は必ずや将来、なんらかの形で活かされるであろう。
だから、ひとたび軍事が目指された場合、軍事そのものとしては、勝利の為の正しい必勝の作戦を立てーー「革命的敗北主義」などの政治的には全く無意義なロマンに酔うことなくーーー勝利を目指し大胆、緻密、細心に徹底的に突き進まなければならない、と言った軍事的教訓はキチンと記録されておくべきであろう。
始めから負けを想定した闘いはやってはならないのである。
コマンド達の完全生還のための安全保障が用意周到に練られるべきである。
そしてそれは本質的には自衛のため、正当防衛のための暴力、軍事、組織だった集団的動機に基づかなければならない。
しかしその前に考えなければならない。
当時の武装決起の選択は絶対的とは言わないが正しかったにせよ、安易に「革命的暴力」等に走ってはならない、と言うことは、その判断の前提の前提に、しっかりと据えられなければならないのである。
このことは次の節で述べる。
又軍事、武装闘争を発動するにせよ、それを「戦争宣言」し、文字通りの戦争を遂行することと政治的な権力の不正義への糾弾、非合理への不服従、暴虐への不屈の抵抗意志の表明として発動するするゲリラ的武装行動、武装プロパガンダとは根本的に違うし、この区別はもっともっと厳格にされるべきである。
我々はこの区別が明瞭であったとは言えない。
又戦争行動と武装蜂起との政治的、軍事的連関と区別もしっかりされるべきであった。
赤軍派の前段階蜂起の蜂起的闘争は一斉総蜂起の武装蜂起とは意識的に区別されていたが尚より明確にされるべきである。
国と国、民族と民族の戦争と違って、階級闘争、人民戦争の国内戦の場合、もっともっと政治的諸関係に規定され、微妙で、可変的であり、様々な段階が想定される。
まして先進資本主義国の市民社会と国家の関係が膠状となり成熟している場合、人民大衆が主体となった政治闘争が中心となるのであって、戦争的な軍事が前面に出てくるのは、よっぽどに政治的的対決が先鋭化した時であり、それもその頂点においてのことである。
しかも、先進資本主義国の場合、一般に長期の内戦は可能性が少なく、バスク人の闘いやアイルランド問題、IRAのような闘いは民族闘争である。
フランスのレジスタンスのような外国侵略勢力に対する闘い、これ又民族戦争に於いてのことであり、階級戦争の性格のモノは殆ど見受けられない。
マルクスが「フランス3部作」で解説した「武装蜂起ーコンミューン」は、プロシャの侵略に対する売国者ティエールに対する闘いであり、これ又民族問題と言って良いのである。
階級戦争問題で、一番考えられるのは、内戦と言うよりは帝国主義間戦争で敗れた国での戦争を終結させるための権力者のパージなどが契機となった極く短期間の一斉武装蜂起である。
この典型がロシア革命であったことは言うまでもない。
日本でも敗戦の終戦時、共産党等主体が強ければその可能性があったであろう。
何故、短期間になるかと言えば、先進資本主義社会では如何に敗戦時とは言え、市民社会が確立し、人権、人命が尊重され、それが代議制民主主義の体制、システムに政治的要求が吸収され、一定の解決を見るからであり、血を流す内戦は、勿論短期間の流血に止める意図を持つ一斉武装蜂起すら民衆自身が忌避するからである。
武装蜂起は全国民、民族、人民大衆が経済的飢餓状況や極端な政治的無権利状態が続き、それが既存政治システム、執権勢力によって解決されず、支配勢力内部の軍隊、警察、官僚すら抜きがたい不満を鬱積させているような事態で必要とされ、正当であると言われてきたのである。
このような事態、非常事態を緊急に解決することが、合理的に確認され、それがコンセンサスになった場合であり、正に非常時の緊急処置に於いて、武装蜂起は承認されてきた。
であれば、戦後の現代日本社会では敗戦時以外蜂起は考えられず、今後に於いても、暴力革命、武装蜂起が現実的課題に登ることは極めて可能性が少ないと言えるし、この問題はより慎重に検討されなければならない課題である。
とは言ってもゲリラ的武装闘争の可能性、現実性が無いかと言えばそのことは又別問題であり、抑圧された民衆の武装的抵抗は社会の矛盾の凝集点で爆発するであろうし、そのような矛盾の深みは資本主義の至る所に存在し、このような矛盾と結びつき、武装的ゲリラ闘争が組織されないとは言えない。
資本主義はそれだけの抜きがたい深刻な矛盾を抱えている生産様式である。
しかし、その闘いは強固な民衆の団結、革命的な民衆としっかり結びついた国際的、国内的なネットワーク、組織抜きには存続し得ないし、自然発生的憤激に身を任せた武装闘争であれば、それが如何に正義であれ、哀しい結末を辿って行くであろう。
しかも、このような闘いは民衆の大規模な全人民的規模の政治闘争、中央権力を巡る熾烈な権力闘争、議会への民衆勢力の大規模な進出、生産点、地域に於ける人民ヘゲモニー、マッセンストライキの状況の事態を産み出す政治的プロパガンダの性格に於いてであり、あくまでこのような正規の陣形の中で、人民勢力の政治的闘いの補完物として、政治を捕捉するモノとして重要な役所を発揮するモノとして位置づけられるモノである。
それ自体が軍事上の殲滅戦を担い、権力の軍事勢力を「消滅」させることで、階級戦争に勝利すると言った類のモノではない。
政治闘争の捕捉物として軍事的にも殲滅目的ではないが高度に組織された政治集団は必要とされるだろう。
赤軍派は当初その政治を凝集する軍事的にも武装された集団を「共産主義突撃隊」(R・G
、赤衛軍)と名付けた。
「共産主義突撃隊」は政治的プロパガンダを目的とした半非合法、半軍事組織であり、都市での政治戦闘を補助したり、リードしたりする役目を負っていた。
70年安保闘争は第一次、第二次のそれに続く、第三次の戦後史を画する政治闘争であり、日本の進路を決するような性格のモノであった。
とはいっても、それが武装蜂起の類の闘いでないことは、政治的、経済的深さ、広さに於いてハッキリ明言できることであった。
赤軍派も又この闘争が「デモよりは遙かに大きく、しかし武装蜂起よりは小さい」といった形で、その闘争の規模、広さ、性格を表現していた。
そのような性質に於いて決定的な闘争を準備することを主張した。
だがこの闘いの軍事的性格、形態については明確な判断を示さなかったし、示せなかった。
現実の闘争過程で見定めて行こうとした。
玉砕的闘争を組織を賭けて追求する事に危惧を表明する意見もあったが、前段階蜂起は赤軍派が政治生命を賭けて追求した路線であり、それを撤回するわけには行かなかった。
それは最終的に「首相官邸の武装占拠」方針として確定された。
又赤軍派中央は政治局最高指導部がこの作戦の指揮官となることも検討したが、最終的に統合司令部の重要性を考え、残すこととし、弾圧をくぐり抜け、跳ね返しつつ次の戦闘や組織の再建を担う判断をした。
今でも、これで良く、「革命的敗北主義」と言った個人主義、実存主義の政治を引きずったロマンこそ反省されるべきと思っている。
人民の臨時革命政府的権力を宣言する声もあったが、討議対象とはならず、時の権力、佐藤政府 の専横に対する糾弾を決死的行動で表現し、人民大衆に佐藤政府打倒の決起を呼びかけるもの以上は出ず、その後についてはその時は方針はなかった。
もとより様々な状況からして、政治局の逮捕の可能性は高く、塩見個人も死刑は覚悟の上であったが20年の超長期刑を受けるような事態は想定していなかった。
又官邸への接近過程での武装遭遇戦に行くぐらいであれば、それでも最高の出来と30年後の今思いを巡らしているが、その当時はその企図、試行がどんな結末を迎えるかについての予測など立てる余裕は全くなかった。
ただただ後先のことは考えず夢中でそれに邁進していったのである。
結果は軍事技術上の初歩的未熟さから、幸か不幸か、大ドジとなり、大菩薩の軍事訓練の過程で挫折せしめられてしまった。
その後、徐々に「国際根拠地建設」の路線が浮かび上がり、準備過程に入って行く。
武装闘争、決定的な蜂起的闘争や武装闘争を永続させるためにはこのような国際的条件が必要と認識していったからである。
赤軍派は第二次ブントの「全人民的政治闘争」「中央権力闘争とマッセンストライキ」の基本陣形を守りつつ、それに「国際根拠地路線」を加えていったのである。
いずれも第7回大会の「過渡期世界論ー世界同時革命」の路線の展開であった。
70年に於ける前段階蜂起、その後の「国際根拠地ー連続蜂起」の路線は森体制にあっても堅守され71年末頃まで継承される。
これは「赤軍」第7号において明瞭に検証される。
そして、その路線は革命左派の70年末頃からの毛沢東「遊撃戦争路線」「銃を軸とする殲滅戦」路線、「山岳根拠地路線」が登場し、それに影響され、徐々に修正されて行く。
この後のことについては二章で述べた。
「共産主義突撃隊」は赤軍派が分派して行く過程で、ベトナム労働党の軍事指導者、ボー・グエンズアップに習い「赤軍」に改組され、「中央軍ー地方軍ー民兵」の三種に分化される
位置づけを与えられるが、これは第三世界型の戦争路線の適用で現実にあってなかったし、中央軍は「共産主義突撃隊」的な政治と渾然一体となって、政治闘争を推進する政治的組織者的性格が薄められ、純然たる軍事組織的性格になっていった。
それでも70年頃前半までは政治拠点の再獲得、政治闘争の追求が目指され、軍は「長征軍」と称され主として組織者の性格に重点化され、軍の位置づけは柔軟であった。
森指導部にあっては政治闘争の組織化は非合法化されることも手伝い、放棄されて行く。
拠点や地方組織はそれでも可成り独立自主で行動していたし、政治闘争の補助的役割を与えられていた「軍」は徐々にゲリラ隊の性格に変化して行くが、これまた「指導の集中と任務の分散」の原則に於いてだが、独立自主であり、そのことに於いて事態に柔軟に対応し得た。
しかし、森赤軍の場合、ゲリラ隊に赤軍派の指導は集中され、ゲリラ隊が情勢を切り開く主力に変質していった。
アルゼンチンの指導者、カルロス・マルゲーラの「都市ゲリラ戦争」の「教程」などが真剣に研究されたりもする。
「赤軍」第六号は都市底辺を根拠地とするゲリラ戦争路線を展開していた。
この路線が遂行されて行けば、事態はもっと違う局面を迎えて行ったかも知れない。
この事態は基本的には政治組織の「赤軍派」が本来の全人民的政治遂行の政治機能を
果たせず都市の労働者等人民の中に政治的ヘゲモニーを獲得する政治闘争に敗退した結果であり、その追認と言えた。
それは第三次安保闘争の終結の過程でもあった。
軍事の前に、否軍事のためにはそれに十数倍する政治的、組織的闘いが強化され、人民大衆の中に強固なヘゲモニーが創出される必要があった。
このような方向は、連赤敗北後の赤軍派の釜が崎や山谷ら寄席場を拠点とする中で幾つかの赤軍派系組織によって追求され、若宮・宮本達のグループはラーメン屋を開店しつつ数百の地下足袋部隊を組織し、「釜が崎現場共闘」などの先頭で闘う。
この中で水崎町交番爆破闘争が貫徹される。
この物語は「釜が崎赤軍 若宮正則物語」(高幣真公著)に詳しい。
以上は赤軍派の闘いを軍事、軍事路線を若干検証し、総括したモノである。
2節 軍事、暴力への自制と人間自主思想、非暴力思想の涵養、対人活動と団結
の要点
殺すより、殺さない道を選択しよう。
殺すぐらいなら、殺されても道理を貫こう。
殺されても、道理を貫く勇気こそ涵養しよう。
幼い頃、殺さないことの倫理を教え込まれ、それを真実に信奉した。
その人々が社会の不正、矛盾に気づき、殺さなくては不正をただせないと気づいた。
自分たちの生きている社会が幼い頃教えられた通りには動いてないことに気づく。
それをマルクス主義が理論的、思想的、政治的に検証していることも手助けとなったであろう。
そして70年闘争は暴力の復権から始まり、その後暴力の限界、それが醸成する荒廃に思い知らされる事態が続いた。
暴力を越えた、いのちと人間を大切にする非暴力の闘いによって、「殺し、殺される」悪無限の連鎖を断ち切る、これまでとは次元の違う哲学、世界観と闘いが創造されるべきことに気づかざるを得なかった。
「永遠の平和を実現する為の戦争を無くすための戦争」これは毛沢東の有名な命題であった。
果たしてこれで良いのであろうか。
その前に現実の今、人間と命を大切にし、人々一人一人の自主性、主体性に於いて人と人、人と自然の関係を変えて行く粘り強く、根気が要り、賢明で英知ある道こそが追求されるべきである。
毛沢東の時代、中国の状況ではそれが現実的に不可能と判断されたから、このような逆説命題が樹てられたのであろうが、このプロセスを通じ、資本主義を批判し続け、良き方向に変容させ、変革して行く道こそ追求されるべきである。
暴力革命や軍事組織の「中央集権党」による「資本主義の一挙的変革」の幻想から解放されるべきである。
人間は「自主性をもった社会的存在」である。
自主は独立自主で自分を大切にすること、自分にとっての要求から出発するが、それはとりもなおさず隣人関係、社会と自分との関係を通じて実現するのであり、これらの関係から切り離された「個我」は存在し得ようがない。
人間は、社会的関係性を通じて自己の自主が実現される主体的関係として、自己と世界の関係を創っている。
そうであるからこそ、そおいうこととして、自主を実現すべく、人間は赤子の時から、様々なことを様々に学んで行く。
人間は生まれ落ちるその以前から歴史的な社会と自然の中に胚胎され、この世に生まれ出る。
そして、社会的関係性を通じて自己実現を果たすことを学んで行く。
互いを自主性を活かし合い、また自主性を発揮して社会に尽くすことで自主を実現してゆけることを学んで行く。
社会的関係性を通じて自主が実現される主体的関係に自己と世界の関係があることを知って行く。
このことに於いて、隣人は他人ではなく、「自己の他在」としてあることを知って行く。
社会は本来自己の自主性を保障する存在としてあることを知って行く。
人間は人間になった時から社会の主人たらんと振る舞おうとし、それを通じて世界の主人、主体たらんとし、宇宙の命を体現せんとする存在であることを知って行く。
これらのことに於いて、人間は社会的関係性を隣人、社会構成員、社会や民族、国(クニ)の自主性を伸ばし、そのことで信頼と愛、協同の関係をつくりあげんとする。
或いは社会の関係、社会と自然の関係の歪み、非調和の関係を正すべく異議申し立てをして闘い続ける。
私有財産の階級社会では人民大衆に属し、自主と協同の関係を造りあげつつ、人民大衆を団結させ、そのことを通じて社会に責任を持ち、社会の主人たらんとする。
あらゆる側面を持つ人間、人民大衆の生活に於いてその側面、側面に応じて自主性を向上させるべく努力する。
人間の本性が自主性であれば、関係性の変革は唯一隣人、社会構成員の自主性の尊重に向かうし、強力の暴力による抑圧を否定する。
このことに於いて暴力を否定する非暴力を人間は目指す。
如何なる人も自主性を伸ばし、暴力によるその抑圧に反対することを否定しない。
であれば、武装闘争の根底に人間自主と非暴力が据えられるべきことは自明であり、それ以上に武装闘争に依らない直接の非暴力行動が第一に目指されるべきである。
だから、暴力や軍事をたとえそれが人民の利益を守る緊急事態として必要とされても、何よりも軍事に走らないことが基本原則とされるべきである。
たとえ、それがどうしても必要とされ、正当であっても、それを絶対化したり、美化したりしてはならないのであり、最大限の自制、そして「軍事の自然発生性」に流されることへの自戒がなければならないのである。
個人主義や個人利己主義、実存主義は根底に於いて「個我」の自己認識であり、それ故「人と人の間に架ける」橋はないものと思い、隣人を他人と思いこみ、強制に頼ろうとする。
個人主義、個人利己主義、実存主義とその強力、暴力に対して人間自主、信頼と愛、非暴力が対置され闘われなければならない。
「連合赤軍」は指導部の個人主義、利己主義、ニーチェ的とも言える実存主義によって、同志間の人間不信を極限までに拡大していった。
それは逆説的に如何に同志愛が求められているか、の思想的課題を真っ正面から投げかける。
それこそが人間自主思想であり非暴力録思想であったたと言える。
人間自主の思想、非暴力思想に立脚すれば以下のような諸点が人民大衆の団結の要点となろう。
1,『俺が俺が』『私が私が』の個人主義の自己絶対化を排し、最高価値として、人民大衆、社会と民族、人類の利益、要求に従うこと。
自信、信念を持ちつつも、他方で自己を常に相対化する思考を持たなければならない。
2,隣人、隣人グループの良きところ、共通性を認め、それを伸ばし、拡大して行くべく努力し、短所、違いをを良きところ、共通性を第一にしつつ、治してゆく。
違いだけを取り出し、それを拡大するようなことをしない。
3,それぞれの意見を尊重し、意見を数量で圧迫しない。
少数意見を尊重する。
4,敵を主要敵の1つに絞り、人民大衆の側の広範な団結を第一にする。
3節 野合の挫折を越えた階級派と民族派の正しい合流のために!日本人と日本を
愛する思想を!
人間主義、労働者主義と一体の愛郷の民族主義を!愛国者、愛族者たろう。
ーーー真の人民思想とは?
人間主義とは人間の自主性を社会的関係性を信頼と愛の協同の関係に変革しつつ開花して行くことである。
労働者主義とは資本主義の下での労働者階級の経済的、政治的不平等を打破して行く闘いである。
マルクス主義は労働者階級がこの不平等を打破していけば、そのまま自然に素晴らしい人間性を育んで行くとと言った誤った認識を持っている。
労働者主義が自然に人間主義を育む訳ではない。
人間主義が独自に育てられて行かねばならない。
その為には人間についての独自の自己認識、哲学的営為が必要である。
労働者を実体主義的に捉え、それを持って、そのままで人間性とするのは全くの間違いである。
とは言え、人間主義が労働者階級と結合してしか成長していかないのも又事実である。
しかし、真の人間性、労働者性は両者が結合されれば十分であるとは言えるであろうか?
真の人間性、人民性とは一体どのような要素で成立すのであろうか。
人民大衆が育ってきたその大地との関係で育まれてきた民族性、広い意味での文化、そしてそれを愛する心が、人間主義と労働者性に結合されなければ完全化しない。
この点で民族と国の自主は人間性と人民性の前提条件であるし、人民大衆は愛郷主義をベースにして、国と民族を愛し、そこに責任を持たなければならないし、自主権を完全なモノにすべく闘わなければならない。
連合赤軍は軍事至上で「社会主義革命」派と「反米愛国」派を強引に合流させようとして失敗した。
この企図は完全に正しく、人民運動の最先端に躍り出れば必ずこの問題に逢着するのである。
現在、対米従属のグローバリズムが跋扈し、主権の略奪が巧妙に進行し、民族のアイデンティティーの喪失が70年当時に比べ、圧倒的に進展している状況下で、このことは、70年時以上に圧倒的要求されている。
この挫折は人間自主主義や人民主義が希薄であったことと裏腹に個人主義や実存主義をその裏面に繁茂させていたことにも起因するが、もう1つとして愛国主義の欠如の問題があった。
そもそも、戦後「愛国主義」の問題が正しく総括されていず、赤軍派も革命左派もその根底で「民族ニヒリズム」の根を引っこ抜き切れていず革命左派の方も中国直輸入であり、赤軍派も「日本人の最良の息子、娘となろう」などと標榜していたが、政治上、思想上は国と民族への愛をまだまだ、封印したままであった。
そもそも、自分が生まれ育った民族と文化、自然・風土、故郷そして民族同胞を愛さずして、それが原点になくして、いかほどの自分たちの社会の向上が出来るであろうか。
人間を愛すことも、人民を愛すことも国と民族を愛すことと結びつかずして、いかほどの責任ある、具体的な行動が取り得ようか。
人類を愛すことや世界の人民を愛すことが、自民族を良きようにすることと結びつかずしていかほど世界に貢献し得ることになるであろうか。
この基本ベースを第一の確認とした上で、高度に発達した日本資本主義=帝国主義に於いてすら民族問題が存在し、それを新しい性質の民族問題と捉え、解明、創造的解答を引き出すことに「連赤」も赤軍派も革命左派も理論的にも思想的政治的に答えきれなかったこともある。
愛郷主義に根ざす人間主義と人民主義を持った、従って国際主義で持って開かれている民族性、パトリオティズムを育成することである。
人間主義、人民主義をベースにした国際主義を持って開かれた諸民族の連邦、人類社会が成長するに応じつつ、それぞれの社会は宇宙の命が貫流し、溢れる社会となって行くであろう。
4節 日本人民の実践に照らし、自分の頭で、自分の言葉を持って考えよう。
ーーーマルクス主義、レーニン主義を相対化しよう。
連合赤軍問題にマルクス主義、レーニン主義の核心部分が影響をあたえていることを述べざるを得ない。
当時先進的活動家、コミュニストを自認する人々がマルキストであったことは紛れもない巨大な事実である。
「二度と侵略戦争をしない」「反戦、平和、民主主義」を志向した大半の人々がマルクス主義の影響下にあったのである。
そして、あれから30年、中国の路線転換、ソ連・東欧の崩壊、「冷戦体制の崩壊」という歴史的事態の展開の中で、マルクス主義、レーニン主義がある一定の時代の人間解放・人民解放の世界観ではあったが、普遍的世界観ではなかったことが歴史的に露呈し始めた。
マルクス主義も又相対的なイディオロギーであり、広松渉流に言えばある時代、人類を捉えた「共同主観」であった、とも言える時代が到来したのである。
勿論マルクス主義はある地域に於いては今でも有効であり、相対的には世界的にも有効性を完全には失っていない。
しかし、今後マルクス主義がイディオロギーの玉座を奪回して行くことはあり得ないと思われる。
ブントも新左翼も第二次ブントも赤軍派も革命左派もそして森や永田等「連合赤軍」もみんなマルキストを自認していたのであった。
そして、マルキストはあらかたマルクス主義をマルクス主義とレーニン主義を一続きの世界観、革命思想と見てソ連式に[マルクス・レーニン主義者]としていたのである。
勿論この説に異論を唱えたりする人々、流派もあり、この「主義者」の中も5流13派、沢山の流派に分かれていたのも事実である。
まあ、しかしこんなことは本題ではどうでも良いことである。
重要なことは、「マルクス・レーニン主義」の大枠、パラダイムの中で活動家達が、思考し、行動していた,というと言う歴史的事実の確認である。
そしてご多分に漏れず、赤軍派も革命左派も「連合赤軍」もこのパラダイムの枠の中に在ったということである。
マルキストの間にもいろんな解釈があったにせよ、次のことはどうしても揺るがせに出来ない命題と言えた。
1,敵、味方を生産手段の所有関係で線引きし、分けること。
この所有関係を巡る関係は「非和解的」である。
無所有で労働力を売らずしては生きていけない人々が革命の本隊である。
2,この「非和解的」と言う言葉はレーニンの言葉であるが、そしてそのレーニンは「国家と革命」の中で、「国家を階級対立の非和解性の産物」「国家は階級支配の道具」と断じ、ここから「暴力革命の不可欠性」を主張している。
このような「ロシア・マルクス主義」程問題を単純化し論じていず、国家論等にはいろんな解釈があり、その中には「権力の平和移行・平和革命」を説く流派も発生したが、それ故マルキスト内に様々なバリエーションがあったことを認めるにやぶさかではないが、マルクスその人すら「プロレタリア独裁」を説いているように、その政治学説の骨組みには厳然として「所有関係」→「階級対立の非和解性」→「国家の階級性と暴力支配」→「暴力革命」と言う図式は存在していたのである。
この図式は欧米先進資本主義国では実現しなかったが、ロシア、中国、アジア、アフリカの第三世界の半封建的、植民地国の極端に貧困で、政治的無権利状況の国では実現されていった。
先進資本主義国では実現されはしなかったが、それを信奉する人民大衆は広範に存在した。
革命後のソ連に於いても、共産主義の理想とはほど遠いか、全く無縁であったが、「プロレタリア独裁」の名の下にスターリン等「党」官僚が専制政治で強硬的に「上から」工業化する近代化戦略に利用されもした。
「革命」を冠した「強権の暴力」「暴力革命」がその高い理想主義と裏腹に、マルクス主義 の切って切り離せない実際であったことは今ハッキリ承認されるべきである。
3,「所有関係」→「非和解性」→「暴力革命」に連動する回路を断ち切る「原理」「論理」は残念ながらマルクス主義の中には何処にもないのである。
僕はこのことを「幸福論」で究明し、これを断ち切っていける原理を「人間の自主性」を拠点に展開したわけだが、そのことは今は措くとして、70年当時ブント等新左翼はこの図式を否定しないばかりか、逆に「自分たちこそがマルクス主義を復権し、実行する」と主張していたのである。
この点では毛沢東思想派も違った視座からではあるが、同じような主張を「ソ連現代修正主義批判」として展開していたのである。
4,そしてこの図式を実現する組織として、レーニン主義の影響、ロシア・マルクス主義の影響で「中央集権党」の建設を疑わなかったのである。
なぜ、このように「中央集権党」になるのか。
明らかに上記図式に従った場合、暴力革命、武装蜂起を準備して行く、必要があったからである。
職業革命家で構成される「労働者階級の意識的部分たる、前衛で構成される『党』」と言う図式である。
つまり、軍事組織が必要とされていたからである。
このような組織論が革命運動を前進させもすれば、他方で幾多モノ筆舌に尽くしがたい、粛清や査問等非人間的事態や組織悪、人間悪を不可避に産み出していったと言える。
そもそも、このような組織は最初レーニン等がツアリー専制権力と闘う為に、代議制民主主義も存在し得ない前近代的社会状況で考案したモノであり、ロシアの特殊事情による側面が強調されていたわけだが、後コミンテルンを通じ全世界に伝播されていったのである。
マルクスの「インターナショナル」の組織はそうではなかったし、欧米では比較的早くに「近代民主政党」「合法政党」に衣替えされていったわけだが、アジア等第三世界ではもっともっと非合法で、軍事的な上位下達組織であった。
新左翼では「革マル」の「他党派解体」の組織戦術が常に内ゲバを将来させていた。
これは黒田寛一の宗派主義的組織論と言った日本的要素があるのだが、毛沢東思想派も粛清を原則的に否定してはいなかったのである。
ブントは「中央集権制」を否定してはいなかったが、それを定式とはせず、未だ未完成で、どちらかといえばマルクス組織論に近く、もっとも人民大衆の利益を第一にし、運動を第一にする連合的組織イメージであった。
以上を前提にして赤軍派や革命左派、「連合赤軍」を考えて行く必要あるのである。
それは、どおいう意味合いにおいてか、であろうか。
つまり、彼等がある面では最も理論的には忠実に、この「暴力革命」論を信奉し、実行しようとしていたという、意味に於いてである。
そしてその事に於いて「中央集権党」に伴う迷妄たる「粛清」の罠にはまり込んでしまったと言うことでもある。
世間には今でも、マルクス主義を信奉をしている「マルクス』護教論者はゴマンといる。
このような人々は、「彼等、赤軍派も連合赤軍も、マルクスをしっかり理解してなかったからだ」と言うだろう。
このような輩に限って立派で優秀な「マルクス」学者も沢山いるが、実践は何もしていず、マルクス学で飯を食っている連中が多いのであるが、大体は「マルクス読みのマルクス知らず」なのである。
事実は「構造改革」系も含め、新左翼系はブントに限らず全党派が武装闘争に手を染め闘ったと言うことである。
内々ゲバも内ゲバもしっかりした反省も持たず、花盛りであったのである。
当時「暴力革命至上主義」は新左翼のコンセンサスであったのだ。
このことは、当時のベトナムを巡って、アメリカ等国際帝国主義と世界の人民大衆が世界規模で大激突し、日本でも500万人規模の人民大衆が立ち上がっていたこと、このような情勢の反映であるが、その闘いをマルクス主義から捉えていた、と言うことが大きい。
日本の青年達のラジカリズムがマルクス主義に名を借りつつ爆発していった、と言うことである。
武装闘争が持つ"魔""狂"が伴う領域に、勇敢で良識があったが故に、或いは人民大衆に献身しようとする想いが強ければ強いほどに、当時の最も良質な青年達は彷徨いこんでしまったのである。
情熱だけは根限りあるが、20代半ばの青年達であれば未熟で、頭だけでっかちである青年達であれば誰でもが迷い込む可能性はあったのである。
しかも、先進資本主義国で武装闘争を実行しようとする場合、その失敗度は高く、誰もが大なり小なりの失敗をやらかすのである。
当時の世界を見渡せば、文革中の大規模な暴行、殺人、そしてカンボジアのポルポトによる大粛清と挙げるに枚挙がないのである。
このように見てくれば、「連合赤軍問題」は決して個人だけに基づく事件ではないことは明らかであり、我々はレーニン主義、マルクス主義に遡ってまでこの禍根を断ちきっていかなければならない。
マルクス主義の脱構築、相対化こそが連合赤軍問題総括の決定的ななウエイトを占める内容とならなければならない。
マルクス主義のパラダイムの中では、連合赤軍問題の根元的解決は図れない。
この点で人間自主の問題や非暴力の問題は大きいと言わなければならない。
マルクス主義が帝国主義の植民地主義や資本主義国の労働者の生活向上、「労働者国家での何はさておいてモノの社会保障、近代化」らに強力な武器となり、つまり極端な経済的不平等を打破する、最後の人民大衆の鋭利な武器となり、最後の隆盛を極める時代がベトナム攻防を巡る時代であった。
そして隆盛から残照を漂わせる時代に、わが日本人民はマルクス主義を指針として70年安保闘争を闘ったのである。
そしてマルクス主義の栄光と悲惨はその象徴的事態を悲劇的な凄絶さを持って「連合赤軍」に帰結させて行ったと言える。
この時代をくぐり抜け、人間の世界に占める地位と役割に於ける主人性が確認され、人間が世界の客体ではなく、世界の主体として輝き、宇宙の命を体現できるような21世紀の到来に際し、マルクス主義は超克されなければならない。
組織が目的と手段に悪無限に分裂するような事態は根本的には人間の本性を自主性に置かず、組織そのものが自主性を目指すことに於いて自己目的であるようなモノになっていないからである。
人間自主・人民主義・愛郷の民族主義・非暴力思想を導きにあらゆる教条を排し、日本人民大衆の経験、実践に照らし、自主独立で自分の頭、自分の言葉で人間解放・人民解放を語らなければならない。
日本左翼の自主独立、自力で物事を考え抜いて行く作風こそ全力で涵養されて行かなければならない。
もう僕たちの世代はそのようなことが出来る年齢に十分達したのである。
12名を始めとする「連合赤軍」の人々の苦闘は必ずや活かされていかなければならない。
4章 あれから30年たってーーー21世紀を担う青年達に伝えること
これまで能うる限り、資料を調べ直し、多くの人から事実関係を聞き、自分の体験を記憶から引き出し、事実過程をたどってきた。
自分や赤軍派、革命左派についても極力真実をさらす努力をしてきた、その上で物事の正邪、理非曲直を定めてきた。
このことについてはいつも「厳しすぎる」「お前に何ほどのことが言えるのだ」「もっと語り口に優しさがあっていいものではないか」と言う内心の声が聞こえてきた。
しかし、それと同じくらいの比重で死んでいった12名への想いがあった。
彼、彼女等の無念の思いが脳裏をよぎり続けた。
殺された人、殺した人、総責任者としての僕の責任の自己追求や獄中の同志達の関わり、僕の中の自己分裂は続いてきた。
しかし、僕なりにひとまず決着付けなければならぬ
責任感もあった。
物事の正邪、理非曲直にひとまず決着を付け、連合赤軍問題総括論争に僕なりに終止符を打つことを決断した。
しかし、実際は僕の30年間経っての想いはそんなところに実はなかったのである。
事実経過の解明と理非曲直の判断の向こうにあった。
しかしこのことはこのことでしっかり30年を踏まえて、確定しておかなければそこにたどり着けない、こともはっきりしていた。
あれから30年たっての自分の思い、認識は何処にあったのであろうか。
1,「連合赤軍の」の青年達は世の中の不正を正そうとし、必死で一途に生きた日本人民の最良の教養と良識をもった勇敢で献身的な青年達であった。
とりわけ12名はそうであった。
2,同志殺しは許されない過ちであり、それは森君や永田さんの利己主義に基づくモノであった。
しかし、それはあくまで人民内部の過ちであり、利己主義は赤軍派や革命左派の政治、思想路線の限界、人民解放の大道から逸れた誤った「遊撃戦」路線や山岳根拠地路線とスターリン主義的処断方式の採用、決定的な野合判断の過ちらの判断の過ちからくる日和見主義に起因するもので一時的なモノである。
森君は逮捕されて反省し、自決で、自裁し、永田さん、坂口君は死刑攻撃に今でも闘い続けている。
森君、永田さんを含めた12名を始めとする人々は人民の戦士達であった。
3,「共産主義化」は森、永田の利己主義に基づく自己権力確立の為の「粛清」であったが副次面で「革命兵士になるための自己錬成」の側面があったこと、とりわけ12名において。
4,「連合赤軍」の根底の根底に於いて「自己を自傷しつつ、人柱になって」人間解放、人民解放を実現せんとする、殉教の精神があったこと。
5、「銃撃戦」は、山田や坂口、板東等によって正され、その自己批判、贖罪として闘われたのであり、彼等が人間解放、人民解放を目指していたことの厳然たる証であり、この点に於いて評価されるべきである。
5,事件は巨視的に見て、日本や世界の人民運動の負の側面、マルクス主義の限界、欠陥の蓄積の上に発生したモノで森君や永田さんの固有の「資質」に依るもではない。
権力者の社会背景や人民運動の歴史的要因を無視する「資質論」は断固として否定されるべきである。
しかし、事件の要因の重要な比重として、二人の指導者としての器量、経験、行動や思考法等のの特殊要因が決して無視できない要因として存在する。
この特殊要因を基底還元主義的に程度、質を踏まえず赤軍派やブント、或いは革命左派、毛沢東思想、マルクス主義や人民運動全体に還元するするのは誤っている。
特殊と普遍を統一的に正しく捉える努力が必要である。
この点を踏まえて、日本社会、日本人民運動の負の伝統、要因が二人にどのよな影響を与えてきたかも究明されるべきである。
6,ベトナム人民の闘いは勝利し、それを抑圧し、侵略してきたアメリカ帝国主義、それに加担してきた日本独占資本主義は敗北し、両国は「統一ベトナム」を承認した。
日米安保が如何にベトナム侵略、アジア抑圧に機能したかは明きらかであり、人民の側の反安保闘争は正義の闘いとして勝利したのであった。
佐藤政権、その官僚である後藤田、そしてその部下であった佐々惇公などに正義はなかった。
彼等が「売国奴」とか「凶悪殺人犯」とか、「狂信のテロリスト」とか誹謗、中傷する権利は全くない。
連合赤軍は過ちを犯したが、この正義を貫いた人民の側にあった、ことは決して忘れてはならない。
「連合赤軍」を彼等権力者達が裁くのはトンでもない茶番劇であり、30年たった今も獄につなぎ、死刑攻撃を続けるのは許されないことである。
裁かれるのは彼等の方である。
どうか、その時生まれていなかった青年諸君!いろんな予断と偏見に取り囲まれて成人せざるを得なかった青年諸君!21世紀を担う青年諸君!
「連合赤軍」は、大きな致命的過ちを犯したが、理想と正義に燃え、必死で人生を一
途に生きた青年達であったことを忘れないで欲しい。
我々は連合赤軍問題の過ちを襟を正して受け止め、その教訓をしっかり身につけて進むむ。
何よりも人間を大切にし、人間の可能性を信じ、人間の自主性を原点とするとする政治を行う。
非暴力を実行する。
人間主義、労働者主義、愛国主義の人民大衆中心の政治を行う。
日本の人民の側の政治は大胆に路線転換しなければなりません。
新しい真にラジカルな日本の未来を担う大衆的な人民政党があの鉄火の70年闘争の正と反を正しく総括し、新しく創建されるべきである。
アメリカ帝国主義の覇権主義、グローバリズム、それに追随する売国主義者達の従属覇権、金権と腐敗の政治を一掃する日本救出の闘いが始められなければなりません。(了) 9月6日記す。
 第1章へ戻る
第1章へ戻る
 第2章へ戻る
第2章へ戻る
 目次へ戻る
目次へ戻る