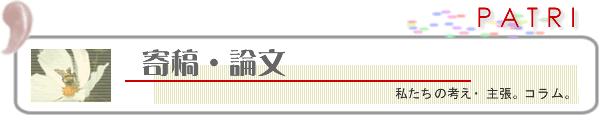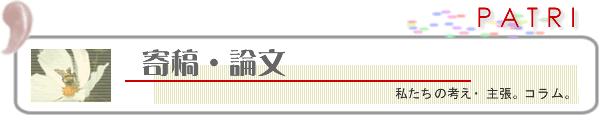30年目の我が「連合赤軍問題」総括
1章 問題の設定。
1節 「30数年に際し、連合赤軍問題を考える集会」実行委員会を開催してみて。
7月17日、「30周年に際し、連合赤軍問題を考える集会」準備実行委員会が結成された。
旧赤軍派や革命左派或いはブント系の政派やこの問題の関係者、関心を持つ人々、若い青年達等、準備をする人たちが集まった。僕は発起人として、この実行委員会や集会を提起した。
これから約4ヶ月弱各方面の人々に集まっていただいたり、意見を聞いたりし、集中的に総括運動をやり問題を煮詰め、他方で闘いに倒れた人々への追悼の想いや、今も弾圧を受けている人々への連帯と行動を凝集していきつつ、この問題の正しい総括をやりきり、権力側に相当独占されて来た「連赤総括」を民衆の側に奪還し、現政治状況の反動攻勢を打ち返そうと思ってのことである。
「"共産主義化"と銃撃戦」としてあった連合赤軍事件以来30年が経ち、総括の主体的条件がある程度成熟し、様々な経験が集約されていく場が提供されれば、それぞれが刺激されあい、よりトータルで正解に近い解答がなされるのではと思ってのことでもある。
僕にとっても12名と改めて向かい合い、追悼する中で、自分の到達点を様々な人々と対話し、確かめ検証していくことは、自分にとっても教えられるところ大であり、自分の総括運動の過程を連続的に捉えられるようになったり、判断留保点の穴を埋めたり、踏み込みきれないでいた領域に踏み込み始められたりし、この実行委員会運動は大いに役にたち始めています。何よりもこの問題を考えつづけている人達が存在し、この問題に関心を持っている若い人々がいることを確認できることは、何よりも勇気づけられることです。
若い人たちが現在の到達点から、この事件を批判的ながら、追体験的に理解し、より現在の到達点を深く、豊富に理解してくれ、現在の彼等の問題意識に回路付けし、問題解決に進み出てくれるとすれば僕にとっても望外の果報である。
この問題は新左翼運動の主流とも言えるブント運動から生まれた点や、毛沢東思想、いわゆる "正統派" 日共系の中国派から生まれた点でも規模が大きく、三つの安保闘争のうち、三番目の闘争の頂点であったことからして戦後史を画し、しかも戦後世界体制の犠牲的基底であった植民地体制を打ち破るベトナム解放を巡る反帝国主義、反植民地体制打破の世界人民運動の一環であった点でも、世界史的意味をも有している。
であればそれに照応するモノとしてこの事件の総括は規模が大きく、底深く奥行きが広く根本的になることは当然である。
2節 これまでのプロレタリア革命主義や「封建的社会主義批判」らの総括過程とブント急進主義を「観念主義、主観主義」と矮小化し、それを「連合赤軍問題」に直線的にあてはめる清算主義の意見・毛沢東教条主義、革命左派の要因を無視してはならない。
・ブント、赤軍派急進主義は如何なるもので、如何に総括されるべきものか。
総括はいろいろな観点からなされて来たし、今もなされ続けている。
イ、革共同主義を批判的対抗軸としつつブント急進主義やその観念性、軍事至上主義を総括する観点。
ロ、スターリン主義、毛沢東教条主義や野合の問題、或いは
ハ、運動、運動主体の階級的性格からプチブル革命性をプロレタリア革命主義に脱皮し、資本主義批判、労働者階級の生活要求、感情、階級苦を理解し、この階級の変革の社会的能力を信じ、これを培って行く問題。
ニ、日本資本主義社会の特質、対米従属打破、反安保、国と民族の自主、天皇制的特質と結びつけ反差別、人民の民主、自主と協同の社会性を養ってゆく問題、「封建的社会主義」の克服の問題。
これらの観点は基本的に正しく必要なことである。
しかし、批判としての指摘は正しくても、それだけで終わってしまうような「批判的批判」の観点もある。
批判的な指摘の上でそれを克服する内容的観点が必要である。
ブント急進主義、赤軍派急進主義は、その急進主義(ラジカリズム)体内に生来的とも言える形で、体質化していた負の側面、個人主義(個人利己主義)、実存主義、階級的性格に於けるプチブル性を、階級主義に置き換えることなく、人間主義それ自体として克服する思想的問題、 或いはプチブル的空想的社会主義革命の意義と限界を止揚する、日本社会、日本資本主義社会の普遍性と特殊性を綜合した真に現実に合致した政治路線、組織と変革陣形(軍事の問題も含む)を確立することに於いて、その中にあるエッセンスのラジカリズムを掬いだし、開花して行かねばならない。
ラジカリズムとは根底的、本質的と言う意味である。
或いは注意すべきは次のことである。
事実関係に於いて、この問題にブント急進主義が働いていたとしても、事件を形成する極めて大きな要因に、毛沢東派、それもスターリン主義を奉ずる部分との野合の要因があったこと、そしてそうである以上、単純にそれを無視して「ブント急進主義の延長」で裁断しようとしても裁断しきれない部分があること、このことは決して無視されてはならないのである。
「共産主義化」として論じられている、「同志殺し」のおどろおどろしい部分は、ブント的、赤軍派的急進主義の「雰囲気」とは違う、毛沢東的文革時の紅衛兵の「つるしあげ」「引き回し」の残酷さを越えたスターリン主義の個人崇拝-人民裁判-殺しとしての粛清の、より凄まじいおどろおどろしさ、残酷さが漂っていること、或いは革マル主義の「反スタ・スターリン主義」の党至上主義が見受けられることを留意すべきである。
森思想は毛沢東的な性格も持つが、スターリン主義政治を奉じる永田の「粛清政治」を彼流の右翼体育会的シゴキ思想、良く言えば日本的な武士道思想の「清明心」獲得の修養思想で覆っていた側面があり、ブントや赤軍派の組織性に於ける自由主義性を見限り、清算するものとして革共同的リゴリズム(*注 厳格主義)、党至上主義をスターリン主義の「鉄の規律・一枚岩主義」と融合させつつ持ち込んでいた事実があることに留意すべきである。
これらを「ブント急進主義の極限」などとすり替えられてはたまったものではないのである。
このように、安易、軽薄に「ブント急進主義」を捉えるとすれば、ブントと赤軍派への侮辱と言い得る。
ブント・赤軍派の思想はあの69年11月5日、大菩薩峠に結集して遺書を書き残して、首相官邸武装占拠を目射せんとした60数名の人々に体現されており、 「よど号」闘争の田宮達に現れ、リッダ闘争に現れた奥平、安田、岡本に現れていた、と言わなければならない。 僕は(イ)や(ロ)を総括視点に押さえつつ、主として(ハ) の問題を総括内容の視点に据え約8〜10年近く活動してき、その後これを踏まえつつ(ニ)などを強調してきた。
いずれも、これらの課題はマルクス主義のパラダイム、思考枠に基づいてのことである。
このプロレタリア革命主義、「封建的社会主義の克服」の観点は僕の思想的営為に置いて今でも骨がらみの根幹にずっと今に至るまで座り続けている。
そして、この5〜6年それを踏まえつつも決定的な質的次元に一歩踏み込む必要を痛感し、その機軸に人間自主の思想、非暴力思想を据え、これをベースに階級主義と一体の民族主義を新たに加えた人民主義、人民主体思想を考えるようになった。
このような基本観点、機軸を持った「マルクス主義の脱構築」を考えるようになった。
3節 武装闘争の歴史的必然性を踏まえ「連合赤軍はどのような限界に於いて敗れたか。
あるべき武装闘争とは?」ーーー「覚悟」としての人間自主思想、人間主義/労働者主義/民族主義/の綜合としての人民主体思想、超暴力としての非暴力思想
いずれにしても僕が総括運動で闘ってきたのは、次の二つの見解である。
70年安保闘争、反ベトナム侵略闘争に於いて、運動の政治的性格、運動の攻防プロセスからして武装闘争の歴史的必然性があったこと、この歴史的必然性を踏まえた上で、どの様な武装闘争が闘われるべきであったか?
「連合赤軍はどの様な問題、欠点、限界に於いて、それに敗れたか」と言うことが基本的な総括の問題設定であり、「武装闘争の歴史的必然性はなかった」とする見解には与しない、と言うことであった。
武装闘争をやれば必ず粛正、または「同志殺し」=「粛正」、「粛清」=「同志殺し」の反動的思想運動、または「共産主義化」が伴う、というのは謬論である。
外部の人民を「誤爆」したり、敵に必要以上の残酷な仕打ちをしたり、民間人を「誤爆」したりする過ちも、また犯してはならない過ちであるが、味方のそれも同志を「殺す」のは如何なる位置づけであろうとやってはならないのであり、「変革主体」が如何に変質、腐敗、荒廃、錯乱しているか、してゆくか、の現れとも言える。
変革主体を自認するモノであればあるほど、絶対に犯してはならない過ち、と言える。
「同志殺し」など無くても、人民大衆を鼓舞する闘いは、やれたはずであり、現にそれに近い闘いはなされた。
「よど号」闘争も、「人民を盾にした」過ちはあったが、人民を鼓舞したし、革命左派の柴野君達の12・18闘争もそうであった。酒井同志の6・17闘争もそうであった。
民間人を巻き込んだ面はあったが、それは無差別なモノでなく、管制塔占拠の攻防の過程で発生した、国際主義精神に溢れたリッダ闘争もしかり、渋谷暴動での星野君の闘い、9・16三里塚東峰武装闘争もしかりである。
磯江君の非道警官誅殺闘争、黒ヘル諸君のツリー爆弾闘争も、しかりである。
しかし家族を爆殺した土田警視総監邸の闘争、「反日武装戦線」の民間人を巻き込んだ爆弾闘争などに典型にみられるこれらの武装闘争も、また幾つもの根本的欠陥、限界を有していたのであり、このような欠陥、限界は克服される必要があった。
或いは「内ゲバ戦争」を伴った中核派の武装闘争もまた思想的、政治的限界を孕むモノであった。
「連合赤軍」はこれらの武装闘争の中でも、より本格的な武装闘争、「正規の人民軍」による「銃を軸とする殲滅戦」、本格的な「遊撃戦争路線」を標榜、追求した。
このような性質の武装闘争路線貫徹のためには、その主体に極度の思想的緊張と修練を要求することとなり、その課題に連合赤軍指導部は正しく応えられなかった。
暴力による殺しを伴ったスターリン主義恐怖政治、スターリン主義的「修養論」の反動的「思想運動」を持ち込み、同志を「亡きものにする(殺す)」といった、変革主体形成ではやってはならない基本原則から逸脱することで解決しようとしたのである。
ここに武装闘争派の思想的政治的、軍事的、組織的、変革陣形上の過ち、弱点が集中的に露呈、暴発したと言える。
本格的な武装闘争、銃で武装した正規の軍、建軍を目指す変革主体に於ける過ちゆえに、しかもその過ちに烙印されて――決してそれは「粛清」の延長線上に実現されたモノでなく、その自己批判の上に実現されたモノであったが――正に「銃による殲滅戦」が貫徹されたが故に、その過ちの社会的衝撃は倍増され、甚大で人民運動を一挙に大後退させてしまう結果となった。
だからこそ武装闘争をやる上での、正しい思想路線、政治路線、軍事路線、組織建設、それを踏まえた変革の総陣形が追求されるべく「連合赤軍問題総括」が30年たった現在でも問題にされるべきなのである。
時代が変わり、僕は現在「非暴力」を主張している。
しかしこの「非暴力」は当時の「人民の革命的暴力」の歴史的意義を清算、否定している訳では決してない。
このような70年闘争に於ける武装闘争の意義と限界を超克する観点として、超暴力としての非暴力を主張しているのである。
僕の「非暴力論」は「正しい武装闘争の思想、政治路線」の追求と超克の結果、導かれたモノであり、「革命的暴力」を排除しない。
厳格なる正当防衛の上に追求される、べきということを排除しない。
というより、人民の最も基本的な本性的権利,自主権の擁護の為に、暴力を越えた厳しく、真の意味でラジカルな非暴力の政治の闘いが、徹底追及されるべきこと、つまり「超暴力としての非暴力の政治」が追求されるべきこと、を主張しているのである。
言い換えれば、あの酷寒の山岳での「共産主義化」運動に真正面から応えんとして亡くなっていった12名の戦士達に代表的、萌芽的に体現されていた人間自主主義、階級主義、民族主義を綜合した人民主義、これと一体の「人を殺さず人と人の関係を変えて行こう」とする、暴力を越えての変革を目指そうとする思考、そしてその逆説、背理として敢えて「殺すこと」を承認せざるを得なかった思想的営為の重み、重い々思想的試み、もがきの捉え返し、対象化として述べているのである。
その人々は戦後民主主義、反戦平和、基本的人権、主権在民、より良き生活を目指した
戦後人民運動の担い手、世代の最良の部分である。
人を殺すことを絶対的に忌避することをもっとも純粋に幼い頃、教えられ、信奉した人々であり、長じて「人を殺さざるを得ずしては社会悪をなくせない」ことを知り、不殺生と殺生の矛盾に悩み、もがき、敢えて武装闘争を受け入れ、にもかかわらず殺さないことを忘れず、「あるべき武装闘争」を真に追求した人々と言える。
「あるべき武装闘争」は暴力を越える非暴力思想を基本ベースに本質的に据えており、このような基本ベースを「超暴力としての非暴力」として意識化し、継承しようとしているのである。
指導部は「銃による殲滅戦の覚悟」を、自らの個人主義、個人利己主義、実存主義の下に「精神主義的決意」として提出した。
敵を殺すことは翻って殺されること、死ぬことであり、その覚悟を要求した、のである。
個人主義は「単独個」「個我」であり、「人と人をかける橋は無い」モノと思い、隣人は他人であり、「利用のための手段」「け落としの対象」であり、集団もそうである。
であれば「集団は支配のための権力獲得の対象」としてあるのみである。
ここでの「武装闘争の覚悟」は弱肉強食の競争世界でしかない。
このような思想、関係世界では生命の重さ、人間の尊厳、人間の自主性、協同性は後景化するか、どこかに消し飛んでしまう。
革命の信念は宗教的神秘主義にとって替わられてしまう。
人の死生の覚悟は「その人がどれほど隣人から必要とされ、信頼され、愛されてきたか」「所属する集団から必要とされ、信頼され愛されてきたか」に因る。
或いはこのような関係性を普段から作ってきたか、そのような関係性を変革してきたか、に因る。
人はこのような人と人の関係性、人と集団の関係性の充実度、十全性において死ぬことを覚悟するし、自然なモノとしてその覚悟をする。
物質だけの問題でも無ければ、精神の問題でもなく、唯物論を踏まえるにせよ、唯物論と唯心論の二項関係を越える人間の自主性を原動力とする関係性の変革の問題である。
「士は己を知る者の為に死す」と言うことである。
「人間は自主性を持った社会的存在」なのである。
このことは「人間を社会関係の総体、階級関係であり、階級性に烙印されている」(後期マルクス)でもなければ、「自然と人との関係に於ける、(労働の)受苦的関係としての疎外」と言った宗教的な性格を帯びた疎外論(初期マルクス)でもないのであり、「人と自然の関係」「人と人との関係」を綜合した「世界(自然、社会、意識)に於ける、人間の地位と役割としての自主性、協同性を人間性の本性と見る」人間観である。
「覚悟」の問題は「同志愛」の問題であり、隣人愛、同胞愛の問題であり、変革に於ける恋人、家族、友情の問題はその関係性においてクリアーされる問題である。
しかし指導部はその共通性としてある自主と協同性、信頼と愛の関係を目的に向け押し広げるのではなく、支配のために、そのなさを強調し、「階級的献身度」の違いを押し広げ、敵対矛盾化していった。
隣人関係と集団に於ける、隣人の自主性を如何に伸ばすかに於ける、関係性の変革、非暴力の関係を打ち壊し、消滅させようとしたのである。
労働者階級は資本主義の下で搾取、隷属され、資本関係を憎み、それを変革、打破し経済的平等を実現せんとする。
しかしその為にはその階級的同胞の関係、階級集団での隣人愛、諸個人の集団の中での適材適所を確定し団結しなければならない。
これは、資本関係から独りでに発生するものでなく、人間自主の人間観がなければならない。
或いは労働者階級以外の他の階級との自主と協同を通じ国や民族に於ける責任を果たさなければならない。
人間自主主義、階級主義、民族主義が綜合される人民主義を創造することで始めて変革主体となり得る。
マルクスは階級主義の問題は強調したが、その底の人間自主主義は言わず、階級を成立させている民族への責任、その自主化は言っていない。
12名が本質的に持ち、萌芽的に現れていた自主思想と超暴力としての非暴力の思想は、5人の指導部派兵士の自己批判としての浅間山荘銃撃戦の中にも現れ、他の連合赤軍の人々の中にも現れ、指導部森、永田さんの自己批判の中にも現れていた、とも言える。
我々はこの思想を、その反面教師の個人主義、個人利己主義、実存主義を批判し、現在に回路付け、意識的に対象化し、継承、定着化しなければならないのである。
この思想的営為の中で、武装闘争と大衆的政治闘争、労働運動、その他の人民運動との結合が目指されるべきであった。
またこの歴史的必然性は客観条件と主体的条件が綜合されて判断されるモノであるから、どんなに長く見ても75年のアメリカのベトナム侵略終結までであり、それ以降は平和的闘争に路線転換されるべきであることも前提にしてのことである。
4節 植垣の「殺すつもりはなかった」「思想的援助をしようとした」の「同志殺し」の居直りは許されない。
「同志殺し」を「粛清」と居直り、何か大義のために無私で「献身」したかの如く振る舞う見解、曰く「自分は殺すつもりはなかった」「上から言われ思想的援助をしようとした」として、森・永田の自己保身、延命のための反動的思想運動に荷担して、自らも保身と延命のために「同志殺し」を推進したことを隠蔽せんとする見解、或いは、この「粛清」があったが故に「銃撃戦が貫徹された」とする見解、総じて最近テレビなどで華々しく流布されている植垣の見解である。
この植垣の見解に同調する、ほんのごく少数の見解は、前述の武装闘争の歴史的必然性を否定する清算主義の見解が権力の反動攻勢と絡みつつ跋扈し、正しい総括がなされ切れていない裏鏡的所産と言える。
「"共産主義化"の中で身を削り、人柱になっても闘わんとした」亡くなった12名の行為を始めとして、副次的にだが「連合赤軍の中にこのような側面があった」ことを抹殺する風潮に反発せんとする「敢えて極論」の類、と言った方が、このような見解の存在意義を言い当てている見解ととらえるべきである。
とは言え、30年たって正面からこのような問題提起がなされるとすれば、それは全く愚かであり、一体この人たちは何を学び、何を総括してきたかと問いたいし、僕は上記のことを踏まえつつも、物事の正邪、理非曲直を違え、殺された12名を再度傷つけ、殺すようなこのような見解とは断固闘うモノである。
「共産主義化」の反動的思想運動の中にこのような側面が含まれていたことは事実である、或いは指導部に付き従って行かざるを得なかった下部「党」員の弁明の気持ちは理解できるが、それはあくまで副次的な側面であり、主要な側面ではない。
植垣はこのことをすり替え、自己弁護の正当化をやっているのである。
吉野が真摯な反省をやり、金子さんを擁護・防衛できなかったことを金子さんのご両親に、それが「自分の中にあった保身、利己心」によることを認めてゆく態度をとっているのとあまりに懸隔があり過ぎるではないか。
植垣は大槻さんの家族のところに詫びに行っているのであろうか。
植垣の言いぐさ、態度は30年経ったとしても倫理的に見過ごされてはならないのである。
植垣はこのような言いぐさ、態度を改めるべきである。
「同志殺し」を「粛清」として肯定したり「共産主義化」を「殺す気のなかった援助」などと自己弁護の詭弁を言うなら、別に総括運動などやる必要がないのである。
問題の設定は以上を概括すれば、武装闘争の歴史的必然性を否定したりすることで、或いは「粛清」を居直って肯定したりすることで、事件の根底にあった個人主義、個人利己主義、実存主義、それを克服する、あるべき武装闘争の課題や、そのことの根底に据えられるべき思想、人間論としての自主思想や超暴力としての非暴力思想の思想に到るような思想的努力を回避したり、放棄したりする志向と闘うことである。
 第2章へ行く
第2章へ行く
 目次へ戻る
目次へ戻る