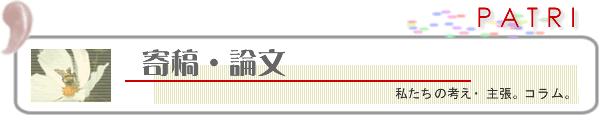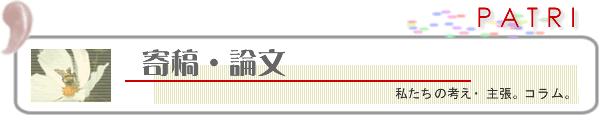30年目の我が「連合赤軍問題」総括
2章 連合赤軍問題形成のプロセスとその節目、節目の問題
1節 塩見の責任性について
僕は連合赤軍問題が露呈した直後の1973年3月か4月、この問題の総括論争が沸騰していた時「百花斉放、百歌争鳴」を宣言し、赤軍派解体、赤軍派議長辞任を声明するまで赤軍派議長であった。
そしてこの問題に主体的に迫り、その責任を議長として引き受ける意味で「元赤軍派議長」と言う看板を敢えて掲げてきた。
「任務は情勢に帰し、総括は主体に帰せ」と言う態度である。
僕の責任問題での態度の基本はこのような態度である。
僕が自己批判しなければならないと思っていることは山ほど、細かいことを含めれば、ある。
その中でもここでは今から見て、最重要なことを二つほど挙げておく。
1.1つは思想上、理論上のことで、連合赤軍問題を発生させて思想的欠陥を防止出来なかった限界についてである。
もう既に述べたが、人間観に於ける個人主義、実存主義的傾向を残していたことである。
もとより、この実存主義はサルトルのようヒューマニズムやマルクス主義に連関していたものであるが人間自主主義的なモノでなかった。
つまり、人間自主主義、プロレタリア主義、愛郷主義を土台とする民族主義を融合したモノに高めきれていない問題、正しい「覚悟」の観点、同志愛の観点で、脆弱なところがあった。
これと関連して超暴力としての非暴力の思想的、政治的、軍事的観点、思想が弱く、また武装闘争の歴史的必然性を確認するもが故に、より思想的、政治的に慎重であるべきなのに、安易に「革命的な人民暴力」を賛美、ロマン化するようなところがあった。
2.2つは赤軍派は現代先進資本主義国に於ける現代革命を、ブントを継承し、ドイツ革命の総括など追求し、あくまでも「全人民的政治闘争に於ける中央権力闘争、地域に於けるマッセンストライキ」を原型イメージにこの政治を実現する要素として、軍事を設定していく軍事思想をもっていた。
この展開として「前段階蜂起」やその国際的条件、布陣として「国際根拠地」路線が定められていたのに、毛沢東思想・中国革命型の軍事にひきずられてゆくような弱さをもっていた。
勿論、それでも「社会主義の労働者人民大衆を依拠階級とした都市ゲリラ戦」を追求していたが、この現代革命の基本陣形を忘れかかっていたが故にこの「都市ゲリラ戦」は唯軍事主義的なものを含み、観念的な超唯軍事主義の革命左派に引きずられたのであった。
それは、外の現場にいた森達の困難さを思いやりきれず、彼等を「左」に追いやって行くような無責任さを伴っていた。
この基本態度を踏まえることは、70年安保武装闘争での赤軍派、ブントとしての提起者、総設計者、総プロデューサー、総監督として責任を取り続けると言うことである。
そのことは、殺された12名を復権し、二度と同志殺しの過ちが繰り返されないよう身を正しつつ、事件の総括を続けること、そしてそのことに於いて事件の理非曲直、正邪について明らかにすべく闘い続けることを表明し続けることを意味する。
但し誤解無きように言っておくことは上記「総」の付く性質に於いてであり、現場監督、現場設計者の個別な特殊な独立的責任を負う者ではないこと、個別責任は個別責任であり、それまでを総監督が負うのは逆に物事の理非をねじ曲げることとなること、赤軍派やブントの歴史的意義を歪曲したり、抹殺したりすることになりかねないからである。
赤軍派はブントから生まれ、そこから大菩薩軍事訓練、首相官邸武装占拠を企図した戦士達が生まれ、「よど号」戦士達が生まれ、日本赤軍が誕生したのであり、連合赤軍を構成した森派はこのような赤軍派の一部が赤軍派全体の合意を得ることなく、非公然、私的に分派したグループと言える。
その森派と永田を指導者とする革命左派(日本共産党左派神奈川県委員会、議長川島豪)から、これまた非公然に分派した永田派が分派し野合したのが「連合赤軍」という「新党」である。
ある意味「現場監督」であった田宮や重信さんは独立し、自主的な赤軍派を乗り越えるような活動をしてきた、と言える。
しかもこの人々は赤軍派のコンセンサスをえて、公然と独立していった。
しかし森派はそうではなく、秘密に赤軍派全体の承認無く、勝手に分派したのである。
そして悲惨な過ちを犯したのである。
第一次赤軍派、大菩薩グループ、第二次赤軍派、よど号グループ、日本赤軍もまた、赤軍派指導部、塩見の思想、理論、行動の意義と限界を多分に受けており、その意義を継承したり、これを乗り越えた面も持てば、その限界を引きずっている面もある。
そしてそれは、現場監督の善し悪しによってその活動の成果が決まって行く側面が強いのであり、そこでの総監督の現場監督の起こした問題の責任は、双方の責任の区別と連関をしっかり現実に即して分析されて認識されるべきである。
森派は、言いにくいことだが、田宮や重信さんとは違って「赤軍派の鬼っ子」の面が強いのである。
永田や植垣は勝手に分派しておきながら、裁判の過程で「同志殺し」の責任を否定すべく、それまで塩見と交わした「12名の立場に立って総括する」と言う盟約を投げ捨て、「同志殺し」を一方では正当化し、他方では「森さんの指示に従った」「森さんは塩見さんの指示に従った」といった論理で塩見に責任転嫁しようとしたが、このような責任の有り様設定は見え透いたペテンであり、醜い逃げ口上と言える。
ここでの塩見の責任は政治上や組織上のことでなく、思想上、理論上の分野に於いて何故森派を産み出すことを防止し得なかったか、と言うことである。
この点、かなり「幸福論」で総仕上げ的に解明してきたつもりであるが、ここではこの分野での責任の区別と連関を明確にすることを念頭に於いて、「連合赤軍問題の発生のプロセスとその節目、節目の問題点」を追跡する中で、責任関係を明らかにして行きたい。
2節 7・6事件を赤軍派はどう総括したか。
第二次ブント総括は別の次元で必ずやらなければならない僕の仕事なのですが、今回は「連合赤軍問題」・赤軍派との関連することで、それも最小限に絞って語ることにします。
なお、ブント総括については、ブント戦旗派(日向)の「理論戦線」にある程度の輪郭を語っておきましたので、それをさし当たって参考にして下さい。
赤軍派は第7回大会の主流派を形成していた部分がコアになっている。
その時の路線は塩見が中心となって当時の諸意見を纏めた「過渡期世界論ー世界同時革命論」であった。
またその時上京した佐野茂樹(7回大会議長)、旭凡太郎(政治局員)、高原浩之(学対部長)、田宮高麿(共産主義青年同盟書記長)、上野勝輝、竹内陽一、上田さん、森恒夫、久保田その他多数のメンバーは6回大会政治局員で学対部長あり、7回大会で政治局員であった塩見が上京を要請したメンバーであった。
このメンバーと在京の早稲田支部の村田、菅野、荒、花園、大下、本多、松平等や医科歯科大岡野、山下、中大、東大支部等のメンバーや塩見の盟友で当時関西地方委員会議長であった八木健彦や関西学対部長であった望月上史等の関西学生部分が中核となって主流派が形成されていた。
ブントは当時8個師団と言われたようにある種の連合組織であり、このような主流派以外に幾つもの政治グループがあった。
8回大会では仏徳二が議長となり、佐野・塩見達主流派を「労働者の組織強化と組織の建設の独自的強化」を主張し、批判した。
この段階で塩見、佐野、旭等は政治局員に残留するも、主流派からブント左派に退くこととなる。
仏氏の主張は一定の意義を持つが、実際の指導力としては無きに等しく、迫りくる69年の安保決戦に何の方針も持たず、闘いは依然として7回大会派が担い、仏氏の労働運動サークル主義の弱点が露呈した。
この労働者主義は10・21防衛庁闘争の総括として確認された「中央権力闘争とマッセンストライキ」の路線とも違っていた。
10・21闘争の総括論争の継続に加え、69年4・28闘争の総括論争がそれに加わり、他方での破防法弾圧が加わり、ブントはガタガタになった。
この状況に7回大会派は危機感を感じ「前段階決戦を前段階蜂起・世界革命へ」「党の革命、共産主義と軍事を組織する党への改造」の旗印を掲げ、第7回大会路線を忠実に実行しようとした。
そのフラクションを他のブント連合諸派は「赤軍派」と呼び、7回大会派は自らを「赤軍派フラクション」と自称するようになった。
このようなブント内の路線闘争と小競り合いを調整するものとして7・6中央委員会が開催されることとなった。
かかる事態の中で、中央委員会開催の場、明治大学和泉校舎は赤軍派と「連合」ブントの路線を巡る激突の場となっていった。
どのグループも前の晩から泊まり込んだし、ゲバ棒で武装する始末となった。
赤軍派は指導力をなくした「中央」に代わって「中央を担う用意がある」ことを宣言し、これに備えた。
和泉校舎で仏氏を捕まえ、相まみえ論争し、自己批判を要求する過程で塩見は感情的になり、激し衝動的に氏にリンチを加える過ちを犯した。
他のグループにもそのような過ちを犯した。
それまで森君等「赤軍派フラック」に加えられたリンチや仏氏の路線や方針抜きの権謀と術策の「宮廷政治」の仕方への不満が爆発してのことである。
塩見はその直後、自己の過ちに気づき個人として、他の同志と共に赤軍派フラックとして二重に自己批判し声明を出した。
現在、改めて「この過ちをブント同志達に自己批判します」、また「赤軍派同志達にも自己批判します」。
このことで、塩見等赤軍派フラックがブント主流派への返り咲きのチャンスを失ったのは、返す返す残念なことである。
その後、機動隊が包囲し始め、撤退が全体的になされ始めた段階で赤軍派も仏氏を擁護して撤退していく訳だが、そして氏を仏グループに任せる過程で、機動隊が乱入し、赤軍派も仏派も仏氏を守りきれず、権力に逮捕させてしまうこととなった。
この点についても、仏派にも落ち度があったが、基本的には塩見と赤軍派に責任があり、真摯に当時自己批判したが、今も自己批判する。
その後、塩見と田宮はホームグランドの医科歯科大に引き上げるが、軍本体と離れていた。
そこへ叛旗派系中大全共闘が襲撃をかけてき、激闘の後、塩見、田宮、望月、物江等は捕捉されてしまう。
中大に連れ込まれ、度重なるリンチを受け、2週間後の脱出過程で望月が転落死する。
度重なるリンチで腕の力が弱まっていたことに起因する。
この点については、味岡君や連合派の謝罪、自己批判を僕は聞いたり、見たりしていない。
重要なことは、中大監禁、リンチの過程でも、その後も赤軍派は声明を出し、「前段階蜂起路線」を堅持しつつも、仏氏リンチと氏を逮捕に追いやったことについて厳正に自己批判し、ブントに処分を仰ぐ旨、対応したことである。
分派,別党でなく、ブント復帰は赤軍派の基本方向であった。
このような立場で、7・6事件に関係のない山田が「赤軍派フラック」の自己批判書をもってブント中央委員会に参加しようと会場に行ったが、連合派は入れようとしなかった。
これは連合派の狭量と自信のなさを示すものであった。
明大闘争の時の斉藤・大内の処分の仕方、7回大会時のマル戦派への対応の拙さに共通するブントの組織建設上の問題点の露呈である。
この辺はブント総括の問題であり、ここでは省くとして、我々赤軍派フラックは真摯に自己批判したにもかかわらず、連合派が拒絶したので、やむなく分派せざるを得なかった。
しかしいつの日にかのブント復帰を留保し、別党、新党路線は取らなかった。
ブントの分派と自己規定し、「ブント(赤軍派)」と名乗ったのである。
森は野合「新党」結成の過程で、この対応が不徹底であったと批判し、「新党」を名乗り、塩見達をさらに批判したのだが、このような対応は、極めて重大な過ちと言える。
第一次赤軍派では厳格であったブント組織原則は第二次赤軍派、森指導部派や分派「新党」を肯定した部分では、単なる徒党集団の離合集散にまで矮小化され、スリ返られていってしまったのである。
また路線闘争に伴う暴力の行使の問題は、それ以上深められなかったが、これは原則的に否定されており、「赤軍派がこれを居直ってきた」とするのは、全くの歴史の偽造と言わなければならない。
森はその時(7・6)トンコしていたが故に、この自己批判の深刻さを知らず、手前勝手な解釈を施し、私党「新党」を居直っているのである。
また彼は永田のスターリン主義的な「一枚岩の個人崇拝」の党建設観を許容し、「革共同的党至上主義」に乗り移っていったことも留意しておくべきである。
いずれにしても7・6の過ちの延長線上に「新党」リンチがあったとするのは、こじつけと言わなければならない。
11月5日から7日までの首相官邸武装占拠闘争(*注 69年、大菩薩峠での53名逮捕)の敗北の総括として、赤軍派は武装闘争の永続性の条件を国際性に求め、「国際建設路線」を設定する。
この路線は「主体建設をあくまで日本とプロレタリア等人民大衆に求める基本原則」から、かなり逸れる点をしっかり押さえ切れてないことが問題であったが「過渡期世界論」の路線に従ったもので、また彼我の攻防関係の現実に照らせば、迂回作戦であることを意識的に含んだ、極めて妥当な路線と考える。
ともあれ、赤軍派はこの路線で「よど号」闘争を貫徹し、武装闘争の現実性を示した。
しかし権力の報復弾圧の凄さを計算に入れず猛弾圧を受け、大菩薩の打撃と合わさり、第一次赤軍派は壊滅的打撃を受け、獄と国外に分散されてしまう。
3節 革命左派「遊撃戦争路線」の登場と「2名処刑」に見られるその功罪、「スターリン主義」の現実は何であったか
① 革命左派とは
日本共産党(左派)は、日共(宮本派)が中国共産党とプロレタリア文化大革命の評価を巡って対立、絶縁状態になる中で、日共から脱党したり、除名されたりした毛沢東思想派(通称中国派)のことである。
この部分は「毛沢東思想は当代最高峰の革命思想である」「毛沢東思想は精神的原爆である」とか言い、毛沢東思想を高く評価し、それを日本革命の指導思想とする部分である。
東京、大阪、名古屋、山口、佐賀等全国に存在した。
神奈川県にも存在した。
毛沢東・中国共産党の影響力は当時、日本人民大衆に甚大な影響力を持ち、新左翼にも毛沢東思想を評価する部分が輩出した。
ブントやブントML派である。
ちなみに第二次ブント系でも、ブント主義を前提にしてだが、毛沢東思想を評価する部分が現れた。
関西では上野や塩見であったし、東京ではマル戦派であった。
もっとも塩見達は毛沢東以上にゲバラ・カストロに親近感を持ち、支持していたが。
この日共(左派)の神奈川の部分から「警鐘派」が生まれ、さらに日共から脱党した部分が合流し、「日共(革命左派)神奈川県委員会」が生まれ、武装闘争派の川島豪と従来の「新聞発刊」を組織建設の要とする木下(川北)派に分裂する。
永田はML派系で最初木下に私淑し、川島や川北はマル戦派から流れてきたと聞いている。
日共(革命左派)の下に京浜安保共闘や「反戦婦人の会」が作られ、学生運動の拠点としては横国大や水産大があった。
木下は「連合赤軍問題」露呈以降、「黎明」を発行し、後に大隈鉄二等と「労働党」を作り、亡くなる。
川島はML派との党派闘争以降人民軍創建を提唱し、米ソ大使館火炎瓶闘争や愛知外相訪米・訪ソ闘争を提唱したりする。
以降、革命左派は一路左傾し、12・18上赤塚署襲撃・銃奪取闘争、2・17真岡銃砲店襲撃を行い、武装闘争派を牽引し、全体の運動の焦点となるが、これは川島豪の「遊撃戦争路線」に立脚してのことである。
12・18の闘いと柴野晴彦の戦死、渡辺正則の負傷は日本人民に感銘を与え、柴野の国民葬が文化人達によって挙行されたりもした。
しかし、2・17以降の弾圧によって、孤立し、いき詰まり、一時中国への退却論争を経て、山岳小袖のアジトをベースにするようになり、ここから脱出した向山・早岐を「スパイ認定」し、「処刑」する。
これは明らかに山岳ベースを権力に知られたくないところから起こった事件で、一時逃避、武闘訓練の場を根拠地と倒錯していく認識との関連で起こった事件である。
柴野晴彦は赤軍派に「連続蜂起・国際根拠地路線」を「待機主義」と批判し、「遊撃戦争路線」の採用を訴える。
これに赤軍派内部から呼応したのが花園・松平であり、花園は12・18闘争を高く評価し、同時に思想、政治路線でも毛沢東思想、反米愛国路線を支持し、川島と同志的連帯を表明する。
塩見が接見禁止を受けている間に二つの路線闘争が起こる。
イ、国際根拠地路線をどう見るか。
肯定か否定か
ロ、「中央権力闘争ーマッセンストライキ」路線から発展していった「前段階蜂起路線を否定するか、肯定するか」の論争である。
この論争は明らかに革命左派の影響であり、花園はその代弁的推進者であった。
この主張は塩見の接見禁止が解ける1971年7月頃まで跋扈し、塩見がそれを批判するまで続く。
その後も花園はこの路線に固執し「自由への道」を著し、「レジス・ドブレ」の「革命の中の革命」に依拠しつつ「合流、野合の路線」に固執していく。
獄中の川島花園路線を受けて、永田は「遊撃戦争路線」を様々な不満を持ちつつも推進して行く。
②川島「遊撃戦争」路線、「銃を軸とする殲滅戦路線」を支える政治路線とは?
川島はこの遊撃戦争路線を更に「発展」させ「銃を軸とする殲滅戦」路線を主張していく。
しかし、この川島路線は様々な点で毛沢東教条主義とも言える本質的欠陥、限界を持つもので、この軍事路線が「連合赤軍問題」を爆発させた、と言っても過言ではないことを、今こそ言わなければならない。
まず政治路線である。
日本社会は対米従属ながら高度に発達した資本主義国である。
70年当時もそうであったが、あれから30年経った現在このことは動かしがたい事実であり、ここから引き出される支持路線はマルクス主義風に言えば 「反米帝国主義、反日本独占資本主義の、国と民族の自主を目指す社会主義革命」の路線と言える。
「反米、反従属独占の民族・民主の変革から社会主義の連続革命」の路線と言える。
対米従属を当時の新左翼系は「日帝自立論」の認識で認めなかったが、「いずれ日本はアメリカから自立し、対立するようになる」の認識は間違っていたことが、現実で証明された。
新左翼系は、対米従属から、資本主義でありながら日米関係に於いて民族的課題があることを確認していくべきである。
日共は「従属しているから、日本は帝国主義にならない」と言っていたが、今はその従属下でそれを利用しつつ、帝国主義的膨張を強めており、自衛隊は海外派兵をやり、侵略軍隊の性格を帯びつつある。
但しアメリカ軍の従属軍隊としてだが。
この見地から、日共は「民族民主主義革命から社会主義革命へ」の伝統的な二段階戦略をとり続け、社会主義革命の性格を無視し革命の課題を「近代国民国家、近代民主主義国家」に低め、切り縮める改良主義の党に脱してしまっている。
革命左派、川島豪の路線はこの路線に近く、毛沢東教条主義故に51年の日共綱領に近く、反米愛国路線もまた中国直輸入で日本の現実に適した物ではなかった。
丁度田宮や小西が朝鮮革命の「反米愛国」を機械的に日本の現実に適用したような過ちがあった。
塩見には、この空回り、反発を日本の現実にあわせるべく、対米従属下のグローバリズム高度資本主義国の民族問題、パトリオティズム(愛郷、愛族、愛国)に読替えて展開するような内容は、見受けられなかった。
塩見は当時獄中で「合流の可能性」を探り、対米民族問題ではかなり近い認識を確認したが、スターリニズムの「プロレタリア独裁下での粛清」についてはどうしても受け入れることが出来ず、その結果「合流をさし当たって見合わせる」判断をせざるを得なかった。
この中国革命教条主義とスターリン主義が「山岳根拠地路線」や2人の処刑、中世的「唯軍事主義的軍事路線」を導き、連合赤軍を凄絶な破産に帰結していくのである。
③川島軍事路線の教条性と花園軍事思想との共通性、赤軍派軍事思想とは?
川島路線は、毛沢東の軍事路線をそのまま日本へ適用しており、51年綱領の山村工作隊の路線より、さらに旧式でかつ極左主観主義なのである。
毛沢東の軍事路線は中国社会が「軍閥が割拠し、陣取り合戦の軍事が前面に出る半封建国、半植民地国の未だ市民社会が成立していない、社会と国家がゼラチン状(アントニオ・グラムシ)の社会」に適合する軍事路線であり、このような中国社会では「反植民地主義の愛国心と反封建の民主主義闘争を、農民に依拠し、農村から都市へ」の路線が導かれる。
毛沢東はその路線を発見し、創造していった。
しかし、日本社会は明治以降の戦前でも曲がりなりにも市民社会は成立し、戦後60年代以降は国家独占資本主義社会で市民社会は成熟して行き、「社会やその国家の結びつきはゼラチン状(上記グラムシ)」となり、変革は「都市の労働者と社会旧階級に依拠した、中央の権力を巡る全人民的な政治闘争と市民社会の底部の生産関係と再生産関係でのマッセンストライキやゼネスト」の変革陣形となり、この政治、思想路線を阻む人民大衆が主人公となった政治的闘いとなり、闘いは「政治、思想第一」の争い、とりわけ知的、道徳的な要素が決定性を持つようになる。
このような人民の側の闘いを阻む体制側の暴力に対して、あるいは民間の反動勢力に対して、その圧力から自衛し、それを跳ね返す人民勢力の側の実力暴力「レッド・ゲヴァルト」「エル・ゲー(赤衛軍)」となる。
赤軍派はこれらのことをドイツ革命の総括から学び、当初それを「共産主義突撃隊」と名付けた。
このような点で赤軍派と革命左派では根本的とも言える軍事思想の違いがあった。
花園は本来政治軽視で、鹿児島出身故か戦国大名や薩摩や西郷の軍事が下敷きにあり、この点で川島と一致し、その「水滸伝」「三国志」的剛勇で尊敬もされれば、政治局で孤立もしたのでもある。
それが塩見の接見禁止中に頭をもたげたのである。
④スターリン主義の粛清思想に、無批判な体質
毛沢東思想にはスターリン主義を許容する内容がある。
毛沢東は本来、スターリンの「個人崇拝ー人民裁判ー粛清」と言った強権的、行政主義的政治を否定する、または悪風の思想的根元を抉り、その思想を批判し、大衆的思想運動で人民の隊伍を整える「整風運動」といった良き作風があったが、川島の作風はそれと反対のスターリン主義を感じさせるところがあった。
それは、僕との文通の過程で使われた「整風」の意味合いが「粛清」意味合いを有していたことや連合赤軍問題露呈後の革命左派同盟員である雪野が、永田の「粛清」への意見を聴いた時の「(同志殺しは)ゲリラの鉄則を守ったのでは」との言質にも窺れた。
推論ではあるが、僕は「この考えを2名処刑に忠実に適用したのでは?」と思えてしかたがない。
この粛清思想が、まだ永田と川島が訣別していない関係下で永田を通じて、2名「処刑」に発動されたと思われてしかたがないのである。
またこの粛清思想が野合の過程で森の反動的シゴキ修養論に乗り移り、合体し全面開花したわけである。
永田は例によって、「死人にくちなし」で森に責任転嫁しているが、これは永田の自己防衛の常套手段であり、実際は川島との相談で出てきた判断を打診したのではないか。
⑤赤軍派の「都市ゲリラ路線」への徐序の転換
森赤軍派は獄中の花園等の要求に応じず、「よど号」闘争の大弾圧をナントか乗り切り、森体制を確立してゆく。
これは71年前半の「連続蜂起-国際根拠地建設路線」を堅持している「赤軍」第7号機関誌に明らかである。
この路線でM作戦や6・17闘争を闘い、板東隊は山谷等寄せ場を拠点に「都市ゲリラ」として行動している。
徐々に革命左派「遊撃戦争路線」に影響されつつも「連続蜂起路線」を修正して言っている。
このころ赤軍派はスパイ処刑の誘惑にも勝ち、軍事作戦としては欠陥だらけながら大きな決定的過ちを犯さずにいる。
森体制の安定期であり、このころの彼等の頑張りは評価されるべきである。
しかし、森はこの路線をしっかり固め、より大衆化し、同志達の自主的行動を伸ばし、依拠基盤を徹底的に労働者大衆に移してゆくことなく、徐々に拠点からの召還、集中主義で永田の「山岳根拠地路線」に引き寄せられていく。
塩見は71年7・15裁判開始後、接見禁止が解かれる中で川島、花園の「毛沢東教条、合流」の路線を批判し、「統一赤軍」を「連合赤軍」路線、共闘路線に改めさせる。
同時に「前衛の軍人化(機関誌も発刊するが)」「社会主義都市ゲリラ路線」を」主張し、他方で毛沢東教条主義の「反米愛国路線」を「民族解放・社会主義革命」の路線を対置し批判していく。
森はこの「民族解放・社会主義革命」の路線を革命左派や永田を批判したようであるが、植垣・永田はここで一言使われていた「共産主義化」という、獄中で「自主平等で助けあって、自己点検して行く」意味合いで大衆化されていた用語を、森流にシゴキ修養論に解釈し、指導者が軍事の先頭に立てるほどに軍事に習熟することは「党至上主義」でやらず、勝手に使っていったようである。
この「党至上主義」が後に永田のスターリン主義の党組織論と合体して行き、指導者を絶対化して行く。
いずれにしても、よど号以降の70年末から71年にかけて「川島遊撃戦争路線・銃を軸とする殲滅戦路線」といったブントや赤軍派には言語的に違和感を巻き起こす路線が全局を先導し、赤軍派や森は引きずられていっているのである。
この路線が都市の人民大衆からの遊離を極端に進行させ、山岳を根拠地と見立て、スターリン主義的妄動の2名「処刑」に結末し、更には致命的、決定的な「野合新党」、12名「粛清」の大破綻に爆発して行くのである。
この文脈はしっかり押さえられておくべきである。
川島路線は70年「よど号闘争」以降の停滞を打破し、70年以降の武装闘争の激発、71年の大衆闘争の高揚を導き、最初革命的な生鮮さを与えたが、それは日本の現実から遊離しているために後が続かず、はやばやと行き詰まってしまい、致命的破綻を招来させることになる。
塩見達、獄中者は「連合赤軍」主力が山岳に隠れ棲んでいるなど夢にも知らないことであった。
⑥二人処刑をどう捉えるか
向山、早岐さんの「処刑」を受け入れるか、それを拒否し、批判するかは根本的な価値観、革命の価値観の問題である。
人間解放をどう捉えるか、の革命家それぞれの人間観の問題となる。
それはどの様な政治路線、変革陣形を敷くかを遙かに越えた、普遍的な価値観の問題である。
もっと広く言えば、その社会がブルジョア社会か、否か、社会主義社会か、否かの如何に依らない、人民大衆が住んでいる社会がどの様な人間観、社会観を持つべきか、ヒュ-マニズムをどう捉えるか、と言う宗教観をも貫徹する社会生活の根本的規範、倫理を何処に求めるかの根本問題である。
そして、それはスターリン主義と粛清をどう見るのかに直結する問題である。
我々ブント・新左翼がスターリン主義やスターリン主義日共と訣別したのは、この粛清を拒否するところから出発したのである。
粛清を肯定する人間観を拒否し、新しい人間観、社会観をを確立すべく誕生したのである。
赤軍派もこの思想的流れを継承、発展して行くべく誕生したのである。
だからこそ、7・6事件での自己の自然発生的な感情に流されたリンチを厳しく反省したのである。
森もまた最初「処刑」を批判し、「永田達はもう革命家でなくなっている」と非難したのである。
或いは板東、植垣は一時森の「処刑指令」を無視したのである。
人民大衆は殺さない。
分けても同志は殺さない。
敵に対しても戦闘以外やたらと殺さない。
非戦闘員は殺さず人道的対応をする。
人間愛、非暴力を根底において、戦争原則「敵を消滅させ、味方を保存する」を考えるのである。
「軍事の自然発生性に帰しない」は7・6事件以来の戒律であった。
スターリン主義はこの人間愛、同志愛を軽視し「プロレタリア独裁下での敵と味方の境界線」を恣意的に操り、利己主義、自己保身の為に人民権力を個人独裁権力に置き換えるべく、「個人独裁→人民裁判→粛清」の反人間主義的恐怖政治を実行した。
その政治は、一時期ソビエト権力を延命させたが、最終的にはその社会を崩壊させていった。
カストロ、ゲバラにせよ、毛沢東にせよ、味方のどうしても許し難い決定的裏切りには断固たる処置を採ったが、日和見主義や捕虜などには寛大に望み、食料を与え、退散させるような処置すら採り、極力殺さないようにしている。
本来、暴力革命や人民戦争はこのような在りようが模範であり、道徳的高さが追求されるのである。
自主意識の高くなっている、先進資本主義ではブルジョアジーすら死刑を抑え、まして人民大衆の側は判然としない「スパイ容疑」などで人民を殺すなど絶対に許されないのである。
永田は「中国亡命路線」を批判され、政治・軍事路線を行き詰まされ、「大衆に依拠する」など思いもよらず、切羽詰まり、自己保身から、小袖の山岳ベースを一時の逃避場所、軍事訓練の場所から「根拠地」路線に位置づけなおし、その根拠地の権力を守るべく、前沢等の反対を押し切り、二名を「スパイ認定」し、「処刑」を行った。
二名の「スパイ認定」の科学的根拠の追求などには、全然慎重でなかった。
そもそも「何故山に来させたか?」の反省が真剣になされたとは言えない。
ここに於いて永田はスターリニズムを受け入れ、逆にそれを党派性にして専制化を強め、それを森に迫ったのである。
赤軍派や新左翼を「軟弱」派と断じたのである。
永田は「渡ってはならない河を渡ってしまう」のである。
ここにおいて、スターリン主義は復活するのである。
この行為は川島との相談の上、なされた可能性があるが、また彼女が不運な巡りあわせで、指導部を引き受けざるを得なかったこと、貧困労働者家庭出身で女性差別を経験し、脳腫瘍の病気を抱えていた等考慮すべき要素が多分にあるが、逆にその怨念をスターリニズムの「弁証法的唯物論」の「タダモノ主義的人間観」、「粛清論」と彼女の割り切りスタイル、チャッカリズムを融合させ、権力獲得志向で晴らすとすればそれはトンでもない間違いとなる。
「罪を憎んで人を憎まず」の格言があるが、永田さんの罪はスターリン主義として批判するが永田個人の人格を憎まない。
4節 山岳「同志殺し」の「共産主義化」の発生とその軌跡、構造----野合「新党」権力確立の為の「粛清劇」
①野合「新党」結成という組織問題を介在させるとより「共産主義化」の本質が解る。
―――「共産主義化」は思想運動という衣をかぶせた同志殺しの「粛清」である。
「共産主義化」の本質をどのように捉えるか、そのことによってその原因も違ってくる。
従って「連合赤軍問題」の原因も諸説紛々となる。
この分野では、政治路線、軍事路線の面での革命左派の中国式「反米愛国路線」、毛沢東遊撃戦争路線の観念的適用、「山岳根拠地路線」と「銃を軸とする殲滅戦路線」、山岳根拠地防衛のための「脱走者の処刑」、これらの根源は指導者に取り憑いた日和見主義、利己主義の保身を源とする自己絶対化、スターリン主義の許容等であることを既に指摘した。
「連合赤軍問題」はこの延長であり、その質的飛躍としての、その全面開花と言い得る。
しかしこの認識は政治、思想、軍事上のことで組織上の問題、つまり野合「新党」でっち上げという組織問題を媒介させると、永田・森の利己主義、自己防衛の権力強化に基づく「粛清」であったことがよりはっきり見えてくる。
政治は常に集団の利益、要求を実現すべく指導部、指導体制を要求する。
指導者がその集団の利益、要求を守る際、指導者個人の保身が常につきまとうのは必然である。
当然にも指導者が公として指導権を発揮することと、その指導者の保安は一体であり、そのことを否定する人はおよそ政治が分からない人である。
しかし、その保安とその指導者の利己主義とは全く別のことで、そのことに隠れて利己主義を実行すればそれは糾弾されるし、その人はもはや指導者ではない。
軍事、戦争の場合、集団的行動が日常を越えて格段に要求される条件では、指導者の統率力が最高度に問われ、下からの要求、民主主義が制限される。
このような場合、一時期、指導者の指導権と利己主義が渾然一体となり、公に隠れて利己主義が見えにくくされる場合がある。
政治の要求と指導者の保安が、利己主義に傾く紙一重の状況さえ生まれかねないと思う。
さて以上を踏まえて、「共産主義化」の本質をどのように捉えるか、そのことによってその原因も違ってくる。
従って「連合赤軍問題」の原因も諸説紛々となる。
「山からの脱走者を防ごうとした」これは原因の重要な的の1つを衝いたものだが、極めて現象的な指摘である。
2名「処刑」の場合、山岳根拠地防衛の為に最大、最重要な原因である。
しかし「新党」の場合はこの要因に加え、さらに野合の要因が加わりもっと複雑になる。
「何が何でも銃撃戦をやろうとして、“日和見主義部分”を“粛清”した。
」「思想的に“弱い”部分を教練、援助しようとして、結果として殺した。
一種の思想運動だ。
だから思想運動に暴力を持ち込んだのが問題である」(植垣)。
これは、森や永田の自己弁護の見解と同じである。
これだと殺した側の森、永田は強く、完全無欠で、殺された側は弱く、欠陥多い人物となる。
そして強く、完全無欠なものが、思想的に弱く、欠陥多い人たちを教え、援助したことになり、この思想運動で強く、完全無欠な連中は、「暴力を導入する」ことで方法、手段を誤った、ということになってしまう。
なぜ、完全無欠な人間が「暴力を導入したのか」の思想的原因を追求されると窮してしまい、この論理は破綻してしまう。
そもそも、植垣が、森が、永田がどうして完全無欠であると言えるのか。
殺された12名がどうして弱く、欠陥多いと認定できるのか。
そもそも、認定するのは誰なのか。
そして、その資格が何処にあるのか。
とんでもないことである。
指導部派、とりわけ森、永田が勝手に自己の日和見主義、保身から恣意的、政治的に勝手に決めただけではないか?
「共産主義化」と題する、人騙しの、鵺のベールを剥ぎとればこんなことは一目瞭善となる。
それでは、「銃を軸とする殲滅戦は何処に行ったのか」「森、永田は心底から銃を軸とする殲滅戦を望んでいたのではないか」否、断じて否である。
二人はそれを望んでいなかった!それは彼等が保身のための権力を維持する名文に過ぎなかったのだ!
二人は「銃を軸とする殲滅戦」を声高に言うことで、逆にこれをしようとせず、自己の延命、保身、延命の個人独裁権力を固めようとしたのである。
そして、真に闘おうとした、それ故に二人を批判しようとした人々を何が何でも抹殺しようとしたのである。
一体何処に「銃を軸とする殲滅戦の展望、計画、戦略ー戦術が検討され、その為の体制強化、それぞれの任務、配置、これとの関係での主体強化が追求された」痕跡が在るか!
山本が免許証を落とし、それが猟師に拾われ、官憲に強襲されるのに如何に備えるかが下部から提起されたのに、森は言下にその準備を拒否し、アジトの移転を考えているではないか!
森は、具体的な「殲滅戦」の計画と切り離して、観念的、精神主義的に「決意固め」を語り、同志を殺していって居るに過ぎない。
正に「左」の格好をした、日和見主義ではないか。
「日和見主義、個人主義故に“銃による殲滅戦”を掲げて、それをやらないために、“共産主義化”と言う無基準、無原則、無ゴール、不可能な思想運動を提起し、みんなが死んで行く中で、二人になって延命しようとした。
左翼日和見主義である」(花園)。
僕の見解はこの見解にほぼ一致している。
「無原則な野合による“新党”結成、森、永田の個人権力を固めるために、その権力の桎梏になり、反対する可能性のある部分を“殺し”で排除しようとした」(川島豪)。
この見解にも僕の見解は一致している。
川島豪は「反米愛国路線の放棄」を問題にし、赤軍派も塩見も「野合」を問題にした。
塩見は事件に対する大筋の見解を左翼日和見主義と確定していた。
しかし細かい事実関係、責任関係の明確化、裁断を避け、野合「新党」の問題を問題にするも、自己反省、主体に照らして森、永田に凝縮された、赤軍派、革命左派双方の人間観、思想問題に決定的に弱点を有していた、プチブル革命主義と唯軍事主義の偏向を問題にし、労働者、人民の生活感情、要求、人民大衆の社会変革の能力への確信、或いは科学的なマルクス資本主義批判の獲得を問題にし、プロレタリア革命主義を目指した。
或いは「大衆的政治闘争の中での武装」「人民の海の中での武装闘争」を追求した。
これらの連合赤軍問題の構造、プロセス、責任関係については当事者自身が話さないこともあり、最初の十年近く事実関係については真相究明が進展しなかった。
その後、永田、坂口、植垣等が、裁判の進展もあって、事実を語ることが要請され、自己弁護の裁判方針を固めて行くべく、この三者が「当事者の声」と称して「本」を出版し始める。
これはこれで、当事者としての弁明の書として、それまで発言を封じられていた状況を打破し、人民大衆が客観的に判断する素材を与える意味をもっている。
しかし、永田、植垣は所謂「ブルジョア裁判に勝利する」ことが基本目的故に、これらは極めて自己弁護、責任転嫁的なモノで、自分たちに不利なモノは隠されたりしていた。
最初、「“ブルジョア裁判”と“人民裁判”は違う。
その時は本当のことを言う」と弁解されていったが、いつの間にかそれが真実かの如く言動されていった。
この2人は、裁判で「死んでいった彼、彼女等にも問題があった」と裁判の場で、12名を傷つける二度目の言説を振りまいたりもした。
しかし、前述したように30年が経ち事実関係も出そろい始め、マルクス主義の呪縛に不必要にとらわれなく、より一歩踏み込んで総括できる条件がそろった段階で「連合赤軍問題」の真の原因、直接の原因、プロセス、構造が追求されるべき段階が生まれたと思う。
真の原因は依然として思想問題、人間観の問題である。
しかしそれは政治路線、軍事路線、組織問題を通じて現れる面を持ち、この方面の追求と一体に統一的になされるべきである。
②永田、森の野合、「新党」への道
永田の場合、一時退避、訓練場所としての山岳を、根拠地と明らかに錯誤し、それを中国式根拠地論で正当化し、それを破壊するモノとして脱走者の向山、早岐両君を処刑にした。
ここにスターリン主義が取り憑いていったと言え、これを卓抜な指導力の発揮とは決して言えないことは、人民大衆から遊離し、その中での論争、政治を避け、人民の要求を汲み上げ、組織化し、隊伍を整えることなど念頭にないことで、明瞭である。
これは日和見主義、利己主義と言える。
ここから人民解放、人民運動の大道から逸れていってしまったのである。
自己の日和見主義、利己主義を指導力の発揮、指導権の確立、自己の権威化として、専制主義的に日共(革命左派)同志に押しつけていったのである。
自己のこの権威を確立するには、他の自分より上の権威、獄中の川島の権威と制動を嫌がり、これらを否定してゆくのは自然の流れであり、永田はそれを森・赤軍派の力を動員し、果たさんとしていくのである。
川島は獄中にありながら、直接的な指示を出し、永田は、それまでそれを権威にして指導権を獲得してきたわけだが、もはやそれを必要とせず、独立化しようとしたのである。
僕は、大局的な理論的文書や「野合、是か非か」の判断を示す文章は書いたが、獄から細かい戦術方針や組織方針を出すようなことはしてないし、それは適切でないと思っていたし、出来ないことでもあった。
この辺の作風は留意しておいてもらえればと思う。
ところで永田は、川島豪の自分への女性差別を言い立て、彼の「反米愛国路線」を赤軍派や森の理論を借りて批判していったのである。
川島は始め「新党」を軽々しく提起するが、赤軍派の反対の中で、それを撤回するわけだが、永田はこれにも反発している。
森は、赤軍派が曲がりなりにも人民大衆と結合していたが故に、「よど号事件」弾圧の過程で赤軍派指導部となるが、永田以上に赤軍派の中では指導権は確立しておらず、赤軍派の中では様々な論争が続いていた。
決定的なのは、彼と同格か、それ以上の政治局員を含む大菩薩軍事訓練の同志達が、保釈出獄し始める段階で、森の指導権が脅かかされていくことだった。
この意味で、彼もまた政治的投機、赤軍派からの分派衝動を高めていかざるを得なかった。
菩薩グループの出獄を待ち、路線論争や「合流問題」を正式に提起し、論争を集約する「赤軍派総会」を召集する、ような原則的組織対応は思いも付かない。
そればかりか、分派、野合「新党」でこの危機を切り抜けようとするのである。
森は社会主義革命を堅持し、塩見の「民族解放・社会主義」路線で川島「反米愛国路線」を批判し、永田をオルグし、永田もこれに同調したフシが見受けられるが、詰め切れていず、内容的な意思一致は獲得されていない。
これは時間をかけなければ無理であり、一挙に出来るものではない。
まして、組織の合流ともなれば、いくら内容上正しいと思っても、無理であり、そもそも、内容を問題にすれば「山岳根拠地路線」は当然にも批判されるべきなのに、それは不問にされ、新左翼や赤軍派の政治生命である「粛清反対」というスターリニズム批判もまた影を潜めてしまっている。
そればかりか、その反対に言葉とは別に、それを受け入れ、実行していったのである。
永田、森が公的理由でなく、利己主義から焦り、無原則に無理矢理に、「新党」に走ったのは明白である。
組織の政治生命である政治、思想路線が軽視、放棄され、組織原則が投げ捨てられた分だけ「銃による殲滅戦」路線だけが強調された。
だが実際、それは銘文でしかなく、それを真剣に検討する論議、戦術上の戦略、戦術議論がなされたフシはほとんどない。
これに替わって圧倒的に「共産主義化」といった「決意固め」の唯心的思想運動が提出されて行く。
この「共産主義化」が、永田、森の保身、利己主義からの自己防衛としての「野合」の正当化、「新党」・永田、森権力の強化から発しているのは、今となっては明々白々である。
決して思想運動とかいった高等な運動ではない。
それは自己権力防衛、強化の「逆らうモノを殺し、へつらうモノを優遇するする」といった「粛清」に本質があった。
「粛清」を覆い隠すベールとして永田・森は「無基準、無原理、無原則なゴールなし」、「ぬえ」の伸縮自在、変幻自在の面妖きわまる如意棒として「共産主義化」運動をでっち上げていったのである。
森・永田はこの如意棒を振るうことで「党」員の生殺与奪の絶大なる権力を握っていったのである。
何故殺されていった12名はそれを批判できなかったのであろうか?
それは政治組織を構成するみんなに合意された、公的基準たる政治思想路線・綱領を投げ捨て、組織原則を投げ捨て、「新党」が「軍事」だけで成立したからである。
逆に言えば軍事が至上とされて、安易に「新党」がでっちあげられていったからである。
この詐術に引っかかれば、もはや「党員」は抽象的な、極左の「共産主義化」要求に逆らえる武器をなくして行かざるを得なかったのである。
このことは、それ以前に中国革命的教条の「山岳根拠地路線」、スターリン主義肯定の迷路に入り込まされ、2名処刑の迷路に入ることを強制されていったので、人民大衆と遊離してしまい、既に唯物論的な科学的判断能力を失っていたからに他ならないからである。
更に根底を探れば、人間主義、労働者主義、愛郷の民族主義、その集約としての人民大衆中心主義の哲学的営為、つまり人間自主や超暴力としての非暴力で、赤軍派、革命左派、或いは新左翼に共通性としてあった「左傾肯定」「分からなくなったら左をとれ」といった傾向から発する「唯軍事主義」、つまり個人主義や個人利己主義、実存主義の思想的弱さを批判する、思想的哲学的力を持ち得なかったことがある。
③「粛清」としての「共産主義化」運動の展開構造、プロセス、「共産主義化」論のペテンを暴く。
12名の「粛清」の事実関係についてはいろんな本で記述されている。
しかし、必ずしもその展開構造を冷静に解析して言っている著作は多いわけではない。
僕のここでの課題はその分析とそこでの論点の整理である。
日本の現実に合わない中国式政治路線、毛沢東「山岳根拠地」化と「遊撃戦争路線」の教条的適用、これらを原因するスターリン主義の2名処刑、永田指導権の確立、この延長、質的拡大としての野合「新党」創出、これによる永田・森の権力強化の為の「粛清」、この観点から展開構造、プロセスを明瞭にしていくことである。
この展開構造、プロセスに野合・「新党」でっちあげの組織問題が決定的位置を占め存在しているのである。
このことを踏まえれば、「同志的援助」「指導」と言った思想運動の形をとった、「粛清」政治のペテンは鮮明に暴き出されるのである。
そうすれば「汚された12名の名誉」は復権され、暴虐の中でも革命の理念に忠節であった人々が存在し、その人々が単なる「犠牲者」ではないことがハッキリし、彼らの殉教者精神を顕揚していくことが出来るのである。
何故なら、この12名の中に赤軍派や革命左派の本来の持つ革命的スピリットがあったと思われるからだ。
「殺されたモノが殺している」「殺したモノが殺されている」「“共産主義化”をみんな承認していた。
」「指導部派も被指導部派もない」「同志的援助」「革命戦士化であった」そしてその結論は「同志的援助であった」といった、かつては、森がその上申書で展開し、それを今でも展開している永田や植垣の「共産主義化」論のペテンは暴かれねばならない。
確かに「共産主義化」には、副次面として、「身を削り、人柱になっても闘おう」とする思想運動、自己反省、自己修養の側面があった。
しかしそれは指導部派にあっては決して主要な側面ではなかった。
このような「共産主義化」としての思想運動を真剣に実践しようとしていたのは指導部派ではなくて12名の被指導部派であった、ことを忘れてはならない。
「殺し、殺される場を仕掛け、無辜の革命同志達を分断し、相闘わせ、自己の権威、権力,権勢を高めていったのは森、永田ではないか?」「殺された人々が自ら進んで、同志を殺したであろうか、トンでもない!全て指導部の指令ではないか?」「“共産主義化”と言う“粛清”の手法を編み出したのは12名ではなく、森・永田ではないか?」
「殺し殺されているから共同意志としての思想運動だ」といって「共産主義化」論にダマされてはならないのである。
「殺す気はなかった」と言うが、「総括に掛けられることは死ぬことである、だから指導部に逆らえなかった」と言っているのは植垣本人ではなかったか!
尾崎君以外の死は 「死ぬことが分かっていて、総括に掛けようとしていた」のだから、これは「未必の故意」という殺人行為での心理状態の要件に当たる。
「粛清」は新倉での合同軍事訓練時の永田の遠山美枝子批判とその森の受け入れ、による森の永田への迎合、一時の感情的盛り上がりからの安易な合流確認が出発点である。
ここで永田の主導権が確立して行くのである。
遠山の口紅や指輪はハイカーを装った偽装であり、それを批判の口実にされるのはたまったモノでないが、永田にとっては遠山の存在は、見過ごしてはならないものであり、それ故に彼女を当面、自己の最大のライバルと見立て、執拗に攻撃したのである。
森がそれを擁護せず、永田の批判を容認したのは遠山が獄中と繋がり、大きな影響力を持つ存在であり、彼自身にとっても厄介で、ある面で危険な存在であり、永田はそれを知悉し、永田の森確保のための分断作戦、「新党」への踏切、赤軍派からの分離の決意を森に強要する作戦となったのである。
加藤能敬と小島さんは何故最初に総括に掛けられたのか?
「共産主義化」ということで、なにか客観的な理由があるのか、なんの基準もないのである。
あるとすればそれは森、永田に随順するか、否かのみである。
2人や尾崎が総括に掛けられた理由は「キスした」とか「痴漢行為を行った」という取るに足らないことではなく、川島豪の「合流反対」の意見書をもってきていたこと、3人が山と獄中を繋ぐ救援対策部であり、獄中と都市の政治状況をよく知っており、永田、森にとっては内部的に一定の驚異であったからに他ならない。
外部的には野合「新党」の行動を獄に知られるのは永田、森にとって致命的な事態を産み出すからである。
同じく遠山、行方も獄中や都市を繋ぐパイプ役であり、最初に総括対象になったのである。
進藤は赤軍派の頃から森と合わず、反逆的であり、総括対象となったのである。
このように見てくれば、最初の3人は、明瞭に、コソコソ逃げ隠れの野合「新党」結成にまつわる秘密の保持という、純然たる政治的判断による「粛清」と言えるのである。
そして、それは赤軍派に対しては永田が、そして革命左派に対しては森が、分担しつつ、互いに他の力を殺ぐようになされているようである。
最初の尾崎の死は意図的なモノでなかったようであるが、森がそれを「敗北死」と断じた時、「粛清=同志殺し」の路線は敷かれたのである。
「語られざる連合赤軍」の高橋の伝聞では、このことは「日本革命戦争の基礎をつくって行く上での、どうしても回避する事の出来なかった高次の矛盾」と森は捉えているようだが、野合「新党」による森、永田の権力確立のためという動機からすれば、森、永田にとって当然の言いぐさであろうが、ナントたわけた身勝手な言いぐさではないか。
榛名山での6人の「粛清」が、「新党」結成の外部関係の桎梏を断つ意図でなされたとするなら、寺岡、山崎、山本、金子、大槻の粛清はもはや「共産主義化」のベールなど投げ捨てられた、この「共産主義化」に反対し、森、永田の権力を脅かすような可能性をもつ人々内部関係への、あからさまな「粛清」と言える。
寺岡、山崎は「反革命の分派分子」のレッテルをはられ「死刑」に処されている。
「寺岡は一番強力な批判派になる要素をもった人であったのであろうし、金子、大槻もまた、永田のライバルになる人であったのでしょう」と、山本は「批判」の言葉を吐いているのである。
山田に到っては公然と森に対して「死は平凡なものだから、死を突きつけても革命戦士にはなれない、考えて欲しい」と進言している。
そして山田は総括に掛けられた際「こんなことをして何になるのだ。
畜生!」と言っている。
5節 10日間の浅間山荘「銃撃戦」
森、永田は12名の同志を「総括」にかけ、うち11名が死亡し、山田の緊縛中に東京へカンパ集めに出かける。
迦葉山の陰鬱な雰囲気、なんとなくの白けた気分からの逃避である。
そして2人はそこで結婚をする。
永田は坂口に離婚を伝える。
坂口や板東はその間に独自な判断で山田の縄をほどき、裏妙義に移動する。
3人が脱走する。
権力と遭遇する中で、革命家集団としての「連合赤軍」のスピリットを蘇らせる。
闘う「連合赤軍」!雪の中の妙義越えと坂口等は10日間の浅間山荘籠城、銃撃戦。
解放しなかったとは言え、条理を尽くした牟田泰子さんへの処遇と擁護。
彼女を「取引」の材料としなかった。
不退転、非妥協、沈黙の銃撃戦。
坂口等は死んでいった「身を削り、自傷して、人柱」になってでも人民解放、人間解放に挺身した12名の遺志に憑かれ、促され、「共産主義化」を反省しつつ、贖罪として闘った。
この闘いは、「連合赤軍」が人民の側にあり、人間として行動してきたことの証であった。
また同志殺しが「人民内部の矛盾」を正しく処理仕切れなかったことからくる過ちであったことを示した。
「連合赤軍」「新党」は、永田、森の自己防衛から、焦って、じっくりした討議も積み上げず焦ってしまい、応急、即席に野合の「新党」をでっち上げ、その無理から、軍事、共産主義化を、その変わりとして全面に押し出し、決定的なやってはならない過ちを犯し、その過ちの根底の根底にあったひたむきで,凄絶な人民解放、人間解放の大空を飛翔する「ロマン」「夢」「スピリット」を歴史に刻み込み、力つき、僅か3ヶ月で潰え去った。
僅か3ヶ月、同志殺しと銃撃戦の悲惨と栄光を歴史に凝縮し、駆け抜け、潰え去った。
体制の不正義を忘れず、亡くなった12名を忘れず、今まだ獄で苦闘している人々を忘れず人民解放、人間解放の大道を進んで行かなければならない。
 第3章、4章へ行く
第3章、4章へ行く
 第1章へ戻る
第1章へ戻る
 目次へ戻る
目次へ戻る