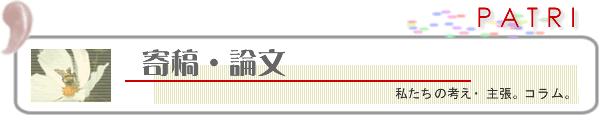旧赤軍派同志、旧第二次ブント同志達よ、しっかりして欲しい
───「燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや」、「赤軍派始末」断章
塩見孝也
1、「塩見が責任を取る」
連合赤軍事件は赤軍派同志にとって深刻でありましたし、この事件とその適切な総括の未獲得が(多々の外的要因があるものの)主体的な民衆運動の後退の重大なる契機になっていたことは事実です。
僕は赤軍派の最高指導者として、ブントの指導者として、民衆運動の代表的指導者として、これまで時代、時代に応じて基本的な解決方向を提示し、責任をとり続けてきたと自負します。
解決方向が提示できない時でも、「自分は関係ない」とか言わず、「12名を想う立場」、「自分が責任を取る」という基本姿勢で、いつも、運動と総括活動の第一線を担ってきたと自負します。
僕以上に、このような方向、レベルで「自分の方が責任を取ってきた」という人が居るなら名乗り出てきて欲しい。
しっかり、その人について検討してみます。
2、どういう理由でこういった責任の取り方をするのか
「僕が責任を取る」と言い続け、それを実行していることは「塩見に、責任はない(部下が勝手にやったことであり、直接の責任はない)が諸般の事情を勘案し、押し並べて全般的、総合的に、主体的に総括してみれば、やはり「塩見に最高責任あり」ととらえ、「12名を想う立場」を踏みしめ、「二度とこういった事件を起こさない」「そのために、当時の赤軍派、ブント、民衆運動の歴史的限界を乗り越える、積極的解決方向、方針を明らかにしてゆく」ということです。
「このような形で責任を取ろうとするのは、責任の取りすぎである」「このような姿勢は立派で、敬服するが、そうすることで、逆に民衆運動や君の部下同氏達を混乱させてしまう」と提言してくれる人も沢山居ました。
彼が編集した革命左派の「銃撃戦と“粛清”」の政治路線を機軸とする野合による「新党」結成による「同志殺し」の分析は、今でも十分検証に耐えられる素晴らしいものですが(思想上の内省、自己批判の欠如、毛沢東教条主義の欠陥はあるが)、実際、革命左派、川島豪君はこの見地で「自分は関係ない、それゆえに責任はとらない」として、岐阜、大垣の方に引っ込んでしまいました。
僕は、このような提言に感謝しつつも、あえてその提言を容れず、「全責任をとる」でこれまで通してきました。
「直接の責任はないけど、責任を取る」は一見言語矛盾で分かってもらいにくいようですが、僕の「志の高さ、遠大さ」、主体的姿勢の問題と自負します。
「志」とは「燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや」の、あの「志」の意味です。
はっきり、言います。
僕は、自分を「燕雀」と自己を卑小化したくなかったのです。
あくまでも「いつまでも、志を遠く、高く持ち」「いつまでも鴻鵠であり続けて、遠くまで行きたかったから」なのです。
このような基本姿勢ゆえに、時代の問題の核心に、連合赤軍問題総括を結び付けつつ、いつも肉薄し続けてきたし、今もそうしています。
連合赤軍直後は、思想問題を提出し、「資本主義批判――人民大衆中心」の思想を提起しました。
差別と民主主義が問題になった時代には「天皇制の問題、封建社会主義の克服」の問題を提出しました。
グローバリズムが問題になったときは「民族自主、パトリオティズム、民族解放・社会主義」を主張しました。
そして、ブッシュ・アメリカ帝国主義の侵略、覇権主義とこれに対抗したテロリズムが問題になっている現今では、その核心を「人間についての、民族についての哲学、暴力についての哲学、組織についての哲学」が核心と捉え「命を人間的に開花する人間の自主性、自衛の際の必要悪としての暴力を含む非暴力思想、開放型の組織」「ミクロでのスターリン主義の克服、マクロでのマルクス主義の超克」を提起し、実行しています。
こういうわけで、僕は、人格的、思想的問題ではまだまだ不十分で、偽善的な面大いにありですが、この克服に真摯に努め、「もと赤軍派議長の看板」を掲げ続け、戦闘を放棄したり、決してブル転したりしなかったと自負します。
3、“鴻鵠の志”を共にせず、自らを“燕雀”に卑小化する諸意見
「塩見が責任を取る」といった旗を掲げ続けているのを見て、赤軍派、ブント系の同志たちの中で勘違い、思い違い、心得違いをしている人が居ます。
赤軍派系ではこうです。
「自分には責任はない,あっても自分の過ち、責任は小さい」「塩見が責任を取る、といっているわけだから、もっけのさいわい、塩見に責任を集中すればよい」「塩見を攻撃し、塩見をつぶせば解決する」「塩見と付き合うのはもうごめんだ。
塩見と一線を画した方が良い」
「塩見の連合赤軍問題である以上、事態を目茶目茶に混乱させてやろう。
ブル転しても、攻撃してやろう」
こういった具合です。
この姿勢は、「齢50を過ぎるにも未だ“餓鬼”、ないしは“狼少年”の姿勢を引きずっている」といわれてもしょうがないのではないでしょうか。
さらにこのような姿勢は赤軍派の清算、とりもなおさず自己を清算する自殺行為、根無し草となって思考停止し、漂流する姿勢、赤軍派を自主的、創造的に止揚、超克してゆく姿勢の放棄にも連なると思います。
基本的には、自己の責任放棄です。
連合ブント系の同志たちの一部の人々も似たり寄ったりで、次の如くです。
「連合赤軍問題は赤軍派の問題で、自分たちには関係ない。
自分たちは正しくて、赤軍派は間違っていた。
それ見たことか」「ブントは塩見や赤軍派によって崩壊した」「塩見に責任を集中すればよい」「赤軍派を攻撃しておけば無難だ」「俺たちも“細く”なっているが、何とかやっている。
赤軍派とは違うのだ。
赤軍派の遭遇している問題は、俺たちに関係ない。
お茶を濁して揶揄するか、突き放しておけばよい」
こんな具合である。
これは、どう見ても自らを燕雀に卑小化させている考えといえます。
少し冷静に考えてみればよいのです。
連合ブントの同志たちは「路線―武装闘争の問題には目をつぶり、“(実際は的確な情勢分析と方針、これに基づく運動のダイナミズムを魅力としてブントは存在し、当時にあってのブントの綱領の未整備、組織論の未確立など無視し)党だ、党だ”といってきました。
しかし、そんな“党”が今どこに出来ていますか。
結果は“党”を語れば語るほど、4分5裂してゆき、惨憺たるものではなかったのではないでしょうか?
この一事だけでも考えてみるべきである。
もう一つ付け加えておきましょうか。
ブントに“党”にふさわしい綱領、組織論があったでしょうか。
そんなものはどこにもありはしませんでした。
僕が出獄した当時は、こんな情況が猖蕨していましたが、「塩見をつるし上げても何の総括にもなららない」「ブントの正、反を象徴的に体現した連合赤軍事件と赤軍派を生み出した主体的総括をしなければならない」「連合赤軍事件を、ブントの問題として、積極的、前向きに総括せずしてはブントも自分たちも立ち行かない」こういう風潮に、ここ3〜4年なってきています。
これが、中庸のまともな判断というものです。
少し考えただけでも、「塩見吊るし上げ」論が主体的で、科学的な「鴻鵠」の姿勢なく、自らを「燕雀」に卑小化しているのはすぐに見て取れます。
なぜなら、赤軍派はブントの正系であり、塩見はブントと赤軍派に股がる代表的指導者であったからです。
ブントの「異端」、「特殊分子」でもなかったし、その反対の、ブントそのものであり、塩見は自分でもあったのではないでしょうか。
4、連赤問題は赤軍派がブントの正系である以上、ブントの問題、連赤事件の総括の基本姿勢、方法は赤軍派、ブントの同時、一体的に止揚しなければならない。
「銃撃戦と“同志殺し”」としてあった、連合赤軍事件は、直接の主要な契機としては、赤軍派と革命左派の比較関係では、毛沢東思想派の革命左派の方にあるにせよ、赤軍派の栄光と悲惨、正と反、名誉と汚辱を極限化して鋭出した事件と主体的の捉えるべきである。
そうである以上、それは、赤軍派がブントの人格的にも、路線的にブントの正系である以上一続きとしてあった連合赤軍問題は赤軍派の問題でもあれば、ブント自身の総括、止揚の問題であると思います。
実際、連合赤軍事件の正しい総括なくしてどうして、ブント崩壊を総括できるでしょうか。
7・6事件は、大きな問題で、これで連合赤軍事件が自分たちブント自身の問題である、ことがぼやかされていますが、この事件があっても、赤軍派がブントの正系であることは紛れも無い事実であり、これを否定し、異論を出す人が居るなら、いつでも論争しましょう。
赤軍派は、7・6事件をブントの一分派として、直接責任を認め、全般的、総括的責任をブント自身の総括として引き受ける観点で、当時も今も捉えてきました。
僕は、こういった姿勢、方向、方法でブント崩壊問題もづっと対してきました。
であれば、連赤事件はブントがプロレタリア革命主義=人民大衆中心主義の弱さ、スターリン主義の未克服、マルクス主義の限界、ブント流組織論の未確立を露呈させてきた問題であります。
従って、永田さん、森君に直接の責任はあるにせよ、その母胎責任は赤軍派にあり、更なる母胎責任としてはブントにあるといえます。
ブントは連合赤軍問題の、この栄光と悲惨、名誉と汚辱の正、反の両側面の責任をしっかり受け止めてこそブントらしいのです。
この事件は、赤軍派、ブント、民衆全体の責任としてあるといえます。
多少ともの違いをあげつらい、「自分たちは正しく、関係ない」と捉えるのは
自己を「燕雀」とする、下司根性といえます。
従って、連合ブントの諸君は、「我関せず」で「赤軍派だけの問題」と捉えず、自らブントの問題と主体的に捉え、赤軍派の総括論争に学び、積極的に参加すべきで、総括論争を冷笑したり、おちょくったり、我田引水の介入をすべきではない、と考えます。
僕が出獄した当時は、こんな論調が猖蕨していましたが、これが、上述した中庸のまともな判断に落ち着き始めたわけです。
ブント分解の総括は連赤事件総括抜きにはありえないのです。
また、赤軍派は、自らをブント正系と捉え、連赤総括を二次ブント、ブント総括まで射程を広げずしては、総括は完結しない、と捉え、連赤問題とブント崩壊の総括を一体的に、総括を関連させて捉え、総括してゆく必要があり、ブントを清算した所で、総括してゆく姿勢をとってはなりません。
(しかし、これは、革左、毛沢東思想の総括にも射程を広げることを全然排除しない)この姿勢もまた総括放棄の「逃げ」なのです。
赤軍派の一部が塩見の人格に責任を集中するのはまったく間違いであり、これでは連合赤軍問題は何の解決ももたらさない。
問われているのは、依然として「民衆第一の観点にたって」の、あるいは「12名を想う立場に立って」の「赤軍派の止揚、超克」する問題です。
いくら、「塩見を攻撃し、我関せず」の態度をとっても、連合赤軍問題、赤軍派の問題は生涯、骨がらみで付いて回ります。
であれば、「12名を想う立場」を堅持しつつ、森君を正しく追悼し、永田さんを正しく擁護、批判、救援し、塩見と共に真の総括、真の解決に向けて力をあわせるべきである。
植垣君、永田さんが間違っているのは、最初は「12名を想う立場」に立ちつつも、連赤公判の最終段階で、この立場に立ち切れず、「同志殺し」を居直って、僕との盟約関係を裏切り、12名を再び汚し、肝心の正しく連合赤軍事件を総括しようとしている塩見を攻撃し、事態をかく乱させ、塩見と共に赤軍派系、ブント系、革左系を団結するように努力してこなかったことです。
花園の間違いは植垣の過ちのような根本的問題ではありません。
彼は“孔子の党”で言えば“子路”であり、二人とは格が違いますし、その提起には、“子路”の類ではあれ、示唆されるものがあり、彼のいうことにはかなり積極的な問題が含まれています。
しかし、軍事至上主義で野合「新党」を推進しようとした点の自己批判が無いがゆえに、しっかりと「12名を想う立場」に立ちきれず、“同志殺し”との関連での銃撃戦の評価も正しく出来ず、曖昧で、「プロレタリア革命主義、人民大衆中心主義」の思考や「ミクロはスターリン主義の克服、マクロはマルクス主義の超克」の思想的、政治的営為などトンとお呼びでない、と思うような地平に未だいることです。
あるいは、彼は、「同志殺し」を正面から肯定はしてないから、植垣のような本質的に邪な救いようの無い過ちは犯していませんが、「居直りの態度」を批判できず、曖昧な態度に終始していることです。
(尚、蛇足と思いますが、植垣、永田も居直おらず、自己批判すれば、民衆の戦士、同志として当然にも迎え入れられるべきです)
同志たちよ、「匹夫」であってはいけません。
また、「豚もおだてれば木に登る」類の行動はしてはなりません。
同志諸君、自己の至らなさを総括せず、問題を誰かに排外化するやり方をやめようではないか。
まず、しっかりと“12名を思う立場”に立ち、自分の問題として連赤事件を総括しようではありませんか。
4、下克上ではなく“出藍の誉れ”“禅譲”の姿勢、方法こそ問われている。
僕は後輩同志、弟子的同志に礼無き非難を受けると、或いは事情からこれらの人々の問題点を指摘せざるを得ない時、どう対応したらよいか、どう表現し、どう伝えたらよいか、正直迷い続けました。
大体は、少しは力はあっても、道理がない意見に、それに力で対することを禁じ、どのようにこのような人々が道理がないかを諭すか、で苦慮するわけです。
こういう言を発する人々は、その感情の底に、僕を批判することでの「覇道」からする、行き過ぎ、現実とのずれから生ずる感覚を正しく捉えなおす必要があるのではないでしょうか。
僕は、差し当たって事実関係を報告する時、同僚、後輩同志、植垣君・永田さんでさえ、評価、成果の面を主に書きました。
基本的にこの姿勢で良いと思っているのですが、そうすると例のごとく「豚もおだてれば木に登る」の類で、「自分が天下第一等」と錯覚し、有頂天になり、僕に逆ねじをかましてくる現象も現れます。
これには、僕もほとほと困ります。
「豚もおだてれば木に登る」気分に陥らないように気をつける必要があるのではないでしょうか。
或いは分別、礼なき「狼少年」の類に甘んじてはいけません。
こういう分別,礼なき「狼少年」の輩の無内容性は明ですから、植垣君は態度を改めるようにして欲しいものです。
僕は、先輩たち(関西ブント、ブント)に礼を失した対応をしたことは無いと自負しています。
7・6の際の仏さん問題については、例外ですが、あの時も感情的に激昂はしたものの、それ以上ではなく(それ以降、連合ブントが、ブントとしての体をなさず、ブントとしての受けとめをやれず、ブントは崩壊してゆきますが)、真摯にブントとして自己批判し、礼儀ある対応をしてきたと思っております。
僕は、この態度を「出藍の誉れ」の格言の意味する内容として捉えています。
「青は藍より出でて、藍より青し」という観点、地平に立てば、連帯と団結が第一となり、何で先輩同志を滅多やたらにこき下ろすことが出来るでしょうか。
僕は、野合「新党」問題、思想問題としての「共産主義化」は、軍事至上主義からする路線抜きの野合にという、政治判断の過ちが、決定的な、直接原因である、ということは厳然たる揺るがせに出来ない事実と思いますが、それをより深く探れば、僕ら全体の人間的未熟に根本的因があったと思っております。
それで、新党、思想問題に失敗したと思っております。
僕ら、特に獄中部分は、森君たちが最前線で奮闘していることにおいて、
最大限の理解、擁護、協力・支援の態度で対応したでしょうか?
基本的にはまったく否で、反対にこき下ろすような態度が全般的ではなかったでしょうか?
本来の意味での禅譲の姿勢で接してはいなかったと思います。
つまり、森君たちは「出藍の誉れ」の態度をとりきれず、僕ら獄政治局や獄同志は「禅譲」の精神で、森君達に対せず、指導権の移譲を「戦国大名がやる下克上」の域を超えられなかった、ということです。
森君たちからすれば、「出藍の誉れ」を実行できず、正しい禅譲劇や「易姓革命」に失敗した、ということです。
7・6事件もそういった性質を持っていますが、「出藍の誉れ」と「易姓」精神が主要な姿勢であったと考えますが、野合「新党」は、残念ながら道理なき「下克上」「覇道」だった、と思います。
5、僕が何故「12名を想う立場」を強調するか
僕は赤軍派系5名、革左系7名の戦士たちは、60年安保闘争、第一次ブントの戦いで斃れた樺美智子同志に70年闘争、第二次ブントで続いた人たちと考えております。
それだけの重みを歴史的に持って、斃れた戦士達と捉えています。
僕が何故「12名を想う立場」を強調するかを、少し説明させてもらいます。
それは、12名を想い続けることによって、正しい連合赤軍事件の総括を「鴻鵠の志」を涵養し続けられ、そこから僕の生き、闘うエネルギーを汲み出せてきたからに他なりません。
しかし、これには僕の個人的な生々しい歴史的体験があるのです。
革命左派の7人の戦士同様山崎同志、進藤同志は残念ながら面識はありません。
それでも、大体はこれらの戦士たちをイメージできます。
遠山美枝子同志や山田孝同志、そして行方同志は面識があります。
だから、彼ら、彼女の志、痛み、要求がどんなものであったか、かなり想像できます。
分けても、遠山同志については一番良く想像できます。
このことは、彼女が赤軍派創生の始めからの同志であった、ということもありますが、他のもっと切実な要因があるのです。
それは、彼女の恋人、夫であった高原同志の悲しみを獄で、直接に見、肌で感じたから分かるのです。
高原は武装闘争の、僕と共の、最も積極的な提唱者でありました。
森君とのつながりも深かったと思います。
彼は、僕と学生時代からの同僚であり、ブント、赤軍派時代、づっと苦楽を共にしてきた頼りがいある近しい同志でありました。
その同僚同志の妻たる人が、並々ならぬコマンドとしての決意を込めて出征したにもかかわらず、同志によって殺されてしまったのです。
なんという皮肉、なんと言う悲劇でしょうか!
彼の悲しみは如何ばかりであったでしょうか!
彼の悲しみを僕は獄や公判でこの目で見、この肌で知ったのです。
言葉も出ませんでした。
彼の悲しみには血が噴き出していたのでした。
彼は、最初「この事件を、森同志と共に総括し、悲しみを怒りに変えて戦う」とけなげな手紙を送ってきました。
その後一転して痛ましくも「遺族の立場に立つ」を宣言しました。
この彼の態度の中に、彼の測り知れない悲しみの深さを知り、彼の悲しみをどう受け取り、どう「遺族の立場」を克服するかを考えざるを得ませんでした。
僕は、彼の悲しみを通じて、遠山さんの志の深さ、高さ、遼遠さ、悲しみ、辛さをより深く感じ取ったのでした。
「12名を想う立場」はこうして、僕の中には自然に確立されてゆきました。
この中には、12名への僕の至らなさの侘びがあると同時に、高原同志を始
めとする、遺族の方々への万哭の侘びの想いが込められています。
僕は、このような経緯で「12名を想う」立場が確立されていったことを、今回の「監獄記」を書き進めてゆく中で、初めてしっかりと確認して行ったのでした。