|
1. 徒然の中での“長澤まさみ”との出会い。
|
|
この半月ほど、女優・長澤まさみについて、どう批評するか、考えてきた。
きっかけは、何気なく、病気療養の徒然に通っているビデオ屋で、「タッチ」〈犬童一心監督〉というDVDが目に留まり、借りたのがきっかけである。
如何に映画好きの僕でも、こういった特別の時間がない限り、こういった批評に時間を割く余裕はないのである。
何で、借りたのか、よく思い出さないのだが、それから「涙そうそう」「ラフ」〈大谷健太郎〉「ロボコン」(古厩 智之・ふるまや ともゆき)、「世界の中心で愛を叫ぶ」〈行定勲〉など立て続けに借り、彼女のプロフィールなども調べました。
「タッチ」を観て、並の女優ではない、と思ったからだ。
僕は、この女優については、全くといって、知らなかったわけですから、僕にとっては「新人」といえますが、やっと20歳になったばかりで、いろんな新人賞や助演女優賞、主演女優賞も既にとっており、日本映画界で、確たる地位を占め、もはや、新人とは言えず、今後の映画界を引っ張ってゆく若手俳優人のトップ中のトップ、ホープとみなされている人と言って良いであろう。
「タッチ」は、野球を舞台とする「青春ラブストーリー」といえるもので、別にそのこと自体に、新鮮さがあるとはいえないが、長澤という存在があることで、映画全体が、輝いていた。
親同士が仲良しで、双子の“勝ちゃん”、“達ちゃん”と、親が作ってくれた、それぞれとは又別の、共同の子供部屋で同居しつつ、主人公の女の子として、長澤は育ってゆく。
二人と学校に行くバスの中での掛け合い、ダンス・新体操をやっている女の子らしい挙措、達ちゃんがボクシングの試合に負け、「優しい女の子ならキスの一つでもしてくれて慰めてくれるべきだ」と半ば冗談半分にいったことを真に受け、そっとキスするシーン、その後、「あんなことをして、平気でよく居られるなあー」と達也が絡むのに「違うよ、達ちゃんだからよ」とさりげなく弁解するシーン、あるいは、達也とぬいぐるみを投げ合ってふざけるシーン、チームの記録係、マネジャー(?)として、部員全体に、マスコットの人形を編むべく、一心に努力している挙措、達也の球を受けるべくキャッチャーを買って出てヘルメットを被る、その身体、手足の長さ、けな気さ、最後の都選抜決勝戦に応援すべく、必死で駆けつけてゆくシーン――――まことに女の子らしい、初々しさが充満しているのである。
このことは、僕が、それから見た、すべての出演作品に共通に言えることであった。
実は「世界の中心で愛を叫ぶ」は一度、見たことがあるのである。
その時は、確かに、印象が残ってはいるのだが、まだ、単なる“かわい子ちゃん”女優の一人ぐらい、との区別がぼやけ、映画自体は強い印象を残していたのだが、女優・長澤まさみ個人については、決定的に追ってみようといった意欲は生まれなかった。
長身、伸び伸びとした手足、大きな目、繊細さと意外と明るさだけでなく、翳りも帯びる豊かな表情、やや丸顔の美形、豊かな髪等々の姿態、初々しさ、素直で伸び伸びとした演技、声、表情ら体全体から醸し出されてゆく柔らかで、おおらかな表現力――――彼女の魅力は絶大であるといえる。
「タッチ」には、女優・長澤個人の上記のような、魅力がいっぱい盛り込まれ、それが、僕等の時代とは、全く違う、文字通りの「新人類」として、あらゆる世代をひきつける初々しさを醸しているのである。
監督・犬童は、この彼女の魅力を引き出すことにターゲットを絞っていたのであろう。
それは、全く成功していたといえる。
青春スターから登場した女優として、すぐに思い出されるのは、宮沢りえや広末涼子などであろうし、遠くでは、吉永小百合などであろうが、さらに遠くでは、高峰秀子や田中絹子が思い浮かぶが、魅力的スケールという点で見れば、僕には、このような有名女優をも完全に圧倒する、何ものかを秘めていると思えたからです。
全般的にいえば、原節子に近い位置かな。どうだろう?
それでも、爆発的魅力を持って銀幕に登場したという点では、女優人に比すべき人は居なく、男優で見れば、唯一、石原裕次郎的規模、といって良いように思えた。
このような規模の女優ともなれば、映画監督や脚本家が、あるいはプロデューサー自身が、時には小説家すらが、そのスター性にあわせ、イマジネーションを湧かせ、構想やストーリーを練り、彼女を使おうとするものである。
又俳優は、良き監督に恵まれ、新しい自分を引き出され、そのことで、今まで知らなかった自分を発見し、より人間を練りつつ、さらに高い演技者になり、この世界でのステータスをあげてゆくのである。
大林宣彦〈なごり雪〉、森田芳光〈阿修羅のごとく〉、塩田明彦(黄泉がえり)、土井裕泰(「広島・昭和20年8月6日」(テレビドラマ)、「涙そうそう」、行定勲「世界の中心で愛を叫ぶ」)――――いずれも、映画界の、大林は別にして、僕等団塊の世代の後の監督群の錚々たるメンバーである。
このように確認してゆけば、このことは明かなことであろう。
しかし、現代は、テレビの時代、映画と相補関係にあるテレビ・ドラマでも、その存在がアッピールできなければ、旧来の映画エリアに嵌った古い型の「映画俳優」のままといえるが、ところが、彼女は、十分に両棲類で、二刀流である。
「広島」がそうであり、「セーラー服と機関銃」がそうであり、NHK大河ドラマ「功名が辻」などにも出演しているのである。
最近では、TBS日曜劇場「ハタチの恋人」に出演中である。
こういった中で、土井裕泰監督などとも出会って行っているのであろう。
ちなみに、土井は「広島」だけでなく、その前に「ビューティフル・ライフ」「グッドラック」、映画「いま会いにゆきます」など作った、監督にして、TBSドラマのエース級ディレクターといえる人物である。
こういった、次第で、長澤は、2000年、(13歳?)位から、映画やテレビに出始め、2003年に「ロボコン」で、主演を張り、演技開眼し、各種の新人賞をとり、2005年、助演女優賞、2007年、19歳の時、「涙そうそう」で、主演女優賞を取り、若干20歳で、ある階梯での頂上に上り詰めて来たわけである。
|
|
|
2. 「涙そうそう」の映画的完成度の高さと内容上の限界。
|
|
これは、夏川りみの歌ったヒット曲「涙そうそう」の歌詞をモチーフに映画化し、『いま、会いにゆきます』を手掛けた土井裕泰が監督した映画である。
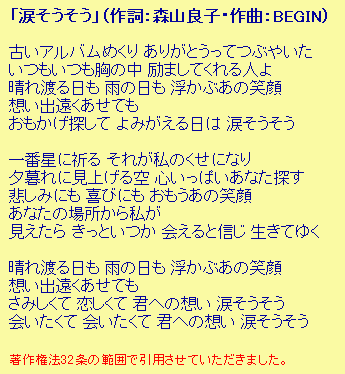
映画のエンディングの部分で、夏川りみの「涙そうそう」が、BGMとして幾度か流れる。
「涙そうそう」とは、涙がぼろぼろ流れて止まらない、という意味である。また、ウチナーは、その涙を「ナダ」と言う。
この歌は、観客の誰の心にも染み渡り、涙を誘うのである。
主人公の新垣洋太郎(妻夫木聡)、カオル〈長澤〉の兄妹は、幼い頃、洋太郎にとっては、義理の父の蒸発後、母を亡くし、離島〈石垣島?〉で育ち、兄は、妹に、生活費を送りながら、本島で働いている。
兄は、妹を幼い時から、必死で守ってゆくのである。
映像は、白黒の陰画で、幼い頃、どんなに二人が天涯孤独で、その苦節の日々を、兄がどんなに奮闘し、妹を守ってきたか、妹がどんなに兄を頼りにし、二人が、どんなに慕いあって来たかを示す。
母の郷里、離島に行く幼い兄妹、本島から離れて行く汽船の上で、必死で手を繋ぎ合って、寂しさに耐え合ってゆく陰画。野坂昭如の「蛍の墓」を思い出す。
兄は、妹への仕送り、高校、受験―大学生活を支えるべく懸命に働き、将来、自力で店を出そうとしている。
カオルが本島の高校に入学することで、再び共同生活を始めることになる。その妹が、本島に来るのを兄が迎えに行くところから映画は始まってゆく。
遠くから近寄ってくる汽船、その船首にたたずむシルエットが、段々大写しで、鮮明になって行き、成長した妹の形姿が顕わになってゆく。
幼なかった妹も大人の美しい女性に成長しかかっており、その妹の眩(まぶし)さに、兄はどぎまぎし、一瞬途惑うのである。
屋上のこじんまりしているが、ハイビスカスら沖縄の草花が植えられ、海が眺望できる、兄妹が住むには、一応十分な広さの質朴で、しっくりしたアパート、そこで「ニ―ニー」とカオルの兄妹の、水入らずの、気のおけない生活が始まる。
・沖縄の風景、島、植生、祭り、エイサー、国際通り、街、バックミュージックの素晴らしさ。
ウチナーの労働と生活の描写。流動してゆく世間。
・再会とその夜の兄妹の語らいと手を繋ぎ合って寝る兄妹の姿。それほどまでに、信頼しあい、親密である兄妹の、それまでの歴史的関係が想像される。
きわめて、デリケートな映像。とは言え、僕には、少々、違和感があったが。
兄の恋人、友人、働き先の飲み屋の夫婦、親しみを持って見守ってくれる働く女達ら、兄を取り巻く人間関係、高校入学式、親代わりとして参加する兄。
店を出そうとして詐欺に遭い一時挫折する兄。だが、兄は告発せず、自分のせいにして、又黙々とそれまで以上に働く。過酷な労働。この事件が因で、兄と恋人の関係は破綻する。兄の言いつけを守って、勉強するカオルの受験生活。
半分以上、真面目に「ニーニーが一番好き、愛している」という妹、「ばーか」といなす兄。
カオルは、兄の恋人に、「何でニーニーは、貴方と結婚しないの。結婚話は出ないの。結婚したらいいのに。そして、兄は、どうして、あんなに働くの。」「考えてみれば、そんな話しはちっとも出ないはね。それはカオルちゃんを、父親替わりで、一番、愛しているからよ!」「フ―ン」というカオルは腑に落ちない。
だが、恋人は、女の“直感”なのであろう、この兄妹愛には、別の要素も混合していることを鋭く見抜き、「カオルちゃんは、貴方が思っているほど、もう子供ではないわ」と最初に、洋太郎がカオルを引き合わせた時、彼に告げている。
祭りの夜、エイサー。浴衣着のカオルのあでやかさ。 しかし、ついに論争になる。
「何でバイトなどするのか。お前には、今が正念場の受験勉強があるではないか」 「ニーニーにばかり負担をかけさせたくないから、自分のことは自分で処理する。もう子供ではない」「ニーニーは、学歴社会をいつも、批判しているのに、何で、私にばかり勉強しろ、と言うのか。大学など行かなくても良い。ニーニーが行けば良い。」、兄は妹の頬を張る。
「毎日、毎日働いてばかりいて、自分のことはちっとも考えない。私のことは良いから、少しは、自分のことを考えるべきよ」と妹は泣きながら、それでも食い下がり、駆け去ってゆく。考え込む洋太郎。
カオルはその足で、沖縄に帰ってきた、トロンボーン〈サックスか?)を吹く、実の父、金城何がしが働いているジャズバーに行き、父と一晩話し込む。
これが、「カオルが、一晩中中年男と一緒に居た」という噂話になってゆくのだが。
この言い合いは、決定的で、想い合っている兄妹の愛情が爆発してゆく圧巻のシーンといえる。
僕は、つくずく、こういったシーンを見るにつけ、映画の醍醐味を感じるのだ。映画は素晴らしい、のだ。
映画は、人間を語る最高の総合芸術。集団化された芸術の総合労働。限りなき人間追求を可能にする良き題材、良き監督、良き俳優、情感を際立たせ、意識化させる映画音楽。そして、それを、総合化すべく、補完する優秀なカメラら諸スタッフが合わされば、映像は、最高に観客の想像力を研ぎ澄まさせ、人間の本質について、万人、億万人に、飛翔させてくれる。
長澤まさみ、妻夫木は最高の演技をしている。
この映画の、完成度は、内容は、大いに物議を醸すところがあるのだが、非常に高いのである。
妻夫木は、“ニーニーをほぼ完璧に演じきっている。彼もまた、好感度NO1とも言える、キャラを持っている。
真の二枚目とは、女性だけだ無く、誰もがすーっと何の抵抗感も無く、自然に、受け入れるような“普通”“平凡”のようで“非凡”な天性をもっている人と思っているが、彼は正にそういう人であろう。
妹の兄思い故の兄批判。妹の実の父の登場、朝帰りの妹とそれを一睡もせず待っている兄。周囲の憶測を確かめるべく、カオルの実の父に会いに行くニーニー、そして殴り合い。兄の諦めと決断。
・琉大合格とカオルの出てゆくこと、別居の決意表明。別れのシーンと二人にとって、二人の子どもの時からの思い出を刻んでいる、大切で大切なアルバムの扱い。妹が持ってゆくことになる。
この別居、別離は、二人には、相当複雑で、けじめをつけなければならない問題であったであろう。
血の繋がっていない兄妹が、一つ屋根で、暮らしてゆくには、カオルは兄への想いにおいて、女としても、心身ともに成長し過ぎなのであろう。
この別れのシーンと別れた後の、3年後の妹からの手紙は、全く主題歌そのものなのである。
このシーンでも、カオルは「ニーニーが大好き、愛している。ニーニーだけが本当の家族」と又繰り返す。見送る兄、遠ざかってゆく妹。
この、徐々に翳んでゆくカオルを追う、カメラアイが実に良い。全くの「涙そうそう」なのである。
そして、琉大生活。三年間近く会わなかったカオルからの兄宛の手紙。
「会いたくて、会いたくてしょうが無かった。離れてみて、ニーニーがどんなに、私を守ってきて来てくれたかが良くわかった。ニーニーを一日も忘れたことは無かった。父と会って、自分にも父親が居ることが実感でき、嬉しかったが、ただそれだけで、ニーニーだけが、私の本当の、本当の家族。来年、私も20歳になります。成人式を、島で迎える為に、ニーニーと一緒に帰りたい。どんなに楽しいことでしょうか。」
・台風襲来。災害を受けるカオルの下宿。
「兄に助けを求める、カオルの泣き声が聞こえてきたから」と駆けつけるニーニ―、妹の事実上の愛の告白、「本当のおにいちゃんではない、だから結婚できる」、取り合わない兄、二人の関係が、今後どう展開してゆくか、固唾を呑んでみてゆけば、兄はあっけなく死んでしまう。果たして、是で良いのだろうか。
・島のバーちゃんの“ニライカナイ”の話し。ニーニーの生前に発送された手紙と正装の着物のプレゼントが届く。涙そうそう、のカオル。
「ニーニーのお嫁になる。」と幼い時から言い続けてきたカオルの陰画。
|
|
|
3. 僕が一言、言いたいこと。――――「涙そうそう」の問題性とは?
|
|
女としての妹の早熟性と世間の倫理性に縛られた男としての兄の「鈍感さ」、だが限りない兄の純粋な愛、主題歌に込められた、兄への妹の募る思慕。
だが、兄妹、実は、恋人同士が世のしがらみを乗り越え、愛を実現し、ハッピーエンドとなるようには行かない。そんな姿はどこにもない。“ニーニー“は死んでしまうのである。
全く無残である。その分だけ、より強く、情感が募るのである。
ただ、ただ、耐える姿、耐えて生きてゆく姿の貴っとさが強調される。
限りなく、限りなく美しく、晴朗。余りにきれい過ぎるではないか!
そこで、少し、言わせてもらおう。こんないい人間関係が果たして創れるのか?そして、努力し、身の丈に応じた分だけ、幸福は返ってくるのか?
ばーばが語る「南の天国の島」、ニライカナイ信仰は、ウチナーの絶望から生まれた宗教ではないか?これを、前途遼遠の「志遠」と見てよいか!
余りに、非、オア反民衆的ではないか?
人間、民衆は、無数の各人は、各様の愛、幸せを求め、耐えに、耐えて生きる。その集積の中で、人間、民衆は生き、死んでゆくのは、冷厳なに現実である。
だが、果たして、是で良いのか!
薩摩のウチナー支配、維新後の天皇絶対主義的国民国家への暴力的編入とヤマトへの強制同化、ウチナーの宥和主義への屈服、終戦時の「皇軍」の自決強制、その後の米軍占領支配の継続、1972年のアメリカ、日本帝国主義の米軍基地と核を残したままの民衆抜きのボス交的復帰、それゆえの極東・アジア・世界に向け更にグレードアップ化した基地の島化、基地経済への民衆の隷従、ヤマト資本の侵出と開発主義、「癒される潤いのある南の島、沖縄」と囃され、観光地化されてゆくが、日本一の貧乏県、高い失業率と疾病蔓延の沖縄。
ちなみに、この映画では、米軍と米軍基地の映像は、全く出ていない。ちょっとだけでも、チラッとだけでも出すべきでは、なかったろうか。
“ニーニー”の生きる姿は、権力者達に奴隷化された沖縄民衆の忍従の姿、そのものではないか!
土井監督たちは、このような沖縄の現状と歴史をほとんど分かっていないのではなかろうか。
映像で表現されている印象からすれば、土井らにとっては依然表面的な「南の癒しの島、麗しの島」程度を出ていないのである。
洋太郎の生き方は、貧乏県の沖縄の青年労働者の典型であろう。愛するもののために、忍従し、黙々として働き、必死で、真面目、誠実に生きるウチナー青年の典型といえる。
これを、僕等は、ある面で、身勝手な、「革命的青年像」を描いて批判し去ることは出来ないであろう。
先ず、現実を生きる沖縄青年の実際を、しっかりと理解し、愛ある目で見守ってゆくこと。それからである。
とは言え、カオルの求めるような生き方を、僕等は決して否定してはならない、ということである。
二人は、愛し合い、セックスし、結婚すればよい。不都合は、全く無い、と思う。
重要なことは、沖縄の現実、日本の現実、世界の現実に、若い二人がひるまず、自分たちに押し寄せてくる予断と偏見、因習と呪縛に対して、ぺしゃんこにされず、道理を貫き、革命的に闘いぬける、思想的、政治的、理論的、概して精神的準備を培ってゆけるか、否か、という事である。
この問題は、多分、各方面で物議を醸したものと、僕は推定している。
映画の対象は、ある面では「沖縄」そのものであり、議論になるのは当然である。この問題に、監督が、割り切って、主題歌に忠実たらんとしたことは明らかである。
土井監督からは、その美と優しさ志向のロマン主義が、一方では神秘主義と他方での割り切り主義の現実主義に折衷されているような印象を受ける。
今回は、監督なりの分別もあり、それが〈精神的準備のこと)、無理、準備不足である、と判断し、洋太郎の生き方を紹介しつつ、死なす、ことで決着付けたわけである。
僕も、映画的には、そうであってもよいと思う。仕方がないのである。
しかし、総合的に見れば、内容的には、映画の「完成度」に比し、ある面で「毒草」、「ブルジョア的」「プチブル的」と言っても良いのである。
それはそうとして、問題は、それだけで、掬いきれない、残っている問題を、どう繰り込んでゆくか、ということであったろう。
結局、それを、観客の判断にゆだねるという、ある面で賢い、ある面で卑怯で、ずるいな対応策をとっているのではなかろうか。
だから、監督は、カオルのような考え、生き方も重要であることをいたるところではっきりと示し、洋太郎とカオルの対決関係を機軸に、ストーリーは作られていっているのである。
このことに於いて、長澤は、長澤らしいキャラを存分に出しえているのである。
その選択〈物議についての〉については、観客の想像力、イマジネーションにゆだねた、解する。
映画において、価値観を提示するより、観客、民衆が、さまざまな問題提起、選択肢を与えられ、それを各自が、判断してゆく手法は、十分ありえることであろう。それ故、割り切れなさが、強い叙情とともに残ってゆくのである。
|
|
|
4. 女優、長澤まさみの今後について。
|
|
●長澤の「青春ラブストーリー」の時代は、この「涙そうそう」で終わったといえる。
もう、彼女は、この種の映画には出ないであろう。
この種の映画は、この「涙」で集大成され、彼女は卒業したし、この時、19歳なのだから、年齢的に無理でもあろう。
「ロボコン」「タッチ」「ラフ」、あるいは、「世界の中心で、愛を叫ぶ」は、監督や脚本、スタッフ等にめぐられつつ、いろんな分野の青年群像のなかの、女の子像を演じていった。それぞれ、持ち味を持った「良い」映画であり、出演のたびごとに、その演技課題のギヤーアップを要求され、そのたび毎に、彼女は、それをクリアーしていった、といえる。
「ロボコン」はIT時代のハイテク好きの「部活」生活、「タッチ」と「ラフ」はスポコンもの、いずれも、青春謳歌ものである。同じ、スポコン物ながら、ここでも、与えられた情況に追随する傾向から、自分で選択して行く娘へと彼女の演技は“進化”していっている。
青春ラブストーリーでは、おはこものとして、ピュアーな愛が、何がしかの状況から提出される「生死」という厳しい問題―――ここでは白血病であるがーーーに突き当たる「愛と死」「永遠の愛」の課題が提出される。
「ロミオとジュリエット」的課題である。
これもまた「世界の中心で、愛を叫ぶ」で彼女はクリアーしている。
そして、最後の難関である、血の繋がっていない「兄妹愛」という一番難かしい、と思える課題も「この涙そうそう」で、クリアーしてしまったのである。
●15,6歳から、19歳ぐらいの「小娘」が、自分の体験を通じて語れるものとしては、「青春ラブストーリー」以外にない。
それ故、才能ある彼女が、この分野で活躍するのは当然といえば当然のことである。
とは言え、この世界から、排除された、格差社会の犠牲になっている若者達、ワーキングプーア、ロストゼネレーション世代、リストカッター、薬物依存症で等で、日々「壊れていっている」「底辺」を生きざるを得ない、長澤から見れば、「別の世界」を生きる「みじめったらしい」「青春」も厳然としてあるのである。否、それが大半なのである。
「タッチ」のような、仲良しの小市民家庭は、どんどん少なくなっているのだが、この家庭は、余りに小市民的過ぎるし、「ラフ」の少女は、恵まれすぎて、僕にはどうも、現実離れしている感じを受ける。
打ちひしがれ、ぼろぼろにされながらも、どうしても、闘わずしては、生きて行けない民衆、青年たちにとって、果たして、この映画は、本当に、身近な存在であったであろうか。
別の若者像、若者論、恋愛ストーリーがあってしかるべきなのである。
「ポッセ」の若者たち。「フリーター労組」で奮闘している若者たちの「青春ラブストーリー」があってしかるべきなのである。
彼女は「パッチギ」が好きと聞く。これは、全く良いことである。「三丁目の夕日」に描かれる「集団就職」でやってきた女の子達にも目配りができるようであって欲しい。
吉永小百合「キューポラのある町」のような青春像が、ぐるっと一回りして、もう一度、形を変えつつ、必要とされてきているのである。
●はて、彼女は今年、20歳になり、成人式を迎えた。これからである。
ポピュリズムに迎合しない、表面に惑わされず、真実を見抜く目を養い、自分のキャラを磨き、作品を、自分で選択して行く、芯のある個性を磨き、広い視野と深い人間性から来る、懐の深い、女優に成長していってもらいたいものである。
映画界もテレビらメディアの世界も、世の中も、虚飾と偽善に満ち溢れた弱肉強食の世界である。
下手をすれば、彼女のような人ですら、使い捨てにされ、ぼろぼろにされてしまうのである。
いつまでも世俗の、垢に染まらず輝き続けて欲しい。
キャラは決して弱くないが、結構器用で、何か、ポピュリズムに合わせすぎを少しは感じる。
向上心、向学心、友達を大切にすること。
何故、女優の道を選んだのか。美しいから?美しい女は、あらゆる分野で、居るではないか。初心、志を幾度も幾度も、問い直し、踏まえなおすことであろう。
時代は、大きく変化しつつある。
ぼくの見方からすれば、日本や世界の体制は、破局に近づきつつあると思える。彼女の今後も、この時代の変化とともにある。
90年代から21世紀の初頭を覆ったグローバリズム、ネオリベと復古主義がしょうけつした時代は、終わろうとしている。
為政者、権力者に身を任せていては、奴隷にされ、抹殺されてしまうことが、民衆に分かって来、民衆自身、自分自身が闘わない限り、生きて行けない時代となりつつあるのである。
映画は、この民衆とともに手を携えて進み、民衆の感性、感情、要求をあくまで表現するものでなければならない。時には、民衆の文化運動の先頭に立たなければならない。民衆の政治運動を側面から支えてゆかなければならない。
少なくとも、日本映画人は、戦前の「国策映画」の世界、政治、路線に決してはまり込んではならないのである。
あるいは、グローバリズム、ネオリベの戦争と格差、福祉、環境破壊、拝金主義、個人利己主義、低水準の快楽主義に決して追随してはならないのである。
映画界でも、映画人も、ここで、段々に、否、急激に、自己の生きる選択方向を問われてゆくであろう。
幸い、彼女が、これまで交流してきた土井監督をはじめとする監督陣は、僕の見るところでは、監督として優秀でもあるが、微温的(今のところ)ながら、また、各人、各様ながら、そういった思想的方向を選択する器量をもった人々と思える。
こういった、人々とともに、世界と日本の民衆運動に、目配りし、交流し、必要ならこの世界に、飛び込み、その中で、映画人、芸術家、文化人としての想像力、創造力を養っていってもらいたいものである。良い映画を作っていってもらいたいものである。
山田洋次監督などとも付き合っていってもらいたいものである。
女優、長澤まさみが、今のキャピキャピした時流に流されず、既存の社会、そこでの政治や文化に対して、批判的で、志を今以上に高く持ち、発言できるような自主・自立した生き方をすることを切にに望む。
|
|
|
| 〜 以 上 〜 |

