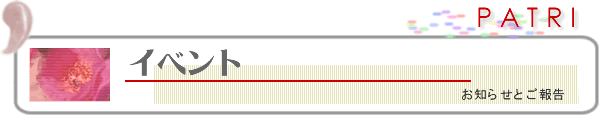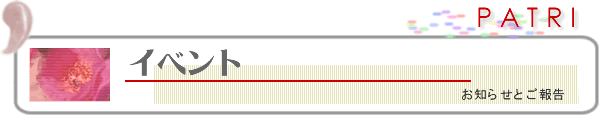|
| 去る2月25日(日)17時から、神楽坂・スキャット・セミナーハウスで第7回「資本論研究会」をおこないました。 |
|
| ● |
今回は、極めて大きな異変が伴った研究会でした。
それは、ある大学の4名の、学生諸君とその卒業生や他の1名の某大学大学院生(女性)といった若い明晰な頭脳と志を持った青年達が参加されたことでした。
これ等の「新人」達が巻き起こした精確な読解、そして情報やホットな知的な議論はこの研究会に紛れもなく新風を巻き起こしたのです。
これまでのメンバーの皆さんも、少々、興奮しました。
この僕でさえ、大いに刺激され、興奮し、臆面もなく、自分の問題意識を吐露する始末でした。
この大学は、もっともモダンな、少人数の、キリスト教―アメリカ仕込みの大学で、卒業生はこれまで、エリートとして、体制上層部に登ってゆく歴史があったようですが、そこから、「資本論」を真面目に研究するような、志を持った青年達が生まれてきていることは、実に注目に値します。
聞けば、彼等は「格差社会」の現状に不満、批判を持ち、フリーター・ニートの支援、ポッセらの活動に参加されたり、沖縄・辺の子の支援らに参加したりしているそうです。
これまで「資本論研究」も手を付けたりもされたそうです。
このような方たちが参加されることで、この研究会は、一段と充実してゆくような気がしました。本当にありがたいことです。「新人」の皆さんに感謝します。
参考までに、研究会の翌日に寄せられた、その青年たちからのメールを提示させていただきます。
|
|
|
「本日は大勢で参加させていただきありがとうございました。
問題提起も多く、新たな出会いもあり、また知的刺激に溢れた会でした。
今回に関しましては、殆ど予習ができておらず、また参照していたテキストも他の方と違っていたので音読の際に若干の混乱がありました。特に不変価値、可変価値についての理解があれば今回の範囲についてもう少しスムースに入っていけたように感じました。ですが、7章を通して、既存の経済学を批判しつつ、自分の方法論を明示するというマルクスの論理展開は素晴らしかったように思います。
他のメンバーも楽しめたようでした。今日あまり発言のなかった二人もそれぞれの問題意識をもって、独自の活動をしております。
彼らもまた参加したいと申しておりました。私もぜひまた参加させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは失礼いたします。」
|
|
| ● |
さて、今回は第1部、3編の「絶対的剰余価値の生産」の最終章、「剰余価値率」のところでした。
これを、僕らは読み廻しつつ、特に「シーニアの“最後の1時間”」を議論しました。これでもって、「絶対的剰余価値」の第3編を読み上げ、文庫本の第一分冊を終了し、次回第8回(3/25日曜日17時〜 神楽坂メゾン2F SCATセミナールーム)からは、「労働日と剰余価値量」を経て第4章「相対的剰余価値の生産」に入ります。
ともあれ、≪資本論≫第一分冊を読み上げたわけです!!
マルクスは、前回、彼の価値論を忠実に運用し、「絶対的剰余価値の生産」を論証しました。
前回、「剰余価値率」までは、つまり、自然と人間との物質代謝、質量転換としての「労働過程」とこれと一体の「価値増殖過程」として分析して来たものを前提にしています。
この過程分析で、それを、より実際的な、工場らでの「剰余価値の生産過程」に近づけて分析してゆくために、「不変資本」と「可変資本」という、現実にあった概念を設定し、剰余価値が、どこから生まれてくるかを、明確にしていったわけです。
しかも、今回は、そして、マルクスは、この章では、具体的な営業活動の収支にまで、切り込んで論じ、資本家的な、身勝手な理屈付けを、見事に暴いてゆくわけです。
つまり、不変資本は価値を生み出さないこと、生み出すのは可変資本であること。
こう言った適切な概念を案出することで、マルクスは、より明確に、不変資本は労働(労働力の消費)によって、その労働力の使用価値と価値が、具体的有用労働としては、不変資本の価値移転と保存、具体的有用労働に介された抽象的人間労働としては、新たな価値を付与すること、を、前回、証明してゆきました。
この価値増殖の過程を、凝固した過去の死んだ労働(不変資本)が、新たな価値と合体することで、蘇生し、生きた運動としての価値増殖する(まさにこのように流動する運動の過程こそが資本である。)という構造で、労働が二面的結果をもたらすことを見事に説明してゆきました。
以上の事柄は、前述いたしましたように、論理的で抽象力を持って措定されてゆくものですが、マルククスは、そうではあっても、実践的な労働者階級の自己解放を目指す、革命家であれば、常に、これを具体的な資本家、工場主、或いはこれを応援する御用理論家のおべんちゃら、嘘八百の計算の戯言を具体的に粉砕することを念頭に置いて、展開して行っているわけです。
そういうわけで、今回の「剰余価値率」論、或いは、必要労働(時間)と剰余労働(時間)は、見ようによっては、シーニアの「最後の1時間論」のマヤカシを粉砕するために、理論構築されたものと見ても、そう見れないこともないのです。
シーニア(Nassau William Senior:1790-1864)はオックスフォード大学の経済学者です。マルクスは、それを彼一流の文学的皮肉を交えつつ、完璧に批判しているわけです。
|
|
| ● |
先ず、マルクスの剰余価値率の定義から入ってゆきましょう。
不変資本:c、可変資本:v、c+v=V、前貸しされた総資本、そして剰余価値:mとしています。
但し、エンゲルスは資本家が言う「前貸し」は、労働者にとって見れば、剰余労働を行った後、“後払い”でなされるのですから、労働者の方が“前貸し”した、というべき」(マルクス・エンゲルス全集,37巻――F・エンゲルス)と補足しています。
叉、不変資本が何も生み出さないこと、可変資本のみが価値増殖する事に付きまして、それでは、不変資本は何も、この過程について何の役割も果たさないのか、という疑問について、確かに不変資本が「レトルトやその他の容器の役割」を果たすも、「不変資本の素材的姿は流動的な価値形成的な力がそこの固定される素材を提供するだけである」と説明しています。
しかし、「そのことが分析に於いてを捨象することを妨げるものではない」と説明しています。
こういうわけで、cは「価値移転」と「保存だけ」であるあるから、価値増殖をしないわけですから、剰余価値率から除外されるとし(もっとも第3部で、利潤率の検討では、投下された全資本に対しての剰余価値の比重を無視せず、仔細に検討しますが)、剰余価値率はm/vとマルクスは捉えるわけです。
この説明の補強として、彼は「無からは何も創造されない(ルクレティウス)」を引用し、「価値創造は労働力の労働への転換である。この労働力は、何よりも先ず、人間有機体に転換された自然素材である」と主張します。
ここから、搾取度をm/vと定め、それを剰余価値率と命名します。
ここの説明は、この文献を見てくだされば、数合わせでもって、詳しく説明されていますが、それは省くとして、この剰余価値率を、ここでは、賃金、つまり自己の再生産に必要とされる価値、“必要労働”とそれを越えて労働し、資本家に搾取される不払いの“剰余労働”と捉え返し、「剰余労働/必要労働と命名しなおします。
v/m=剰余労働/必要労働」は、一方は対象化された労働の比率、他方は流動している労働の形で表わされており、マルクスは、このようにして、精確な搾取度が表わされる、としています。
例えば、必要労働が半日労働で、剰余労働が、やはり半日労働であれば、搾取度、剰余価値率は100%となるわけです。
また、この労働者の自己の再生産に必要な労働時間をマルクスは「必要労働時間」と命名し、そして、この必要労働を越えて、労苦する、彼にとって何の価値も形成しない労働、言い換えれば無からの創造の全魅力を持って資本家に微笑みかける剰余価値を形成する労働時間を、「剰余労働時間」と命名して行きます。
そして、ここも需要なのですが、唯物史観論者である、マルクスならば、この剰余労働が昔から存在していたことを、「この剰余労働が直接生産者から、労働者から取り上げる形態だけがいろんな社会構成体を、例えば奴隷制の社会から、区別するのである。」とも指摘しています。
20ポンド、30シリングの生産物は16ポンドの不変資本部分、つまり綿花が綿糸に変じた部分、13+2/3と紡錘2+2/3が綿糸に変じたもの。つまり、16シリング分の生産物。全綿糸16ポンド分、全生産物の8/10。そして2+2/3ポンドの可変資本部分、つまり、2ポンドの必要労働部分、2ポンドの剰余労働部分、つまり2/10として、比例配分的に明示します。
その事によって、資本家はこの20ポンドを市場に出し、原料と紡錘分、16ポンド分で精算し、賃金3シリングを労働者に支払い、残った剰余価値3シリングを、自分の懐にいれ、27シリングに資本投下し、30シリングの資本を持って次の自己増殖に入って行くわけです。
このことを、マルクスは7章2節で「生産物の比例配分的的諸部分での資産価値の表示」の節で論じています。
|
|
| ● |
「資本論」に紹介されているシーニアの、こじつけ、作り話の御託(いわゆる”最後の1時間”説)は以下です。
10時間法の工場法が制定されたにもかかわらず、資本家や工場主を擁護しようとする彼は「“純益”は資本家の労働に負い、利子は資本家の“節欲”に負う」「11時間半の労働時間の“最後の1時間が資本家の純益”となり、その前の1時間が労賃である」という。
或いは、「工場の児童や18歳未満の少年が、暖かく澄んでいる作業室のなかの道徳的雰囲気の中に、丸12時間閉じ込められておかれないで、丸一時間,濁った外界に、追い出されると怠惰や悪習の為に魂の救いを奪われる」という工場主の弁護を買う。
この辺は、1860年代頃の事でしょうから、現代に当てはめるのは多いにアナクロ二ズムでしょうが、
いずれにしても、シーニアには、全く機械類や工場建築物や原料や労働(自分の労働も含め)ごちゃ混ぜで、何故「最後の1時間が、工場主の「純益」の計算になるのか、労働者の再生産費や剰余労働時間はどう計算されるか、さっぱり分かりません。
工場維持費や土地や機械の摩損部分、或いは原料費はソモソモ、儲けの部分には入っていかず、剰余価値は、ソモソモ、それ等を控除したものとして存在していること、そして、剰余価値率が100%(賃金分=労賃分として半日労働日分、剰余労働半日分)といた具合に、正確に概念を定めて、分析はされていません。
当時にしても、余りにもお粗末な計算なのである。
何故、最後の1時間が、工場主の“純益”になるのでしょう。何故その前の、後ろから2番目の1時間が“労賃”になるのでしょう。
剰余価値率が100%であるならば、例え1時間短縮されようと、2時間短縮されようと、それでも多少と現ずるにしても“純益”はあるでしょう。
このような言説は、法外な搾取を児童労働、少年労働に強制せんとする狙い以外の何者でもなく、何の根拠もないこと、ソモソモ、最後の1時間が「工場主の純益」といった形で、11時間半労働を維持せんとし、工場主の、「純益」時間を最後に持って来、ご丁寧に、労働者の「労賃時間」を最後から2番目に持ってくるなんて、時間順で設定するなんて、強欲のための全くの見え透いた猿知恵である、とマルクスは茶化しまわるわけです。
僕らも、こんな理屈が、たとえ19世紀半ばとは言え、まかり通っていたのかと思うと全く唖然としたものです。
しかし、唖然としてばかりはいられないのです。この21世紀の最新のグローバル資本主義、ネオリベ社会日本に於いて、不正規労働が蔓延し、正規労働もまともで無くなり、「ホワイトカラー・エグゼンプション」なる、時間外延長労働を不払いにせんとする、策謀がなされ、或いは、「健康にして最低の文化生活、セーフティー・ガードネットの最低線、「生活保護」法すらから、排除されんとする労働者が輩出し始めているのです。
うかうかはしていられないのです。
|
| 塩見孝也 |
|