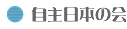





|
ワールドカップ ドイツ大会 アジア最終予選
日朝戦に思う
塩見孝也
(1)昨日の「日朝」戦は素晴らしい試合であった。
日本が2:1で勝ったが、朝鮮側(朝鮮民主主義人民共和国の代表チーム、以下“朝鮮”とする)は、先取点を取られたものの中盤戦、盛り返し、同点とし、粘り抜く。
しかし、日本側は、高田、中嶋らヨーロッパからの駆け込み帰国組みや大黒を加え、寄せ返し、ロス・タイムで大黒が見事な決勝ゴールを決めた。
決して、楽な勝利ではなかったと言えた。
僕は、予想を立てようと思ったが、どうしても立て切れず、試合が始まった早い段階でしようと思うようになりました。
「何が起こるかわからない。やってみなければ見えてこない」という、こんな試合に付きまとう一般的性格に基づく予感でもありましたが、それとは別の、何か予測がつかないものを感じていたからです。
「北」の民族的意地、精神力やスタミナ、若しかしたらのウルトラC的「秘密兵器」の登場、らの要素が考えられ、日本チームはそれにどう対応するのか、と考えました。
それに、日朝関係の歴史と現在、体制の違い、在日の人々の存在!
しかし、「日本」を勝たせる、は僕の基本姿勢は不動で、また、日本が勝つ、とは漠然と思っていました。
今の日本人チームのあの重慶での対応やオマーン戦の延長戦での得点らに見られた、著しく向上した精神的タフさ、ジーコ流の訓練と団結性、選手諸個人の練磨、そして技術的高さ、国際的経験、層の厚さ等から総合して、そう思ったわけです。
結局、試合展開は落ち着くところに落ち着いた、と思えました。
(2)「テレ朝」が独占中継したわけだが、「ワイド・スクランブル」から始まった中継は、非常に良いスタンスを取っていたと思う。
山本晋也監督らおなじみのレギュラーメンバーは、フェアープレーの精神と在日コリアンへの眼差し、日朝関係への理解に於いて極力偏見を排し、現実を冷静に見、それを民衆に紹介しようとしていました。
このメンバーを可なり知る僕としては、「さもありなん」で大いに、意を強くしました。
李漢宰(リ・ハンジェ)や安英学(アン・ヨンハッ)両選手や李選手の両親、在日の人々の立場、想いは上手く、鮮やかに紹介されていたと思う。
在日の青年達が言っていました。
「祖国、同胞のチームを応援し、勝たせてやりたい。しかし、僕等日本の地で育った、2世、3世は日本チームへの想いもあり、複雑です。フェアープレーの精神にのっとって、正々堂々と闘い、良い試合をやって欲しい」と。
ここに、在日の人々の想いは凝縮していたと思う。
この,想いの先に在日の人々は、「日朝平和・友好」を描くのであろう。
僕も同感である。
中には、「引き分け」を望みます、という在日の人々もいました。
本隊の「共和国」選手は、意地と敵愾心があったろうし、何よりも国家の「栄光」を背負わなければならない、宿命、ノルマがあったろう。
剥き出しの闘志、それが反則につながるような、やや泥臭い、なりふりかまわないプレー等も見受けられた。
朝鮮選手達の心の深層に、恩讐を超えたところの、寛容な人間的心が芽生えたか、否かは知る由もないが、両国の選手達は最後まで、抱き合ったり、心から握手したりするようなエールの交歓は見受けられなかった。
とりわけ、そのようなことをご法度徒とされている朝鮮選手達にとっては、今の日朝関係では、望むべくも無いことであろう。
しかし、スポーツはあくまでスポーツであれば、幾度もの激闘を積み重ねて行けば、そこから、相互理解、人間的連帯の道が必ずや浮かんでくるのではないか?
在日の人々が言っていました。
「負けたのは、悔しい限りである。しかし、同胞の選手は良く闘った。誇りに思う。日本選手も良く闘った。敬意を表する。良い試合であった」と。
果たして、日本チームが負けたとき、我々日本人は、かくの如く、誇り高く、晴れ晴れと、潔く、振舞えるであろうか。
僕は、振舞えたであろうと思うが、日本人は、取り乱し、みっともない振る舞いを慎み、この誇り高き姿勢、精神に学んで悪いわけが無いのである。
(3)ジーコ・ジャパンの選手達の健闘に心からエールを送ります。
日本サッカーはこの間、ずっと上昇の中にあると思う。
日本選手たちもサポーター達も一段と鍛えられてきたと思う。
これらの、青年選手達には、もうかつての如き、アジアの人々への侵略戦争の贖罪の気持ちが、メンタルな面での弱さにつながる様なモメントは殆ど見受けられない。過去は過去としてしっかり捉えられながら、それでもって民族的誇り、個人の誇りを見失ってしまうようなことはないのである。精神のタフさを身につけているのである。
サッカーは世界の全ての民族、国民が愛好する、そして、一人の選手にもっとも自主と協同の精神が問われ、ひとたび試合ともなれば、国民、民族がこぞって応援するような、稀有なスポーツである。
であれば、むしろ、選手達は、逆に、このようなアジアの諸国、諸民族とのフェアープレーの凌ぎあいの中で、或いは、世界のサッカー本場に武者修行し、揉まれる中で、本当の自分と日本人、日本を愛するスピリットやアジアの人々や世界の人々を愛する国際主義精神、愛類の心を身につけてこざるを得なかったのではないか。そうでなければ、生き延びてこれなかったのではなかろうか。
そこからして、僕のいう所のパトリオティズム(これからの愛郷をベースとする“愛国心”)を身に着けてきたというのは、僕の単なる思い入れなのだろうか。
ジーコ監督やサントスはブラジル人である。しかし、サントスは日本を愛しているだろう。日本に帰化し、日本人女性と結婚し、日本食や日本文化をこよなく愛するラモス選手は、彼の敬愛すべき先輩ではないであろうか。
ジーコ監督もそうであろう。
このような、選手と監督がいるにも係わらず、日本チームは紛れも無く「日本チーム」なのである。
ここには、明らかに偏狭な「血縁主義」を超えた、或いはその意味での「国民国家」に括られてしまう「近代」の「民族主義」、「国民主義」とは異質な、当該の大地、風土に立脚する、食文化らを基礎とする、言語らを目安とする、自主的で,自律的な個人の共同体、国家、国境を越えたり、その制動、垣根を低くし、人類愛に繋がるような、それでいて愛郷的な、パトリオティズムが成長しつつあるのではないか。
蛸壺的な国家で括られてしまうような、「愛国心」に裏付けられた「公」ではなく、絶えず流動し、矛盾しあう一国と世界の矛盾を解決せんとする、世界的、類的な視野の、パトリオティズム、国際主義精神の「公」が、当該地域、郷土から、アメリカ式グローバリズムを逆手に取りつつ、成長しつつあるのではないか。
政治に、常に文化やスポーツは規定される。しかし、文化やスポーツが、そのような政治の狭さを超え、逆規定してゆくことも十分あるのである。
僕は、ピョンヤンでのアウェイに日本チームをフェアープレイの精神を持って、応援すべく、そしてスポーツを愛する日朝両国民、民族が現在の厳しい日朝の政治関係を跳ね返し、友好、連帯を実現すべく、朝鮮に行こうと思いました。
2005年2月10日
|
|


