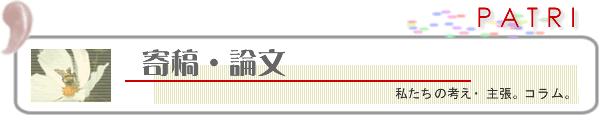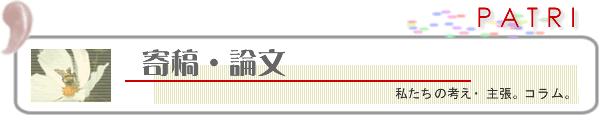*人民主義と愛国主義、「新しいさむらい精神」を孕む人間自主主義
映画「The last Samurai」について(後編)
(四)優しくあるための「強さ」――武士道・儒教における「義」「勇」「誠」そして「覚悟」について
スティーブン・ナッシュの「武士道と日本人」は注目に値する本であるが、そこでは、アメリカ道徳の実用編を表現したものとして「優しくしては生きられぬ、優しくなくては生きる資格がない」(R・チャンドラー)が引用され、強調される。僕はこの言葉を次のごとく解する。「優しくなければならない。優しくあるためには、強くなければならない。」と。そして僕は「優しさ」と相関でのこの「強さ」を重要視する。武士道が、儒教、朱子学(天道論、理気論がベースとなっている)やその支流、陽明学を基本ベースにしているところから、このことを儒教的世界観に照らして考えてみよう。人にやさしくあるべきである。つまり、仁であらねばならない。しかしそうある為には強くなければならない。つまり、仁を貫ぬき徳を得るには、社会、「世の中」における人間の道、つまり「義」、道理を貫かなければならない。そう言うこととして強くなければならない、と解する。「強い」ことには様々な意味合い、体力、健康、武道や格闘技に優れる、知と智、様々な有利な人間関係を持つ、金力や権力を持つ、武闘集団を抱えたり、軍事力を持つ、運が良い等があるにしても、その最大の要点は、思想的政治的にしっかりしていること、もっとつめれば思想的(理論的)にしっかりしていることで社会正義を貫けることである。つまり「正しい義」を獲得し、それを貫抜かんとするところに「強さ」の源泉があるのである。これを、一人の人間の人生目標からみれば、こうすることによって、社会や人から必要とされ、愛され、信頼され、人は徳を得るのである。或いは幸せを感じるのである。儒教が徳を求道、人生訓の究極、最高目標にしていることは明らかである。仁、義、徳と言った儒教的概念の関係はこうなっている。
ともあれ、仁義を実行するには、そしてそれを徳の力に凝集する媒介が「強くある」事となる。正しい思想を持ち日々磨かねばならないにしても(又正しい思想などそう簡単に見つかったり、作り出せはしないのだが)、それでもって簡単にそれが実行されるとはいえない。意志的要素が強烈に必要である。「本当にそれを信じ、実行しようとする」、虚為を拒否し真実を「すぐに」追求する、勇気、勇の姿勢、「義を見てせざるは勇無きなり」、「誠」の精神、知行合一、「武士に二言はない」態度、闘志、意志、しかし最後の最後はどんな障害、困難、強大な敵が存在しても、屈せず、目的実現を諦めない、不屈の敢闘精神が必要であろう。 この過程は、全存在、命を賭ける覚悟、死を恐れない「覚悟」をもって、日々事に対しているか否かである。つまり、決死の精神、貴乃花が使って関心を呼んだ「不惜身命」の精神と練成が必要なのである。 日々の練磨、刻苦奮闘、克己服礼の努力に裏打ちされた、覚悟を持たない主張、言葉は魂がこもっていないし、行動は中途半端となる。文字どうり、生き死にが問われる「常在戦場」の戦闘、戦いの中にある、武士は戦時であろうと、平時であろう、公的時間であろうと私的な時間であろうと常に戦闘、戦場の中に生きるが故に、もっともそのすべての言動、生き様に於いて、「自己矜持」・「独立自尊」とそれを貫徹しぬく「覚悟」を持たなければならないし、生き抜くための「死ぬ覚悟」の出来ていない武士は武士とは言えない。
これは、封建時代の軍人に一般にいえる事であろう。日本では、平安時代から発し、鎌倉、室町、戦国、江戸、幕末・維新へと発達、変遷してきた武士階級の生き方、倫理として「武士道」は存在した。これは、必ずしも武士階級に限らず、町民、農民、果ては貴族階級すらに波及し、日本人全体のモラル、文化の枢要部に位置することとなった。「非暴力」「不殺生」平和、人間愛、「環境に優しくなる」「宇宙、地球的自然の循環の中での人間、その中で人間的命を輝かす」、正に二十一世紀の人類の目標はこうでなければならない。僕は「幸福論」でマルクス主義の超克の観点からこのことを強調した。しかし、しっかりと確認されなければならないことは、優しくあること、人間愛、仁、愛、慈悲の心、不殺生、非暴力を追及する人々が、思想的に強くあることと一体である、とは限らない。民衆がこれらのことを強く求めれば求めるほど革命的インテリゲンチャーは社会の地の塩として、社会の前衛として、強くあらねばならない。
(五)今を生きる我々日本人、日本民衆は「武士道」をどう捉えなおすべきか?
武士道は新渡戸稲造が「武士道」で指摘しているように、日本人の最重要な民族的アイデンティティーの一つと言える。そして、そのガイスト(核心)は、独立自尊、自己矜持、 独立不羈、自主不屈の精神と僕は思い定めている。僕が普遍化して言っている「人間自主」の精神の日本的表れである。武士道は日本人が、生き死にがシビアに問われる長い戦乱期や平時での闘争、戦闘の過程で培ってきた倫理、規範、求道の道、処世訓がまとめられ、概括されたもの、概念と言って良い。そして、それは戦前の幕末から維新にかけて、欧米に「強姦」され、戦後はアメリカ文化に「去勢」されたりした時代風潮の中でも日本人の生き様の根元の中に息づいている。日本人の「武士道」の文化は儒教や朱子学、陽明学等中国思想にその多くの理論的、思想的裏づけ、援用を受けている、とは言え、基本的には日本人固有の倫理、哲学と言ってよい。
日本人は古来より神道を持ち、中国から儒教や仏教や道教を受け入れ、明治以降、西欧近代思想やキリスト教等も受容してき、日本人のナショナル・アイデンティティーはこの総合、総体であるが、戦闘、戦争、政治、政治闘争の際、分野では、儒教を援用した武士道的倫理、徳目が基準であった。神道的習俗、倫理はもっとその底にあり、又上にあった、のであろう。武士階級から発したとは言え、それは町人や農民のそれぞれに社会的条件、地位によって変容されて行くとは言え、伝播して行っているのであり、やくざにあっては任夾道として徳目化している。仁、義、礼、智、信の五常の徳目、それに「忠、孝、悌」を加え八常の徳と言った形でまとめられていたりもするが、それはかなり奇麗事である。
外国人のズウィック達が熱き想い入れをもって「武士道」を語るのに、僕はむずむずした、褒め殺しにあっているような、面映さを感じざるを得ない。この感覚は大方の日本人が感じたことであろう。それは、何よりも、このような価値観、規範を日本人が意識の根底に持ちつつも、忘れてしまったり、否定しまったりている日本社会の現実があることを、僕等が思い知っているからに他ならない。戦後の日本人の規範の在り様、或いは維新以降の在り様について、このような規範を止揚して、継承する思想的方途を確立できず、もがき戦後的現実に流されている、ことを感性的に知っているからに他ならない。
我々日本人は、ズウィック達の熱き想い入れに向かい合う、「新しい武士道精神」とも言える民族的アイデンティーを確立しえていないからである。それゆえに、結局「風とライオン」のショーン・コネリー演ずるアラブの王・族長のような存在感ある日本人の形象化を彼等に実現させきれず、渡部や真田らの勝元や氏尾像もクル−ズ演ずる独立自尊、自主のオルグレン像を際立たせる役どころ以上をなしていないのである。映画では吉野(現在の奈良)が登場人物、勝元らの郷であるが、そこでの民衆像や勝元等との結合関係は、「7人の侍」と農民の関係像までとは言わないまでのも、もっと掘り下げられてしかるべきある。余りにおざなりなのである。薩摩兵学校と民衆の関係らが資料として提供されていれば、もっとリアリティーあるものが描かれて行ったであろうが、残念ながら、勝元ら武士集団や家族関係で完結し、切腹、桜や禅などが付け足され、「死の覚悟」や寡黙、玉砕精神等文字通り、過去への賛否、詠嘆としての「THE LAST SAMURI」に終わっているのである。その他の「不平武士の反乱」は別にして、西南戦争・西郷らの戦いには、後の自由民権運動に継続されてゆく、開明的要素もあれば、民衆的な要素も孕まれていたのである。コンミューンとしての「暁舜の世」を目指した、西郷はキリスト教への素養があり、彼の幕僚には村田新八を始め多くの開明的幕僚が居たのである。ここには、大久保らとは違う、保守主義でもない、言うなら「真の近代の超克」的可能性が孕まれていたと僕は思っている。
しかし、この限界をアメリカ人のズウィック等の責任、いかにもの「ハリウッド的映画」として、簡単にいなすことは断じて出来ないだろう。問題は前述したような、日本人側の問題があり、十分に「新しい武士道精神」を語りきれていず、ズウィック達に十分に向かい合えていないところにある。日本映画「たそがれ清部衛」は山田洋二が初めて描いた武士、下級武士の生き様である。ここには「七人の侍」とまでは行かないまでも、「矜持」の侍の生き方が描かれている。「壬生義士伝」にもその萌芽がある。テレビ番組であるが、今年の正月ワイドドラマ「竜馬が行く」(テレビ東京系列)では「優しさと強さ」の問題が探られている。あるいは戦国キリシタン大名「大友宗麟」(NHK正月時代劇)でも同じテーマが探られている。 毎回三十%以上の視聴率をとる木村拓也の新番組、「プライド」(フジテレビ系列)はこのようなテーマを現代を舞台に展開してゆくようである。今年の大河ドラマ(NHK)、香取慎吾主演の「新撰組」は果たして、どのような内容となるのであろうか。
日本という国が、イラクでの日本人外交官の死やアメリカに強要され、アメリカの犬的に対応するまったく利だけが目立つ、義のない自衛隊海外派兵、他方での朝鮮国の核武装・ミサイル問題に揺さぶられ、もがく中で、日本民衆、日本人はパトリオティズムとしての愛国心、新しい武士的精神を模索し始めているのではないか。「民族とは何か」「国家とは何か」「皇室や日の丸をどう見るか」こういった論争テーマは今「侍(さむらい)精神」を日本人がどう考えるか、に思想的には煮詰まりつつあるのではないか。僕は、このような問題について、三年前に発刊した「幸福論」(オークラ出版)で展開した。それを読んで頂ければと思う。
中国では、水滸伝の百八人の英雄、豪傑に典型化されているが、僕は「武士道ガイスト」とは、黒澤描くところの勘兵衛ら「七人の侍」の生き様で良い、とかねがね思って来た。僕はこれを武士像の典型としたい。武士は民衆や民族の「護民官」であり、その意味で「革命家」「愛国者」であるべき、と思ってきた。このような「武士像」は、安定した体制の時代では、いかに徳目化されようと、現れにくく、時代が大流動する、激動の時期、言い換えれば変革の時期ともいえる、平安末から鎌倉期、戦国時代、幕末・維新期のような時代に、人間の原像のような様相を呈しつつ、光を放つ。民衆の中から、その「上に立つ人々」、つまり、変革のリーダーとして登場する。荘園を武装して守る初期の農民、源氏や平氏の棟梁やその一族郎党の御家人、足軽、鎌倉武士、そこには多くの「剛の者」「つわもの(兵)」、「悪人」と言われる、古代の因習や偏見に捉われない、独立自尊、独立不羈、不屈で創造力に富んだ勇気ある行動をする人々が輩出する。それは、生産力が画期的に上昇し、それが旧来の古代的、中世的守旧秩序を根底からぶち壊す革命的変化を社会の根底から民衆が、吹き上げさせてゆくような戦国時代、この発生期の武士道、独立自尊、不羈、不屈の想像力、創造力を芯とする「剛の者」、「悪人」の気風は、「成り上がり」、「下克上」や「裏切りご免」を平常とする戦国武士に受け継がれて行ったのである。ここから、北条早雲、斎藤道三、信玄や謙信、信長、秀吉、家康、あるいは伊達正宗等戦国大名とその一統や農民を擁護するような活力ある、武士階級が新たに生まれてきた。彼らは、中国、隋の始祖、煬帝のように、最初は農民一揆のリーダーとして、登場し、権力につくや、専制君主に変質し、農民に敵対する典型的なコースを示さなかったにせよ、もともとは農民や庶民の出自であり、似たような動きをしたのである。戦国大名はその統治において限界を持つものの、古代の専制的奴隷制の桎梏を根本的打破し、農民や商人、民衆の要求をよく汲み上げて行った。そうしなくては、生きられなかったし、統治を維持できなかったのである。
農民コンミューンであった富樫一揆を援助した武士達、浄土真宗ら宗教的外皮をかぶった農民・庶民の革命的自主運動、一向一揆を助けた武士たち、これらから外れた武士・リーダーは文字通り、戦国大名に反発し、民衆の側に立ったりし、銃製造、駆使に長じた雑賀孫一の一統らのような、無数の独立自主の武装集団が排出し、彼らは何者にもとらわれず自由闊達に生きようとしたのである。黒澤明はこのような武士像を彼のロマン、想像力、知性、映画監督的能力を総動員し、「七人の侍」達に映像化して行ったといえる。そして、このガイストは幕末の維新の尊王攘夷、尊王倒幕、開国・近代化を掲げて闘った、志士たちに更に継承され、発展してゆく。つまり勃興する産業資本家や、商人、貿易家ら資本家階級や独立自営農民のリーダーとして、登場した、フランス革命の革命家達ではないにせよ、主として欧米帝国主義の植民地化の危機に反応すること、つまり「愛国」「愛族」が、原動力であったにせよ、マニュファクチャー的実業家、豪商や町人、農民らの気分、要求を緩やかに反映し、この意味では「愛民」ももっていたが、封建体制を打倒し、近代的国民・民族国家を作らんとする、愛国革命家が日本では「武士道」を信奉する下層武士階級から輩出していったのである。
このように、武士道ガイストは生まれ、時代とともに、様々な多様性を帯びつつ、変化、発展し、展開して行く。ところで、僕らが、特に注目し、分析し、批判的に継承しなければならないのは、なんと言っても「維新の志士達」であろう。その思想の軸が民族自主・攘夷の国学、その広い見識は洋学から得、革命思想は儒学の「名文論」や孟子の「易姓革命」の思想であったり、行動学は知行合一の陽明学であったりし、時には実学すら入り込んでいた。「忠君愛国」の藩の君、殿様への「忠」は大して意味をなさず、脱藩や藩政改革が横行し、尊王攘夷を裏付けた国学と言っても、極めて実際的で、天皇は国と民族の進路、方向指示器、シンボルとしての「玉(ぎょく)」に過ぎず、むしろ、行動の思想的、理論的リーダー、松下村塾の吉田松陰や薩摩党の西郷隆盛、土佐勤皇党の武智半平太、海援隊の坂本竜馬への忠誠、同志的連帯の方が強かった。
流動する情勢、価値観の目まぐるしい変化からすれば、正に独立自尊、独立不羈の精神、自負・矜持の姿勢こそ必要とされた。松陰は「かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂」と歌ったが、他方で儒学・朱子学や素行の軍学に通じ、入獄中に庶民の生き様、心を知った。西郷についてはすでに述べたが、彼が二度の流刑の中で庶民と接したその意義を再度強調しておく。江戸城明渡しは、西郷と勝海舟の会談で実現したわけだが、それをプロモートしたのは山岡鉄船であった。「無刀剣」「人間本来無逸物」を唱え、端倪すべからざる著作「武士道」を遺した、武道の達人で、生涯人を殺さなかった、山岡鉄船が単身、官軍の陣営に乗り込み、西郷と話をつけ、西郷・勝会談となっていったのだが、山岡は幕府の剣術指南で当代第一の剣客、西郷に遜色しない巨漢であった。彼は清水次郎長や博徒、浮浪者達に慕われた。その時の印象を後に西郷は次のごとく記している。「命もいらず、名もいらず、官位もいらず、金もいらぬと言う人は始末に困る。この始末に困る人でなければ大事は出来ない。なぜなら、こういう人は、ただ単に無欲と言うだけでなく、日々道を行っているからだ。正しい道を歩き続けているからこそ自信があって、何もいらぬと言えるのである」(「西郷南州遺訓」)ここに、山岡鉄船の面目とそれを評した西郷その人の面目が躍如としているのである。このことは、岬一郎「新・武士道」(講談社)に紹介されている。なお余談だが岬は僕が第二次ブント時代、早稲田支部に関わりあっていたころの、マル戦はブントのキャップであった。
「忠」を論じるなら、決して殿様や天皇ですらなく、彼らが天意として、不可視の想像の中にある、国・国家、『日本国』、当時では「国民国家に概括される」『日本民族』への忠誠であり、列島に住む人民大衆へのーかなり漠然としていたがー忠義であった。この忠義は四章で述べた天ー徳・仁・義の儒教の世界・自己認識、求道ー倫理からくるものであった。この儒教の「義」認識は彼ら志士たちの様々な思想の中の共通の思想的背骨をなしていた。つまり、集団、共同体の利益に奉仕する、共同体の利益、要求と自己の要求は一致する、全体の利益に自己の利益、要求を合わせる、のが正しい、と言う信念である。この「義」倫理があったが故に、水戸天狗党の乱、生野や吉野・保津川の乱、安政の弾圧大獄での先駆的犠牲、長州武士の蛤御門での犠牲、新撰組のテロ、第一次長州戦争での犠牲多い敢闘、馬間戦争での犠牲ら無数の犠牲に屈せず、維新(革命)闘争は不屈に貫かれていったのである。
そもそも、この人々は何ゆえ「志士」と言われたのか。その「志」とは一体何であったのか? 言うまでもなくそれは、民族や国、国家に尽くす、という意味での「忠」であり、義であったからに他ならない。欧米の帝国主義・植民地主義に抵抗して、列島住民を守ること、それを守りきれず外国帝国主義に諂う幕府体制を倒し、新しい国民国家を樹立する、と言う志があったればこそであった。尊王攘夷→尊王倒幕→開国のコースを辿った愛国・愛族・愛民こそその志、義であった。「義」「忠」が時代の特質、流れの中で、「愛国」「愛族」の大義へと昇華されて行ったのである。孟子がそれは孟子の「天の将に大任を下さんとするや、先ずは心志を苦しめ、その筋骨を労し、その体膚を餓やし、その身を空乏し、行い、其の為すところを払乱せしめ、心を動かし、性を忍び、その能わざるところを会益せしむるの故なり」(告子意句)と述べたような途方もない「艱難辛苦」のに様態を、敢えて、彼等に引きうけさせ、耐え抜かせたのである。このような、愛国・愛族の義はこれまでの武士道精神の中には、共同体に尽くすものとしてあったとは言え、或いは元寇の際、働いたとは言え、基本的には存在しなかった。この大義、志に向け、これまでの武士道の文化的蓄積、独立自尊、武勇、信義、礼の徳目、己を恥じないで生きる、脇差心、命をかけて責任をとる、切腹慣習や辞世の歌を詠む、日本人特有の「覚悟」等の「武士道の生き方」が、新鮮な生き様として復活して行ったのである。
人間は「自主性を持った社会的存在」である。社会集団の要求と自己の自主要求を統一せんとする存在であり、社会集団の要求に自己の要求を殉じさせることが出来る存在である。自主的で、独立自尊の精神、自負・矜持の自主的な人ほど、社会諸集団の在り様、要求をしっかりと考え抜き、その自己が信ずる集団の要求に自己を殉じさせる、殉じさせてゆくことが出来るのである。そしてその社会諸集団の在り様、要求の問題は幕末・維新期では民族と国の在り様、要求の問題となっていたのである。人民大衆の前衛党を名乗っていた、戦前・戦後の日本共産党やその学者達である講座派は、スターリン・コミンテルンの権威に屈服し、主体性を失い、明治維新がアジア初の民族・民主の近代革命であったあったことを否定し、封建体制の同じく封建制である「絶対王政への再編成」として、徳川氏に恨みを持つ西南雄藩の天皇を頭に担いだ報復戦をやったなる、馬鹿な的外れ認識を受け入れ、戦前革命を挫折させ、帝国主義戦争を許してしまった。この認識は維新の志士達やその「さむらい精神」を侮辱する、何ものでもないし、この過ちは戦後の民衆運動に於いても問題と限界を孕ませることとなった。支配勢力の側に欧米礼賛、盲従があっただけでなく、民衆の側にも民族と人間の自主性を歪める欠点が日本近代にはあったのである。
(終章)「武士道」「さむらい精神」を現在にどう復活させるか。
さて、「THE LAST SAMURAI」の映画評を通じて、「武士論」を論じたわけであるが、それもまとめの終章を迎える段階となった。この段階で、これまで展開してきた、「武士道論」をまとめつつ、僕の「新しいさむらい精神」の大綱を展開してみよう。
第一、武士道の本質は死ぬ「覚悟」を持って、生き抜き、自己の独立自主、自尊を貫かんとする、強さ、闘志である。その生き様に於いて、全世界を獲得せんとする、精神である。これが、生きるための「つわもの」「さむらい」の人間的本質である。死は自己目的化されていず、「覚悟」はあくまで生きるための覚悟であり、生きるための独立自信から生まれるものである。この「覚悟」をもった自主精神こそが万人に畏怖と尊敬心を掻き立て、心を揺り動かせるのである。
第二、僕等は「武士」について、社会的存在としては人民大衆の「護民官」、国と民族の関係では、「愛国者」と捉えるべきであろう。民衆運動との関連では、「優しさを最後まで徹底できる強さを持った人」それ故に「人の上に立つ人」、人民運動のリーダーと捉えるべきである。総じて革命家と捉えるべきであろう。
第三、「武士」論、「武士道」論、「さむらい精神」論も捉える人の社会的立場によって、その内容も様々である。その多様性は、様々な時代ごとに生きる武士階級のあり方もバリエーションをもっているからに他ならない。したがって、その評価の違いはその人が、どのような時代の武士階級の在り様を評価し、継承・復活させんとするか、で分けられてゆく。つまり、様々な「武士道論」は、大別して鎌倉後期、南北朝・室町、とりわけ江戸時代の武士の在り様を評価する人達と武士階級の発生期の平安後期・初期鎌倉期、戦国時代、幕末から明治初期の維新期の武士の在り様を評価する人々に分けられて行くのである。
それでは、僕等はどの時代の武士像を評価し、継承、再構成し復活させようとするのか?この問題についての、僕等の見解は極めて明瞭である。僕等は明らかに後者なのである。前者は国と民族の体制が安定したり、より古い時代が復古したりする時代であり、武士階級はその安定のため、封建君主の家来として、人民支配の為の武勇を駆使する身分であり、「武士道倫理」もそのように構成されている。我々が評価する時代は、古い体制、守旧階級と勃興する民衆階級が激突する変革の時代、つまり五章で述べた、平安末から初期鎌倉期、戦国時代、そして幕末である。そこでの武士階級は、人民大衆の中から生まれ、人民大衆の要求、利益を実現すべく、古い体制を打破すべく、守旧勢力と革命的に闘う、民衆の先進的リーダー、勢力であり、「人民の護民官」「愛国者」、総じて「革命家」なのである。ここに武士の社会的本性、役割があらわれる、と見る。明治以降の「武士道論」は徐々に後者の見解が薄れ、前者的見方が台頭した、と見る。部分的にその後は共産党の中の革命的コミュニスト達、2・26事件の将校や神風特攻隊の青年達に蘇ったりし、敗戦過程のインドネシアら東南アジアで、民族独立度率運動に転進、挺身した将校・兵士達の中に蘇って行ったりしたが。
第四、それでは、僕等は、武士道を現代にどう蘇らせるべきか。第一と第二のガイストを基本観点にして、「あくまで「愛国、愛族、愛民」を基本目的として、「武士道」は現代的に再構築されるべきである。 この三目的に「愛類」と言うか「人類協同」「諸民族共和」、民衆の国際連帯を核心とした、人類愛、「愛類」が、現代では付け加えられるべきである。 尽くすべき対象は人間それ自身、国と民族、人民大衆、そして人類の四つである。 国や民族を否定する、嘗ての「左翼」、「愛民(人民大衆)」や「愛類」を否定する、嘗ての「右翼」は過っている。 国や国家は必要で、民族は幻想でなく、存在している。このことを前提にすえて、その歪み、間違った在り様を正すべきなのである。その正しい在り様の創造、その誤った在り様を正すのは歴史と社会や世界の主体たる人間であり、人民大衆、民族であり、人類性であり、その力の源泉はその自主性追求の志向、国と民族に責任を持ち、その自主性、主権を擁護する志向、その主体を人民大衆に据えること、人類の類的協同志向の中にある。 この点を否定し軽視し民族と国家だけを考える、かつての「右翼」は誤っている。民族は互いにその自主性を認め合い、協和しつつ「人類協同」に向かっており、それが自主を生命とする民族の本性である。自民族中心の民族利己主義は過ちである。とりわけ、他国・他民族の主権、自主権を外からの暴力で否定する侵略は絶対に許してはならない。
天皇、天皇家は「在った方が良い」とは言わないが、現段階では「あっても良い」と思う。特別の歴史的存在で、象徴的評価を受けても良いが、それをもって、実体主義的に民族の中心とか、始祖とか考えるのは過ちである。或いは、さしあたっては、このことに拘らないにせよ、生まれながらにして、特別の身分、特権を現在でも与えられるべき特別な人、血筋、家系と見るのは過ちである。民族は人間自主のために必要で、正しい社会生活単位であり、それは人民大衆中心、民主主義、国際主義・類的共同性、パトリオティズムを留意しつつ発展、強化されるべき。 「忠義」はこのような人間(の自主化)、人民、国と民族、人類に向け発動されるべきである。 「義」「大義」はここから設定されるべき。維新以降、とりわけファシズム期の「忠君愛国」は否定されるべき。「信義」「礼」はこのような「義」を心棒にして再構成し、活用されるべき。「武勇」は練られるべきだが、使うことを目的とせず、人を殺さず、生かす、活かすことに向け役立てるべきものである。「恥、辱め」を全存在をかけて拒絶し、「名誉」を大切にする生き方は大切である。このような志、大義の実現に向け「覚悟」の気風は重んぜられるべき。
民族と人民の前衛、変革者たる左翼と右翼はその垣根を、人民主義と愛国主義、「新しいさむらい精神」を孕む人間自主主義で打ち破り、それぞれの長所を綜合し、反米愛国の陣形を整えるべく大合流すべきである。これが、ズウィック氏達に向かい合うべき、日本人の「武士道」についての僕の態度と考える。
前編に戻る