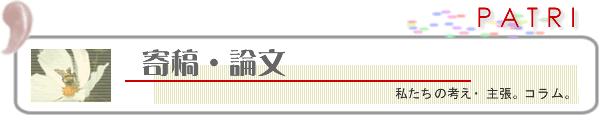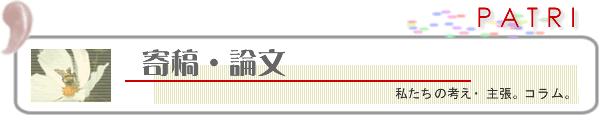*「侍(さむらい)精神」を日本人がどう考えるか
映画「THE LAST SAMURAI」について(前編)
(一)アメリカ人の「武士道」への熱き想いいれを原動力とする映画的面白さ
この映画いついては、封切前から評判になっていたし、僕はエドワ−ド・ズウィックが監督をしているのが、加えての関心であった。この人に関しては、「グロ−リー」や「リジェンド・オブ・フォール」の監督であり「グリーン・ディスティニー」のプロデューサーであることで知られており、勇武、壮心、正義感やパトリへの美的とも言えるような限りない共感性、ネーティブアメリカンや黒人、滅び行く人たち、弱者への労わり、自然への敬虔さ、伝説への憧れ、想像的、創造的人間性への確信らを特徴とする極めて骨太な感性、思想性、見識を持つ、重量感ある人物であることは知っていた。
彼の映画は極めて強烈な魅力を保持しているのである。こんなことを言う前に、広告のチラシのクルーズの侍(もののふ)、緋縅の甲冑姿、渡部謙、真田広之の勇姿、小雪の凛にして潤いある姿のかっこよさを見れば、さらに「グラディエーター」の脚本家が参加していることを知らされるだけで、ひとかどの映画ファンならもう堪(こた)えられない、感じとなってしまう。僕は登場人物の武士、勝元を見て、「風とライオン」でショーン・コネリー演ずるアラブの族長・王にして武人の誇り高さをすぐさま連想した。
ともあれ、いっぱしの映画ファンなら必ず、「映画の醍醐味」を味わえるものと本能的に直感する筈である。 僕も、うずうずしつ続け、封切の直後の或る日、朝一番で駆けつけた。予想を裏切らない出色の出来であった。と言うより予想を越えた名作、問題作、異色作と言えた。 カメラ、歴史的考証、舞台装置、衣装、戦闘、騎馬、格闘シーンら数々の名場面の連続、ストーリー展開の巧みさ、脇役まで含めた俳優たちの所を得た隙間のない抑制、洗練された振る舞い等の特質から見てこの映画が第一級のエンタテインメントであることは論をまたない。 観客はこの面で十分に大満足する。
しかし、この映画の最大の特徴は 第一にその主張、論点が武士道について熱烈な評価、憧憬、熱い想いにあることは言うまでもない。 このズウィック等の認識においてこの映画は政治、思想、文明・文化論的な面での一個の強烈な主張をもった作品になっているのである。 僕等はアメリカの優れた映画人の提出した武士道認識をどう現代の日本人として、理解するかを問われる。同じことの、比較文明論的、東西文明論的切り口なのだが、アメリカ人のズウィックから見る西洋の騎士道的精神と武士道をどう見てゆくか、も考えるべきであろう。映画は南北戦争の英雄にして、その後ネーティブアメリカン虐殺に手をかさざるを得なかった軍人、オルグレンが、ズウィックが想定する日本武士の軍人と戦闘の過程で出会い、手合わせし、打ち合って行く中で武士精神を理解し、同時に一度は死に絶えていた、自己のうちにあった騎士道精神を蘇生させてゆく展開の中で、両者の相互理解、融合の問題を自然と考えてゆかざるを得なくさせている。
(二)日本民族派にエールする反日米国家的映画
第二に、そう言う内容であるが故に、この映画は日本においても、アメリカにおいても極めて強烈な論争を巻き起こす、影響力をもつ異色な問題作と言って良いのである。僕などは良くハリウッドがこんな映画を作らせたものだと考えざるを得なかった。その点で、ズウィック等が映画人としてよい映画を作ろうとする純粋なひたむきな志向を原動力に創作活動に没頭したことは疑い得ないにしても、日本に対し、またアメリカに対して、現在的にこの映画がどんな役割を果たすか、総じて日米関係をどれほど念頭においていたか、念頭に置いていたなら果たしてそれはどんな思想的背景、意図をもって作られたか、について強い興味を持たざるを得なかった。
「パールハーバー」は「ライジングサン」のような敵愾心、日本蔑視の思想を隠そうとしなかった、映画と違ってコンピューターグラフィックスの技術を大体的に取り込んだ、単純な戦争とラブロマンスのエンタテインメントであり、決して政治的意図をもった映画とは言えない、にも拘らず、日本、アメリカにおいて、日本、日本人への敵愾心を煽った映画か否か、で相当の物議を醸さざるを得なかった。日本軍の真珠湾攻撃より約七十年前、現在から百三十年近く前の、未だ激動冷めやらぬ維新直後の歴史を論じたものであれ、そこには現在の日米関係の原点的諸要因が胚種されている。それを、真正面から日本人のナショナル・アイデンティティー、パトリオティズムに直結するような「武士道」を賛美する形で描いているのである。であれば、「ライジングサン」や「パールハーバー」とは反対の意味合いで、より強烈な物議が醸されるのは必定である。映画では、微妙な形でぼかされているが、「不平武士の反乱」というよりは、勝元は明らかに西南戦争の西郷隆盛を素材としており、登場人物の大村は文字通り、初代日本陸軍大臣大村益次郎を指しているようにも思われれば、それ以上にストレートに「近代化」「脱亜入欧」「欧米模倣」の旗手、西郷の対抗馬の大久保利通を示唆しているように思われる。
そして、順逆不二の維新後の西郷の行動は未だ日本では論議が続いている。映画はそこにまで踏み込みながら、巧妙に問題をぼかしたり、ずらしたりしているように思える。そうとは言え、こう見てくれば、この映画は、かなり自覚的なアメリカの為政者達にとってだけでなく、日本の為政者達にとってすら「反国家的」映画と言えるであろう。実際、映画的人気は高いものの、封切直後ころからアメリカでは日本への通敵映画として政治的非難の声があがっていると聞く。又日本ではブッシュ等ネオコン勢力のユニ・ラテラリズム(単独覇権主義)とグロ−バリズム、それに追随し犬となっている、小泉らの従属・追随路線に反発する民衆の反米、反小泉の気分を煽ることは確かであろう。そのプロセスの過程に登場してくる隘路や論点を、テーマに沿って、多数の製作スタッフの集団作業を介して、解決して進むところが小説創作と違うにせよ、映画創作も又創り始めたら、テーマの理路に沿って、ごろごろと坂道を転がってゆく、止めようがない、車のようなところがあることでは変わりがない。監督であるズウィックが最初描いていたようなイメージとはまったく違った形で、テーマに忠実であれば創作のプロセスを経て、結果としてもしかしたら思いもよらぬ映画へと仕上がってしまったのかもしれない。
ハーバードで、日本通、日本びいきの学者大使であったライシャワーの直弟子となり、日本について深く広い、造詣・素養を持つズウィックであればこの理路の道行きに、恣意的に逆らうような事をせず、自然と身を任せ、監督して行ったのであろう。トム・クルーズは大の黒沢ファンの日本通である。彼や時代劇俳優として、日本文化や武士道らにも造詣の深い渡部や真田の意見を聞き入れてゆけば、自然とこんな仕上がりになって行った、ということであろう。そう、見てくれば渡部や真田はひとかどの見識・素養を持ったプライドある俳優と言わなければならないし、文化における民族派革命家といって良いのかも知れない。創作過程の道行きがどうであれ、ともあれ、この映画の政治的評価については、ここでは、この映画がアメリカの現政治、現体制に反逆する、日本民族派や日本民衆にエールを送る作品になっていることをしっかり押さえておくべきであろう。
欲を言えば、維新後の近代化派と反近代化派・近代の超克派、欧米追随派と国粋派と言ったシンプルだが通俗的維新直後の状況把握の図式に依存せず、もっと西郷像、西南戦争の評価に踏み込んでくれれば、勝元像はもっとグローバルな視野を持つ深みのある人物に描かれて行ったと言うことである。西郷隆盛は倒幕回天、アジアで最初の民族独立、民主の革命(近代革命)の最高のリーダーであったばかりでなく、「敬天愛人」の民衆愛を持つ文字通りの近代の超克派であり、東北アジアの欧米、ロシア帝国主義に対する連合・共和を目指した真のアジア主義者であった。
(三)ズウィック達が考える「武士道」や「近代の超克」とは?ーーマルクス主義を揚棄した自主哲学に於いて、真の「近代の超克」は実現される。さて、ズウィックが想い描く武士道の内容とその意義である。
義: 侍たる者、他に対して誠実であるべし。又他から惑わされることなく、己の正義を貫くべし。
真の侍は誠実さと正義に対して、微塵の迷いもない。そこにはただ「真実」と「偽り」があるのみ。
礼:侍たる者、非道な行いを禁ず。そのような強さを誇示する必要がないのが侍なり。
又侍たる者敵に対しても礼を欠かざるべし。人に対して敬意なくしては人間も動物と同類。
侍は戦いにおいて己の強さだけでなく、他に対する行いによっても敬意を払わるべし。窮地においてこそ、真の侍の内なる強さが見える。
勇: 侍たる者、行動を起こすことを恐れる人の中から先人を切って決起すべし。侍は英雄的勇気を持たなければならない。
危険にみちたるものであるが、その勇気をもって生きることが人生を完全で美しいものにする。
英雄的勇気とは向こう見ずあらず。それは知的で強靭な心。恐怖を尊敬の念と戒めへとかえることである。
名誉: 侍たる者、名誉に重きを置き、それをもって己の価値とすべし。
自らが下した決断とそれが如何に成し遂げられたかが、己の真の姿を映す。己自身から決して逃げ隠れすることは出来ない。
仁: 侍たる者、慈愛の精神を重んじ、あらゆる局面において同胞を助けるべし。侍は日々の鍛錬をつうじ、他の何人とも違う敏捷で強靭な存在となる。
その力は他者のために注がれ、そのような局面に出くわさずとも、自らの方法でそれを見つけ出す。
誠: 侍たる者ことを実行すると言った際、それは行われたも同然を意味する。いかなるものもそれをとめることは出来ない。
忠:これに関しては軽く扱われている。
ズイック達はこのように「武士道」をまとめている。随分とハイカラと言うかグローバル化された「武士道」理解だが、簡潔にして要を得た、理解で僕はこれに基本的に賛成である。スティーブン・ナッシュの「日本人と武士道」(角川春樹事務所、西部萬訳)という本が出ている。1997年刊だからそんなに古い本ではない。この人もまた日本女性と結婚している実業家で、経営コンサルタントでもあるようだが、六十過ぎて哲学者、思想家を自認し始め、このようなテーマの本を書いた。この人物の日本人や「武士道」理解とズイック達の認識は非常に近いものが感じられる。多分、参考にしたのではないか。ちなみに、彼等が参考にしたものを、ついでに、推定として、挙げておけば、新渡戸稲造「武士道」、内村鑑三「日本と日本人」、ベネディクト「菊と刀」、「葉隠れ」その他「武士道」についての古典や国学系の古典、儒教関係の書籍らが考えられる。
ズウィックやナッシュにしても帝国主義や近代主義、分けても拝金主義、個人利己主義、快楽主義、浅薄な意味合いでの合理主義、科学主義や物質主義に批判的であるが、しかし、マルクス主義を素養にしてない点で、その近代主義の根元が資本主義生産様式や市場原理にある事は捉えられていない。所有関係の不公平を隠しての市場競争の公正という欺瞞、搾取という不公平の欺瞞が資本主義社会の限界、問題の核心であり、これはマルクスの指摘するところであり、それを僕は「原則的資本主義批判」としているのである。
或いは、この意味でこの不公平を是正する位置に置かれている労働者階級ら人民大衆が歴史の主体であること、その人民大衆の一人ひとりが人間として、自主的主体になるにはどうしたら良いのか、このような観点で国と民族の主体、人民大衆の前衛はどうしたら良いのか、この根本としての人間自主主義の観点はズウィックらには、希薄であり、それ故に、ラジカルな近代主義の批判者、変革的前衛的言動がありながら、民衆を中心とする変革主体形成、新しい人間観と未来社会の構想と創造という点では一貫性、系統性を欠き、取り止め目のなさ、ちぐはぐさを持つことは確認されなければならない。彼等は僕のようなマルクス主義の素養を踏まえ、人間自主と民族を考え、武士道の復権、揚棄を問題にする代わりに、ストレートにピューリタ二ズムや騎士道精神から、批判、変革の問題を考えているのであろう。この点で、「革新保守」、戦前的な意味合いでの戦前の「近代の超克」派の弱点、限界を共有しているところもあるように思われる。
とは言え、彼等の名誉のために、次のことはしっかり押さえておくべきであろう。日本の保田與重郎や亀井勝一郎ら「近代の超克」派、「日本浪漫派」が、「近代」を批判し、日本主義、日本精神を対置しながら、その問題を、その近代の根元である資本主義の問題から捉える事をせず、資本主義の丸々の肯定を前提にし、西欧や他国、他民族との関連で「民族」や国家を論じたのであれば、それがどうしても国家主義、超国家主義や天皇主義ファシズムとして帝国主義的侵略の補完者に結果したのは、必然であった。
この点でズウィック達は、ピューリタント理念や騎士道理念からであれ、利潤第一主義や仁義なき市場競争、帝国主義や侵略主義を批判しているのだから、基本的には「真の近代の超克派」に近いのだから、日本の「近代の超克派」とは厳格に区別すべきなのである。「近代の超克」志向に伴う、問題点、弱点を指摘したわけだが、資本主義・近代革命は個の確立、自由や平等その下での自由な競争、合理主義や科学的精神を推奨し、因習と身分制、観念論的な思想に覆われていた封建制を打破してきたし、今もそれが続けられている、と言った、ごく当たり前の歴史的意義を我々が自らを「真の近代の超克」派と自称するなら、この派がそれらを、否定しているのではないことも、当たり前のことと、ついでに確認しておこう。
近代個人主義や自由主義の止揚こそ目指しているのである。資本主義的の個人利己主義と一体の個人主義、自由と平等の思想、或いは合理主義や科学主義は資本主義の原則的批判を踏まえ、人民大衆中心、人間自主主義で、民族や人類、民衆の共同性(民族や人民、人類に裏打ちされた人間自主主義)を活かすことに於いて、こう言ってよければ新しい「自主社会主義」によって止揚されるべきなのであり、近代の成果、それ自体を否定するものではない。その止揚の要石にはマルクス資本主義批判が据えれなければならないが、マルクスのプロレタリア革命、社会主義、共産主義革命の政治思想、学説、唯物史観の歴史学説には人間論、人間自主思想や国や民族に責任を持つ思想が欠けていること、つまり主体を形成する根本思想がかけていること、その結果スターリン社会を生み出したり、近代主義にマルクス主義は変容していき、破綻したりするのである。そしてそのことの、マルクス主義における克服は、このことを補充すると言った「マルクス主義へのその補充、手直し」といった方法では不可能で、マルクスの思想を人間自主論で、根本的に組替える方法をとるべきである。「つまり、人間自主の人間観からの「マルクス主義の超克」でなければならない。この観点、立場、方法原理において、「マルクス主義」は超克され、それは『真の近代の超克』ともなる。
経済学的に被搾取の地位にあるからからといって、そのことで労働者が人間的に優れていて、その思想的、倫理的高さから、自然に「階級的団結」できたりするわけでもないし、そのままで革命的階級となったり、実態としての、資本家が実態としての労働者に、人間的に劣っているわけでもないし、社会や民族や国家や人類の指導的階級になったり、新しい資本主義を超える社会(マルクス主義では「社会主義社会」)を創造してゆけるわけでもない。民族としての「国民国家」を超えるには、人類や民族、その社会の最高に良き文化、教養を継承した前衛的インテリゲンチャー、革命家が自主自尊の精神で、労働者等民衆の要求、生活感情を理解し、人民の中にある独立自尊、共同の生き方をそだてあげて、革命的インテリゲンチャーと労働者等民衆が融合し、自主的な人民大衆となって、資本主義を超える力、民族に責任を持つ階級、人類的共同性を創造する力を持ってこそ、はじめて労働者は民族、国民の指導的勢力となり、それを実現する。
労働者等人民大衆は資本主義への批判と同時にそれを揚棄する寛容さ、包容力を身につけなければならない。決して資本主義賃金奴隷制や搾取制への階級的憎悪だけが変革の原動力と成る訳ではない。根本は自主性や創造性、意識性などで構成される人間的な主体的な力なのである。この力が民衆の中に培われ、民族精神、文化の推進力となってこそ資本主義の変革はなされる。「近代の超克」はなされる。
マルクスの「資本論」に代表される資本主義批判はマルクスの最大の人類、人民への功績であり、民衆はこれを解放の武器としなければならないが、それは解放のための半分の武器以上ではなく、人間自主論をベースとする主体形成の哲学、世界観、路線が無ければならない。否、主体形成の哲学に包摂されてこそ、資本主義批判は革命的役割を果たすのである。僕はこのことを「幸福論」で主張し、「人間は社会諸関係の総体(アンサンブル)である」というマルクス人間論の限界を指摘し、「人間は自主性もった社会的存在」という場所的弁証法と過程的弁証法を統一する人間観。人間解放の哲学を展開し、マルクス主義の超克を宣言した。マルクス思想には場所的弁証法の視座が欠けているのである。
さて、以上を踏まえ、「真の近代の超克」にまつわる諸問題をまとめて見よう。
一、市場原理と資本主義は様々な問題、欠陥を産み出し、これに鋭敏に反応し克服せんとする思想が産み出される。その重要な潮流として、資本主義社会以前の諸社会で作り出された、良き民族の文化、伝統、文明を活かして、克服せんとする潮流が排出する。それが「近代の超克」志向といえるものである。しかし、「近代の超克」はマルクス思想、とりわけ資本主義批判、階級闘争学説の業績を無視する傾向が強く、あっても市場原理批判に止まり、資本主義を前提にして志向するところが強く、或いは克服方向を過去の文化を見習う方向が強く、後ろ向きに求め、資本主義を人民大衆を中心にして、前向きに止揚する志向が弱い。
二、マルクス主義もまた、ある意味で本来的には、この「近代の超克」志向に属するものと言って良い。マルクスの「資本主義批判、階級闘争、プロレタリア社会主義革命」はその骨組みに於いて、まったく正しいが、階級、階級闘争とその歴史に於いて、主体的、歴史的な自主の人間的営為が欠け、場所的弁証法、主体形成の哲学が欠け、その結果、資本主義革命の成果の無視やそれ以前の社会の文化的、文明的伝統を活かす方法論を持たず、封建的社会主義の偏向を持つスターリン社会やその反対の近代主義社会に溶解する結果となっている。
三、「真の近代の超克」はマルクスの学説を踏まえつつ、その限界を補い、再構成・超克した、人間と人民大衆の自主性を核心とする、人民大衆中心の人間観、つまり主体形成の哲学からなされる。人間自主、人民大衆中心の哲学に於いて、場所性における人間の要求・感情や諸社会や民族、人類の協同の文化、文明の成果は初めて前向きに総合される。マルクス主義の側から見れば、自主人間観のもとに階級闘争論、社会主義論を民族や人類のコンセプトを加えつつ、再構成し、超克すると言うことである。このことに於いて初めて資本主義は揚棄される。
四、この点で「マルクス主義の超克と近代の超克」は人間解放の志向において交差し、一方の「資本主義批判、階級闘争、社会主義」の主張、他方での、民族や国、地域の文化、文明、そしてそこにある人間的矜持、尊厳の堅持と相互に補い合いつつ、融合されるべきである。こういうこととして、階級闘争至上主義ではないにせよ、資本主義批判を堅持し、民衆中心で、人間自主を基本にして、アメリカへの隷属体制、グローバリズムを批判し、新しい人間観、社会観を創り上げ、確立するには、民族の主権、文化、伝統の揚棄を考えることは、ますます必要となっている。毛沢東思想に思想的核をもった、中国革命、戦後のキューバ・カストロ革命、或いは今進行中のイスラム思想と結びついた諸革命闘争らは僕が問題にするところの革命思想創造の志向性が、未完で玉石混交ながら、内包されているである。これらにこそ文字通りの真の「近代の超克」志向は内包されている。未だ、しっかりと正体を現していないチュチェ思想もまたこの範囲にかかるものも持っているし、そうとしても設定しておかなければならない。いずれにしても、「民族」が関係し、民族が伝統的に築いてきたラジカルな革命思想が問題となるのである。
後編へ行く