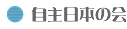





|
映画評 「血と骨」
塩見孝也
(一)「血と骨」を観て-―――我が混乱
この映画を封切りで見落とし、「もうビデオまで無理か」 と思い、諦めかかっていたわけですが、この間、観たいと思っていた他の映画を2〜3本、立て続けに観たので、「この映画も見てしまえ!」と矢も立てもいられなくなりました。
「未だどこかでやっているに違いない」と思い立ち、「それならば」と頭を働かせ、パソコンで検索してみました。
すると、銀座と池袋で2月12日から再上映されることを発見しました。
早速12日、新文芸座に出かけました。立ち見はなかったですが、満席でした。
普通、良い映画、名作というものは、それを見た後、非常にいい気持ちになり、帰途の足取りも軽くなるものである。感動させてくれるのです。
僕は、それを「映画の醍醐味」と思っています。
しかし、この映画は、こういった常識を超え、ストレートにそれを与えてはくれず、反対に、重く、暗く、ある種の怒り、憎悪の感情に絡んだ衝撃をもたらしました。それは激烈なものでした。
この、映画はストレートな爽快感を観客にもたらさない。暫くの、反芻が必要なのである。
段々に効いてくる、重いボディー・ブローのような感じです。
この感情の起伏は、珍しくも一週間ぐらい、続きました。家族や友人にその感情をぶちまけ、当り散らす始末でした。
この映画を見て、素直に大感激し、帰って行った人は少ないと思う。
一週間ぐらいは、あの“おぞましさ”が頭から離れず、それを考えさせ続け、疲れてしまうはずです。
余りにも、バイオレンスとセックス描写の印象が強いのです。
バイオレンスとセックスは人間存在の最も奥深くにある本質にかかわる行為である。
であれば、この映画は、この最要衝に突き進んで、強烈な印象を与える点で、只者ではない、といえます。しかし、幾らかは、その一線を越えるような挑発的要素も含まれていると言えます。
たけしが、無道な暴力を振るい、家族や周りの人をないがしろにするたびごとに、僕も、堪え切れず、我を忘れ憎悪の感情を募らせていったわけです。
この意味で、僕は、完全に俊平やそれに対する人々に想い入れをさせられ、映画の虜になっていたわけです。
つまり、僕は、否定的に「金俊平」に、強引に、感情移入させられ、冷静に映画を見ていけなくなっていたと言えます。
後で、良く考えてみると、これは崔監督の深謀遠慮、仕掛けであったと思われてならないのですが、僕は、不覚にも、まんまとこの監督達の作戦に嵌められたわけです。
「映画的には良く出来、成功しているが、思想的には駄目な映画ではないか?」
「金俊平のこれでもか、これでもか、の暴力性、セックス場面のどぎつさ、あれはなんだ!あの“凄さ”は保留するぞ!」
「自己保存本能のままに、家族や女性らに傍若無人に振舞い、恬として恥じない、あの倣岸さ、エゴ性、力信仰、あれはなんだ!」
僕は、リアリズムの手法のイロハも忘れ、猛りくるっていたようです。
「差別や戦争反対など、まともに取り上げていないではないか!」
「単なる糞リアリズムの、エロ・グロ志向、ホラー映画の類に過ぎないではないか!」
「たけしの動物的力、暴力信仰は相変わらずだ。たけしは絶好の自己表現の場を得た!」
「もっと映画作りにおいて他の表現方法が考えられるはずだ。余りに挑発的だ」
「だから、オダギリジョーのたけしが、敢然として、俊平の暴力に反逆してゆく時、観客は歓呼し、オダギリのカッコよさ、演技性を評価するのである。」
世の先端思想をたちどころに理解し、批評できると自負するこの僕が、不覚にも、冷静さや思索慣習も吹き飛ばし、それ自体、まっとうで健康な、世の善良なる庶民、とりわけ女性達の普通の感性、庶民的感情のままに拝跪して行ったともいえます。
挙句の果てには、以下のように当り散らしたわけです。
「崔洋一監督は、『クイール』などにも現れるように、もっと思想的にわけしりでまともな人なはずなのに!」
「ヤン・ソギル(梁石日)という作家はしっかりした在日の文学者なのにどうした事か!脚本の鄭義真氏や崔氏が原作を捻じ曲げているのではないか!」
「結局は、当世の朝鮮国や日朝関係の困難さ、閉塞性の反映であり、商業主義的映画作りの限界を反映したものではないのか?」
最後には「映画作りとはこういうものであっていいのか!」とさえ思いました。
僕の怒りの想念は、このように、留まるところを知らず、一時際限もなく、エスカレートしていったわけです。
だが、他方で、「俺の“在日”理解や映画理解はまだまだ、表面的で、教条主義的ではなかったのか!」
「暴力批判の思想にやわなところがあるのだろうか?」とも反省してみたりし、「俊平にも、幾つもの、屈折した形であれ、“人間的”な所も表現され、家族等周囲の人々、特に女性達は、映画の中でも、俊平に一片たりとも妥協していず、徹底的に批判的で、中には辛らつな復讐もやってみせ、生命性に立脚する力信仰は、老いの深まりの中で、無残に因果応報的に破綻し、俊平はしっぺ返しを受けているではないか。男性中心の家父長思想は、巧みに徹底的に批判されているではないか!」とか反芻しました。
或いは、崔洋一監督は、どんな映画表現の原則を持って、5年も6年も、この映画作りに集中出来たのか?
生半可な思い付きなどで、あんな映画は撮れるわけがない。よほどの、確信が無い限り、5〜6年の堅忍の映画作りは出来ないはずだ。
それは何なのだ?
しっかりした、映画としての表現原則、原理、基準が無ければ、あのような一筋縄ではいかない俳優人が、こぞって、全力を挙げて自己の役柄に熱中し、全員が一丸になるほど結束し、なぜあのような熱気むんむんのエネルギーが立ち込めるのか、が説明できない、など、僕の内面に、逆に強い、反撥も生まれてきました。
最後は「とにかく、ヤン氏の原作を読んでみよう」「映画をもう一度、冷静に思い起こし、原作とのヅレがないかも確かめてみよう」に落ち着きました。
それで原作「血と骨」と「“恨み(ハン)”をのり超えて―――修羅を生きる」をとりあえず図書館に駆け込み読んだのでした。
(二)描きあげながら、同時に批判、否定するリアリズムによる巧みなストーリー展開
映画は若き金俊平(龍一、伊藤淳史)が「君が代丸」に斉州島から乗船し、大阪に辿りつくところから始まる。
1920年代半ばの話である。
煙突がにょきにょき立ち並び、煤煙が煤気だって空で覆っている大工業都市、大阪が見えてくる。
俊平は、きっとエリア・カザン「アメリカ、アメリカ」、トム・クルーズの「遥かなる大地へ」、或いはデカプリオの「ギャング・オブ・ニュ―ヨーク」など、アメリカへの一旗組みの移民の若き青年と同じような感懐を抱いたであろう。
或いはシシリーからの「ゴッドファーザー」の一統の青年達のようにです。
次は、もう一人の主人公、ヒロイン、李英姫(鈴木京香)が岸和田の工場を追われるシーンである。英姫もまた、日本に出稼ぎに来た斉州島出身の朝鮮人である。
それから、約20年後の終戦に一挙にとび、徴兵を逃れ、全国を流亡し、何年も家を空け、家族をほっとらかしにしていた俊平(ビート・たけし)が英姫や長女、花子や長男、正男たちが住む猪飼野の朝鮮人長屋に帰ってくる、シーンとなって行きます。
英姫ら3人は俊平を恐れ、敬遠しているようである。
俊平はいきなり、妻の英姫に「こっちへ来い、脱げ!」と威圧し、嫌がる英姫に強姦まがいにセックスしようとする。
もみ合いが続き、英姫が半ば犯されかかっている最中に、義理の弟,高信義(松重豊)が復員の挨拶をしに来ます。
俊平は、「事業をするから、お金を4万円ほど用意せよ」と英姫に言いつけ、ぷいと外出して行く。
この、展開からだけで、俊平がどれほど身勝手、無軌道な自己中心主義者、妻や子供に横暴で、並外れた体と体力を利して、人を力で人をねじ伏せ、それで人間関係の秩序を作れると信じこんでいる暴力主義者であるか、女性を性的対象、自己の従属物としてしかみない、女性蔑視、抑圧者であるかが、強烈に押し出されてゆく。
おんななしには一日も過ごせない強精者、その強精をコントロールできず、無軌道に、傍若無人に発散させる、自己中心主義者であることも、遺憾なく鮮明にされる。
元蒲鉾職人であった俊平が蒲鉾工場を起工してゆく展開は、一番リアリティーがあり、家族が総動員されたり、職人達が暴力支配されたり、豚をつぶし、それを皆に分けたり、その肉を石油缶につめ、腐らし、湧いたウジとともに、俊平が健康食として、食うのも如何にもの、朝鮮人長屋の風景である。
しかし、ここでも俊平は徹頭徹尾吝嗇で、儲けを家族には全く渡さず、職人達を昔ながらに暴力支配でこき使い、搾取する。
人に金を与えれば、反抗するか、離れてゆく、という信仰である。
彼は、決して事業を拡大したり、他の事業に投資したり、おんなに多少の金を投資したりしても、決して贅沢をさせたりしない。
自分もまた、贅沢せず、節約する。このことは、又彼にとって全く当然なことでもある。
資本を拡大再生産してゆこうとする近代的経済思考とは無縁で、ひたすら単純再生産で、溜め込み、人を無一文にし、繋ぎとめ、支配しようとする思想である。
本吉(北村一輝)との格闘シーンも凄い。
ここで正男は「やっちまえ!」と本吉を応援するのである。
同郷で、俊平が不良少年の頃、憧れていた、斉州島一の美人の誉れ高かった、女性で、夫とともに日本に来ていた人妻を強姦し、生ませた、その子供、やくざの朴武(オダギリジョー)が「息子である」と名乗りを上げ、突然舞い込んで来る。
武の母はこれが原因で病死(実質、自殺)した、という。
27年して、その時の子供がふらりと現れるのだから、驚愕しつつも俊平は、彼を認知し、同居を許します。
始めから、武は父親の掣肘下に入らず、「婚約者」を呼びつけたり、平気で周囲を無視し、狭い家屋の中で行為をしたり、他の周囲の人と全く違って、平然とし、強権的、暴力的な、家長のボス、俊平への反逆を隠さない。
彼は、ピストルなど持ち出す。
やくざ同士の抗争の渦中で、隠れ家として俊平宅を利用しつつも、実は、父親に自分を捨て、母を自殺に追いやった、俊平に復讐しようとやってきたわけである。
柄も体力も巨漢で、父親に遜色なく、度胸も据わっている武に正男や周囲は憧憬するようになり、父子は一触触発の状態となる。
そして、それは爆発点にいたる。
「27年間ほったらかしにして、少しぐらい金をだしても損はないだろう」と武は家を出る際、父親に金を無心する。
「何処に金がある。わしには一銭の金もない」
武は俊平が、自分の部屋の壁側に、隠していた数百万の金を暴き出す。
「俺の眼は節穴じゃねえ。こんなところに隠しやがって、あきれるぜ。生まれたばかりの俺を見捨てたんだから、俺に百万や二百万くれたって罰は当たるまいに」
「この盗人野郎!」
長屋の戸をぶち破って、取っ組合いつつ、外に転がり出る凄まじい雨中の格闘が展開してゆく。
溝の汚水の中に、頭を押し込まれたり、はねかえして頭突きをかましたりし、逆に、溝に押し込んだり、の格闘である。
引き分けられ、英姫は鷲ずかんできた、札束をたけしの懐に押し込む。たけしは正男に去ってゆく際、「勉強しろよ」と一声、声をかける。
それから十日後、武は抗争中の相手側に刺され、あっけなく死んでしまう。
「自業自得だ。あんな奴,生きていても世の中のためにならん」と俊平は嘯くのである。
次第に成り上がった俊平は、武のような、対抗的に制止する力ある人もいず、その後は全く勝手放題、したい放題である。
新しく家を買い、若いおんな、清子(中村優子)を囲う。
時代の流れの中で、終戦の混乱期に独占企業として成立、可能であった蒲鉾生産は、競争相手が乱立し、俊平は工場をたたみ、金貸し業に転じて行く。
ここでも、強引な取立てなどで、自殺者も出るほど、悪業の限りを尽くす。
子供が生まれない清子は脳梗塞に陥り、退院してからは俊平が彼女を、珍しくも、面倒を見る。
最初は、大きな金だらいで入浴させたり、下の世話もするほど、献身的であった。
が、それも限界で、介護名目で新しい愛人、定子(濱田マリ)を迎え、二人の間に子供も次々と出来てゆく。
清子の定子への嫉妬や介護の限界などもあり「楽にしてやる」と称し、俊平は彼女を窒息死させる。
子供達の面倒もみず、俊平が勝手放題をしてゆく中で、英姫との仲は完全に冷え切り、子供達の養育も彼女だけが面倒を見、子供達は父親を憎み、反抗し始める。
清子が病気で倒れた際、俊平は再び、家族に八つ当たりし始め、酔っ払い、幾度も家を目茶々にし、花子に難題を吹っかけたり、暴行を働き、彼女は、堪らず、猫いらずを飲んで自殺を図ったりする。
花子(田畑智子)は工場で働く張賛明(柏原収史)にほのかな恋心を抱いていたが、非合法組織「祖国防衛隊」に身を投じていた彼は逮捕されてしまう。
別の男と結婚した彼女に幸せは来ず、出獄した張は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)に帰国してしまい、以来一切の音信がなくなる。
心を閉ざした花子は、ついに首吊り自殺をしてしまう。
花子の告別式の際、暴れこんで来た俊平は、脳溢血を発病し、下半身麻痺に至る。
これを境に、頑丈な体、体力に基づく俊平の “永久の強さ”幻想は崩れ始め、以降、「弱体化」、老耄への人生が始まってゆく。
英姫もまた老い始め、癌となり、正男(新井浩文)は、父親に治療費を出すように頼み込むが、拒否され、堪りかね、父親に挑戦するが、返り討ちに会い、以降、ゲリラ戦を開始する。
英姫はその際、それまで、夫婦をずっと維持してきたのに正式な離婚の決意を息子に伝える。
だが、その理由は遺産を他の女に横取りされないようにするためである。
父親が、暴れこんでくるたびに、定子と住む俊平の家を、逆にカウンター的に、襲撃し、仕返しの打ちこわしをやり、逃げ去るのである。
徐々に正男は父親を恐れなくなり、自立してゆくのだが、ついに英姫はなくなってしまう。
斎場に皆が集まっている際、招待されなかった俊平が、別の用事にかこつけて現れ、高信義が列に加わるよう誘うが、彼は、結局その輪に入り込んで行けない
傍若無人、勝手気まま、自己中心に生きた俊平の人生に黄昏が迫る。
定子には、殴られ、金を持ち逃げされ、成人した正男に事業の共同経営という名目で、老後の面倒見を頼み込むが、にべなく断られ、最後は、身を寄せるところを探しあぐね、莫大な寄付を形(かた)に朝鮮国に帰国する。
寒風吹きすさび、雪が舞う荒野のあばら家で定子との間にできた「嫡子」のみに見守られ、寂しく終焉する俊平の姿がラストシーンである。
因果応報、家族に見放された孤独極まる最後である。
(三)リアリズムに、崔洋一監督は“逆説”の演出手法を嵌め込んで、映画に生命力を吹き込んだ。
普通、リアリズム(自然主義)は、良きことと思われる主人公と思われる対象を、そのまま描くことで、そこに良きことが、自然と浮かんでくる手法である。
この手法を、崔洋一は、大方の意表をついて、「悪」の「怪物」と思われる金俊平を、その、「悪」の「怪物」性、反面教師性を際立たせ、典形化し、徹底化して描くことで、これを諸関係の媒介、背骨、心棒にして、在日コリアンの生き様の個々、全体的歴史を巧みに活写している。
又、この関係性を通じ、俊平をも、その「怪物性」が、特別の悪い因子でもなく、朝鮮人の歴史的、社会的要因から生まれてきたことも、――この描写を生れ落ちた斉州島から,それと無くでも示すべきであったろうが、それは原作にも欠けていた――示唆して行く。
こうしてしか、戦前、戦後、そして現在の「在日」の生き様は、映画的に表現できなかったし、そのことを才人たる崔監督は始めから、確信していたのであろう。
ないしは、映画制作に従事する早い段階で掴んだのであろう。
これは、逆説の演出手法といえるのではないでしょうか?
ここには、「権力対人民」「被抑圧民族対抑圧民族」或いは「素晴らしき指導者とそれについて行く民衆」などといった、今の時代では、教条と成り果てているような、必ず偽善性を孕むような図式は影を潜めています。
「正義派の典型」ではなく、俊平のような「悪の怪物」を配置するこの手法によってこそ、その対照関係の中で、相対化されながら、もがき苦しみながら、逞しく、その日、その日を生きる、「在日」の民衆の人間的姿が、何の思い入れもなくても、活き活きと浮かび上がって来ています。
それが李英姫であり、花子や正男であり、たけしであり、死産したり、飢餓で無くなったりする、俊平の家族たち等映画に登場する人々です。
正に、たけしという特異なキャラクターを持つ名俳優を得て、映画は「悪」であって、「悪」と言えないような、「もの凄い、怪物」を映像化することで、逆説の手法を嵌め込んでリアリズムの映画表現を徹底したのである。
そうすることで、現在を生きる「在日」に、過去の「在日」は、無理なく自然に連続されて捉えられるようになり、日本人民衆にも共感を得るようになるのである。
逆説の方法は、ダブル・スタンダードで複眼的方法であり、必ず、皮肉や風刺、カリカチュアを伴う。ある種の毒を伴わざるを得ないのである。
かくして、敢えて、観客を映画制作側は挑発するのである。
つまり、一時観客は、その有無と言わせぬ能動的働き掛けで、評価が混乱し、反感を覚えたり、誤解したりもするのである。
崔監督はそれを、敢えて、覚悟の上で狙っているのである。
それは、「悪」が正真正銘の悪とみなされるか、やむを得ざる歴史的、社会的存在から来る“人間としての歪み”に過ぎない存在であるかは、実はビート・たけしの個性に基づく演技の修練度如何にかかることになります。
カリカチュア性が完全に漫画になるか、否か,毒が毒々しくなるか、それが解毒されるか、も彼の演技一つにかかっているのである。
この意味では、ビート・たけしは一番難題を吹っかけられ、損な、憎まれ役の大役を、敢えて引き受けているのである。
俳優としての満々たる自負心が無ければ、とてもではないがこんな役は引き受けられないであろう。
そこに、彼の苦虫をつぶしたような表情表現が必要とされ、又この映画に備え、体を鍛錬、シェープアップする彼の並々ならぬ役者たらんとする努力もあったのである。
たけしは、一時は反感を感情的に招くが、冷静になり、振り返れば、又時がたてば、或いは見る人が見れば、名俳優であることが分かる、ずば抜けた好演をやっていると、やはり言わなければならないであろう。
たけしの事を僕はよく知らないが、予断と偏見を排し、映画そのもの、演技そのものを見れば、彼は、「北の零年」の吉永と違って、看板倒れに終わらず、監督から要請される極度に難しい役柄を、渾身の才質を出し切り、演じきっている、言ってよいのである。
ただし、たけしは弱いものいじめだけでなく、他の極道と闘う「勇者」の面も出すよう、或いは清子とのセックス描写が、実は英姫や子供達に対して、愛情を求めていながら、自業自得で、それが得られなかった結果、当てつけ的なものであることを演出してくれるよう言うべきでなかったか。そうでなければ清子とのそれは暗示程度にとどめられるべきでなかったろうか?
ここは、決定的ともいえる、一線を越えることで、余計な反感を誘ってしまうシーンであると思います。
これは、演出の至らなさで、たけしの責任とは言えないのです。
ともあれ、彼は自己の役どころをしっかりと理解し、それを果たしたという自負があるが故に「このような役どころを与えられ、演じきったことは役者冥利に尽きます」と毎日映画コンクールなどの受賞挨拶で、神妙に心から述懐しています。
(四)金俊平の存在とは? 彼は何者か?―――
朝鮮社会の歴史的、社会的現実の根っこから生まれてきた「もの凄い」「怪物」
金俊平が「悪の怪物」でありながら、勧善懲悪で罰される極悪の存在ではなく、観客が少しでも、想像力を働かせるなら、彼が、朝鮮社会の歴史的現実、その社会の根っこから生まれてきた一人の民衆的存在であることが分かるようになっています。
「亡国の民」となり果て、帰るべき故郷も無くなり、異国・異民族の社会の中で暮らす境遇であれば、拠るべき価値観、理想、倫理も失われ、そこで生き抜くための朝鮮人の人々のより所は、「民族的、民俗的」同質性や「同胞意識」、つまり、「血縁意識」で辛うじて、覆われてはいるものの、その裸の本質は、原初的な自己保存本能に基づく功利性、実利性、それに基づく、相互主義であったろう。
そして、その核心は知力、智力以上に唯一、確かなものとしての、己が生命力、体力、暴力性であったろう。
動物性を超克してきた人間の自主性、協同性は一時、社会的に剥離されてしまっているか、かろうじてあるに過ぎないのである。
人間は、社会的に培ってきた自主性(=協同性)によって、自己保存の本能、ある意味での功利性と相互主義を、社会の中で、継承しつつ、それを内面化し、文化、倫理にまで高め上げてゆく。そして、政治、経済が創出されてゆく。
そこから、人間は、尊貴すべき、利他精神、社会、集団に尽くす大義精神さえ生み出し、時には、命すらそれに捧げることを厭わない。
それは、朝鮮人にとっては、遠く大陸のキム・イルソン(金日成)らの「朝鮮人民軍」の中に生まれ始めていたかも知れないが、或いは、李小晩らの近代主義の中に存在していたかもしれない。
しかし、それは、「在日」コリアンの人々には、余りにも「遠く」、届いては来ないし、僅かに届いても、日本帝国主義官憲によって芽のうちに摘み取られてしまいます。
売国奴になることすら、手が届かないような、本社会の圏外にあるような「在日」にあっては、極道(極悪非道の者達)や、一匹狼のその類となり、その日、その日を生き、這い上がってゆく道しか残されていないとも言えます。
そして、この方向もまた、全体主義の天皇主義的日本社会であれば、未完で奇形的な存在のままで終わらざるを得ない。
このことは、「ゴッド・ファーザー」のビイト・コルレリオーネのような存在は「在日」一世の社会では、現れきれないのである。
戦後の田岡組長を中心とする「山口組」のような集団は存在し得なかった、といえます。
「在日」戦前朝鮮人社会では、中心は無かったのである。
このような中心なき社会ではであれば、誰も彼もがばらばらにされ、かろうじて、朝鮮人集落を形成し、そこでは「金俊平」の類は程度の差はあれ、誰も彼も「在日」であれば具備していた、ということである。
全ての在日コリアンは、特に戦前は、「凄まじく」「怪物的」に生きたのであり、そう生きざるを得なかったのである。
いわば、金俊平は、無教育、無教養のまま、朝鮮社会の根っこの部分にある、儒教文化や習俗を、長所、欠点ない交ぜにして受け継ぎ、その格段の生命力、体力、暴力性により、餓鬼大将が、そのまま大人になったように生きた存在といえる。
生存し、外敵と闘い、自己が独占するメスを防衛すべく奮闘するようなサル山のボスが、そのまま人間になったような存在である。
彼の中に牢固としてある、生命力、体力、暴力信仰、男尊女卑思想、男子嫡子信仰、特異な精力培養のいか物食いは戦前の朝鮮社会の根っこの部分に普遍的にあった思想である。
であれば、「凄いことは凄い」のだが、決して、彼は、人間の劣性の突然変異種でもなければ、人間とは異質な、宇宙人的存在としての「悪の怪物」「化け物」ではない、言えます。
だから、崔監督は俊平を「典型」にし、逆説の手法で、映画化できたのである。
(五)ヤン・ソギル(梁石日)が「血と骨」にこだわる意味とは?
彼の文学とは?それに何故崔監督が共感したか?
「血は母より、骨は父より受け継ぐ」
これが、映画のテーマであり、それは、ヤン・ソギルの小説、「血と骨」の題名にしてテーマをそのまま、使ったものである。
映画の冒頭は、この題名を大写しにしつつ
「これは、家族の物語である」
「これは、父と子の物語である」
「これは、夫と妻の物語である」
「これは、男と女の物語である」
とナレーションがやや荘重に、余韻をかもし出しつつ、胸にずどんと落ち込んでくる形で流されてゆく。
誠に見事な映画的出だしである。
映画も小説も、その表現の仕方は違っているが、僕は、原作を読んで、そのテーマが全く同じであることを確認しました。
崔監督はヤン氏と同じ、ハーフの朝鮮人であり、それもあって、ヤンの文学テーマに惚れ込み、それをもっとも、よく理解し、文学とは違う表現形式、映画で表現している、ということでしょう。
しかし、誤解なきように述べておかなければならないこともあります。
彼が、ヤン・ソギル氏とは違って、幾らか年代もくだり、日本人人の母を持つ身でもあれでもあれば、このことも関係してか、朝鮮人社会に釘付けにされ、拘束されてきた面は、はるかに少なく、人間を描くことにおいて、はるかに、コスモポリタンで、グローバルであるということである。
彼は、このことを「この映画を、『在日』や朝鮮人のために作ったと誤解されては困る」と強調しています。
「英姫にとっては二人目の子供だが、金俊平にとっては初めての、それも男児である。朝鮮の巫女の歌の中に、“血は母より受け継ぎ、骨は父より受け継ぐ”という一節がある。
朝鮮の父親は息子に対して、よく“お前はわしの骨(クワン)だ”言うが、それは家父長制度を象徴する言葉であった。血もまた骨によって創られることを前提にしているからだ。土葬された、死者の血肉は腐り果てようとも、骨だけは残るという意味が込められている。血は水よりも濃いいというが、骨は血より濃いいのである。言葉に出さないが、儒学者を訪ねて命名してもらったことが金俊平の愛情表現だった」
これは、俊平と英姫の間に生まれた長男で、生後7ヶ月をもって亡くなった、正男(原作では成漢―――原作者・ヤンのこと)の兄が生まれた時の、俊平についてのヤンの表現である。
朝鮮の人々は、父子双方ともども、古代より、こう思って、係累をなしてきたわけである。
日本人も又朝鮮、中国の文化的影響を受けつつ、こうも考えてきたのであるが、それでも、日本人には、その前に日本人の原基たる、これとは異質な一万年に及ぶ縄文時代があり、その影響は朝鮮人(韓国人、朝鮮人のこと)、「在日」程、根底的とは言えない。
しかし、「在日」の人々は、特に一世、二世の人々にはこのような想念が骨がらみにある、と言えます。
更に原作には次のような文章があります。
「成漢にとって、金俊平は父というよりは朝鮮の精神的風土の根っこに巣食っている正体不明の鵺(ぬえ)のような存在であった。頭が猿、胴体が狸、手足が虎、尾が蛇、声がとらつぐみに似ているといった不可解な怪物である。だがそれは乗り越えることの出来ない自己自身であり、何処まで言っても己の分身であるおのれが、またしてもおのれを産み続けるといった無限級数的な陣痛に悩まされるのだ。」
「一体自分は何者なのか?父であり、夫であり、男であり、力の象徴であり、この世界に対する自己顕現の意志を暴力によってのみ貫徹できると信じているのだった。」
この二つの原作からの引用で明らかなように、ヤン・ソギル、成漢の、「血と骨」に流れる一貫したテーマは、父、金俊平が「在日」社会に、根を張る「鵺」のような「物凄い」「怪物」であったが故に、一般の朝鮮人、「在日」の人々の嫡子の息子とは、違って、父との確執、闘争、訣別、自主・自立、平たく言えば「親離れ」の課題は、宿命的ともいえる生涯のウルトラ・スーパーな課題足らざるを得なかった、ということです。
ヤンはこの死闘、そしてその自己確認として「書くこと」を経てしか、自己を最後的に確立し得なかった。
それなしには、生きてゆくことは出来なかったのでしょう。
朝鮮半島の朝鮮人達を分裂させ、相争わせた冷戦期とそして現在に至る「冷戦終了」期の別の混乱、「和解」の模索の時代背景も加わって、「在日」の世代間の闘争は、壮烈なものであったでしょうし、金父子にあっては暴力的闘争を含む全面的な、政治的、思想的、文化的緊張が絡む激烈なものとならざるを得なかったわけです。
そして、それは、父子である以上、どこかで信じあうようなところがあったにせよ、父親への強い否定の感情、憎しみを直接の原動力にしていたわけである。
ヤンはそのことを「“恨み”を超えて―――生きる」で克明に綴っています。
それが、崔演出を経て、時には一線を越える形で、表出されざるを得なかったのであろう。
ヤン・ソギルは僕とは五つ違いの年上であり、僕のような団塊の世代−全共闘世代の一番年上より更に年上であるが、基本的には戦後世代であり、島さん(第一次ブント書記長)ら新左翼と同時代性をもった世代である。
彼の「生きる」を読めば、彼が「在日」の「新左翼世代」であることは明らかであり、労働党や朝鮮連盟、朝鮮総連に反逆し、スターリン主義的な「マルクスス・レーニン主義」の偽善に感性的に反撥した、若者の流れの中にあったことが読み取れます。
彼は、それを若き日、最初、詩作や文学で表現したようであるが、この流れは、すぐには政治的に結実してゆかず、早産で挫折せしめられる。
父の援助と掣肘下、それと闘いつつ、事業家として挑戦するも破綻し、長く自失と退廃の淵を彷徨い、やっとタクシー運転手として落ち着き、10年間この職業に従事したようです。
彼は、その運転手稼業の10年間を「私は、初めて労働とは何か、を知った。労働の中で、私は、過去の傷を癒すことが出来たのだ。汗を流し、誰にも迷惑をかけず、誰の世話にもならず生きることが如何に大切であるかという単純にして明快な答えを得たのである」と、しみじみ述懐しています。
その後、作家となったようである。
余談ですが、ヤンは作家になった後も、「父を反面教師としながら、別の意味で、つまりエゴイストという点で、私は父にそっくりだったのである。そしてなぜ作家になったのかといえば、私は断念の思いを悟れなかったという他は無い。
私は、この原稿を書きながら人生の付けをいつかどこかで必ず支払わされることになるだろうと考えている」と示唆深いことを語っています。
この書く作業の中で、自己の人生を振り返り得、宿業のテーマであった、「父の呪縛からの脱却」を、「血と骨」として文学化しえたことによって、彼は父の呪縛から相当解放されたのである。
こう見てくれば、この文学は、とりもなおさず、彼の「在日」2世世代のアイデンティティー,共同主観の文学化であり、その次の、三世、四世が、その後、生きてゆく思想的ベースを文学的に提供したものと思われ、更には、在日二世が、一世とは違って、日本人社会に溶け込み、生き、政治的にも、同じ日本人世代と共通する波長で生きたことにおいて、広くは、日本人戦後世代、新左翼世代の文学でもあったと思います。
僕は、彼の二冊の作品を読み、このことを強く感じました。
このことが、在日の映画監督の下ではあれ、日本人俳優が、全ての朝鮮人役をやるといった一見奇妙な事態を生み出して行くのでしょう。
彼の文学が、自分の体験に立脚し、自分の頭で考え、自分の言葉で実現されているからである
そうであるが故に、特別な教条やイディオロギーで作られ、必要以上に垣根を巡らしていた、これまでの「在日」文学と違って、簡単に俳優達に理解と共感を得たのである。
僕が、反撥し、アレルギーをもようした、金俊平の描き方は、実は、「在日」の二世世代が、必然的に惹起されざるを得なかった、一世を厳しく、憎しみを持って批判的、否定的に見ざるを得なかった普遍的な問題であり、その出所は、他ならぬ原作者、ヤン氏その人であったことは、今では明らかである。
余りにも激烈な世代相克、ヤン氏の、父の呪縛からの死に物狂いの脱却のための闘争、そこでの憎しみの感情の強さ、比重の大きさ、それこそが文学のバイタリティーを生み出し、それが、崔監督に憑依し、“逆説の演出”で理論武装した崔氏のリアリズムの手法となったのであろう。
そこに、時には一線を越える、どぎつさも一部生まれざるを得なかったのであろう。
確かに、ヤン氏の金俊平像は強烈な批判精神で満ち満ちてはいるものの、
原作を仔細に読めば、幾らかは、原作とズレがある形で、ゴジラ化されたきらいは無きにしもあらずではある。
嫡子誕生の際は儒家に命名を頼みにいったり、英姫たち母子が俊平から逃亡するも万策尽きて、彼のところに帰ってくる際、何も言わず受け入れていること、戦争中成漢を伴って流亡し、彼なりの可愛がりをやっていること、成漢が事業を始める際は金を貸していること、このような原作には記されていることが省かれています。
始めて惚れ、入れ込んだ八重への失恋が大きな傷、トラウマとなり、女性不信の起点となっている人間的面があること、極道たちとの喧嘩、戦いは男としては名誉ある武勇伝に属し、俊平は弱者いじめだけをしていたわけではないこと、このような事情、俊平の格好良いアクションなどは省かれています。
高信義ただ一人にせよ、友人的関係を作っているわけだが、映画では、自分の手代的役どころとなっていることもあります。
このような、ヅレを指摘しようとすれば挙げられないこともないのです。
そうすれば、極端化された金俊平象へのアレルギーも、幾らかは緩和され、テーマがもっとすっきり出たかもしれません。
セックス描写については、僕には未だ良く分からない。
しかし、(二)でも述べたように、原作でもそうだったように、清子とのセックス場面は、監督の勇み足で、原作との二人の対話で暗示するぐらいでよかったのではないか。
別の俊平の行為を持ってくるべきではないか?
ここで、崔の師、大島渚「愛のコリーダ」張りの実写は不必要と思われます。
とはいえ、このような省略と挑発的「逆説の典型化」こそ映画なのであろう。
映画であれば、小説と違って、作者の解説は表に出すべきではない。
それは、小説家とは違って、監督、俳優達の独創性、想像力で、観客の視聴覚的判断に任せるべきである。
ナレーターとしての正男(成漢)は終始,後景にあり、控えめであってよい。映画は時間的制約を伴い、小説の読者層とは異質な、時にはそれより圧倒的に広い厖大な民衆を相手にしなければならない。
小説は一人の作家に負うところが多いが、それでも社会の民衆に必要とされ、読ませてゆく、システムと無関係ではありません。
それ以上に、映画は、厖大な民衆を相手にする、企業であり、利潤とどう折り合わせなければならないかは、至明の前提であり、この問題をクリアーする監督ら製作人の社会的ヘゲモニーが問われます。このことも、頭に置いておかなければなりません。
だからこそ、映画にあっては、テーマは同じであれ、原作者には、想像も付かない、独自のそれでいて、テーマを壊さず、逆にそれを豊かにするような、独自の苦楽を伴う、映画人のみに与えられたイマジネーション、創造力、演出が必要とされると思います。
それは、映画の各所に見受けられますが、崔監督や俳優陣はそれを九分方クリアーし、あまりあるものがあるのではないしょうか。
映画は、問題作であることに論を待たないが、やはり、欠点もあるが、それおも帳消しにする、崔監督固有のスケールの大きさ、鯨のようになんでも飲み干してしまうようなエネルギーを凝集した名作と言ってよい。
「在日」を対象にしつつも、「在日」を越え、朝鮮人全体も、日本人をも包摂した、“愛”と言っても良い、人間、人類の普遍的問題に迫っている点で、バイタリティー溢れる名作、それも歴史に残るような作品と言って良いと僕は思うようになりました。
2005年 2月 22日
|
|

